SNSを使ったマーケティング手法の一種であるインフルエンサー・マーケティング。フォロワー数の多いインフルエンサーは、他のユーザーに対して大きな影響力をもっており、非常に高い広告効果があります。
「インフルエンサーマーケティングの効果やメリットを知りたい」「デメリットや注意すべき点はある?」とお考えの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、インフルエンサー・マーケティングの概要や方法、注意点などをご紹介します。
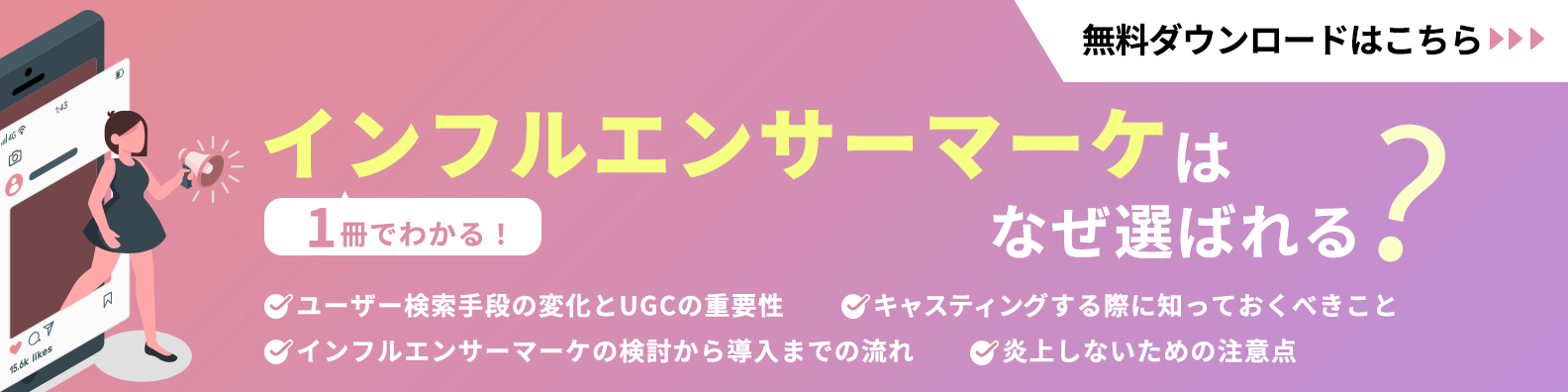
インフルエンサーマーケティングとは

インフルエンサー・マーケティングとは、Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, SnapChatなどのSNSを使用するユーザーを利用したマーケティング手法のことです。
企業がフォロワーユーザーの多いインフルエンサーたちに自社製品を紹介してもらうことで、既存のフォロワーにリーチでき、潜在顧客(消費者)の獲得につながります。
インフルエンサーの種類
インフルエンサーは、影響力や知名度のある人のことを言いますが、どの程度影響力があるかによって呼び方が変わります。
大きく分けて、次の4つの種類があります。
|
種類
|
フォロワー数
|
特徴
|
|
トップインフルエンサー
|
100万人~
|
テレビやメディアへの露出が多く、知名度が高い芸能人や著名人。影響力は大きいものの、フォロワーとの距離が離れている印象を持たれる場合がある。
|
|
ミドルインフルエンサー
|
10万人~
|
SNSを中心に人気を集めており、ジャンルに特化した情報発信をしている。各ジャンルに興味関心のあるフォロワーが多い傾向にある。
|
|
マイクロインフルエンサー
|
1万人~
|
ミドルインフルエンサーより専門的なジャンルやニッチな分野で活躍している。
|
|
ナノインフルエンサー
|
~1万人
|
特定のコミュニティやジャンルで知名度のある存在。学生や主婦などにも多く見られる。フォロワーとの距離感が近く、エンゲージメントが高い傾向にある。
|
インフルエンサーマーケティングでは、もっともフォロワーの多いトップインフルエンサーを起用すればいいわけではありません。
トップインフルエンサーは、多くのフォロワーを抱えているほど拡散力は非常に高いですが、共感力は低くなっていきます。
ユーザーのエンゲージメントを増やし、消費行動を狙うためにはミドル〜ナノインフルエンサーを複数人起用するといった方法もおすすめです。
▼参考記事
SNS別のインフルエンサーの特徴
続いて、代表的なSNSプラットフォーム別の特性や、インフルエンサーの特徴を見ていきましょう。
|
SNS
|
特徴
|
|
Instagram
|
いわゆる「インスタ映え」という言葉が知られているように、視覚的にアプローチできるSNS。Instagramを通じて活動しているインフルエンサーは「インスタグラマー」と呼ばれる。
|
|
Twitter
|
テキストや画像、動画、リンクなどを添付でき、情報拡散性の高いSNS。
Twitterでフォロワーを集めているインフルエンサーは「アルファツイッタラー」と呼ばれる。
|
|
YouTube
|
自身のチャンネルを開設すると誰でも簡単に動画投稿が行える動画プラットフォーム。YouTubeで活動しているインフルエンサーは「YouTuber」と呼ばれる。
|
|
TikTok
|
短い尺の動画を中心に投稿・閲覧する動画プラットフォーム。中高生など若年層の間で人気を集めている。TikTokで活躍するインフルエンサーは「TikToker」と呼ばれる。
|
それぞれのSNSは利用しているユーザーの属性や、インフルエンサーの特徴も大きく異なります。
それぞれの特徴を踏まえて、自社がインフルエンサーマーケティングを実施する目的に合わせて適切なSNSを選びましょう。
「自社のサービスはどのSNSが合うの?」「今から参入すべきSNSは?」とお悩みの方は是非以下の資料をご参考ください。
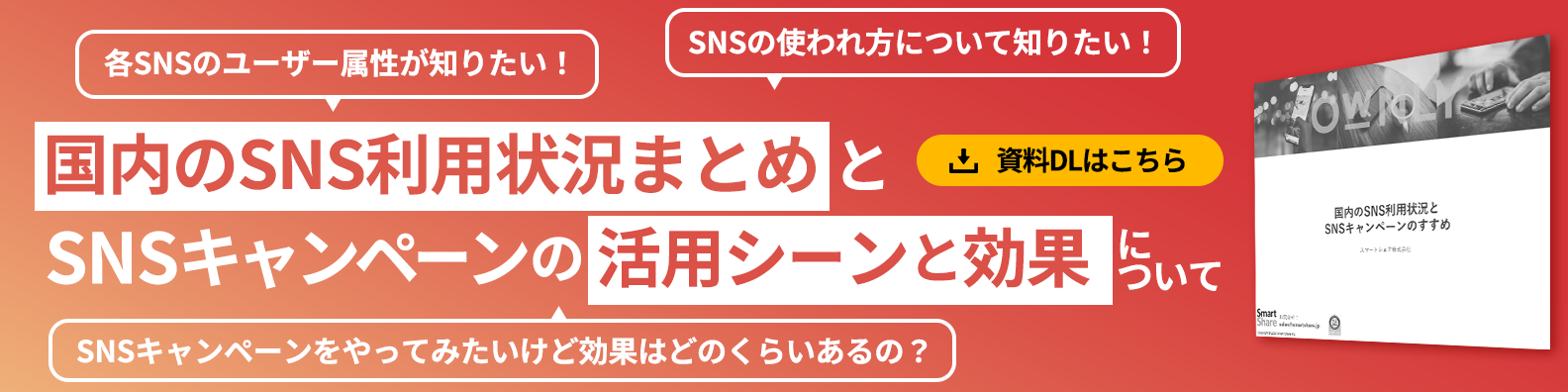
インフルエンサーマーケティングが広がった背景
ブログ、SNSなどの普及により、一般消費者の発信活動が盛んになったことが、インフルエンサー・マーケティングの広がりの背景です。
商品やサービスの感想がブログやSNSで発信されれば、企業側は自社商品やサービスがどのような感想を持たれているのかSNSを通じ簡単に探せるようになります。
このとき企業は、たくさんのフォロワーを持つSNS利用者つまりはインフルエンサーが、自社製品のイメージに大きな影響を与えていると知ります。
このインフルエンサーを積極的に企業側に取り込むことによって、自社製品やブランドのイメージアップを図ろうとしたのが、インフルエンサー・マーケティングの始まりです。
インフルエンサーの広告としての高い価値
現在SNS上での広告が増えているのは、拡散性が高いというSNSの特性に注目しているからです。一方、広告ブロック機能を使う消費者も増加し、スクロールで広告を飛ばしてしまう消費者もいます。
この点、インフルエンサーは消費者が見逃さない形で商品アピールできるため、SNSで自社の商品をバズらせたい企業にとって効果的です。
消費者の嗜好の変化・多様化
多様な情報にアクセスすることが可能になった現代日本社会では、消費者の時間の使い方・お金の使い方も多様化してきています。
このため、消費者の属性を、以前のように年齢や性別で単純に区分することはできなくなっているのです。
消費者の意思決定プロセスの変化・多様化
今は商品の情報が膨大に増えています。あまりにも情報があり過ぎて、消費者が自分で判断することが難しいこともあります。
消費者にとって、常に消費者目線の投稿を行っているインフルエンサーは身近な存在です。インフルエンサーを信頼し、インフルエンサーに判断を委ねることも珍しくありません。
このため、インフルエンサー・マーケティングの価値が高まっているのです。
なお、インフルエンサーマーケティングで口コミを投稿すると、口コミの2次拡散が期待できます。それによってSNSマーケティングで重要な「UGC」の創出につながります。
▼合わせて読みたい
インフルエンサーマーケティングのメリット7つ

インフルエンサーマーケティングには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
- 柔軟にマーケティングできる
- ターゲティングがしやすい
- 情報を信用してもらいやすい
- オンライン販売と相性が良い
- データ取得や効果分析がしやすい
- UGC創出のきっかけとなる
- SEO強化につながる
ここでは、それぞれのメリットについて解説します。
1. 柔軟にマーケティングできる
一口にインフルエンサーマーケティングと言っても、さまざまな形で施策を行える点がメリットです。たとえば、以下のような例があります。
- アンバサダー:ブランドの広告塔として長期的にブランドの魅力を発信してもらう
- ギフティング:インフルエンサーの自宅に製品を送って、感想をSNSに投稿する
- 現地訪問:インフルエンサーを店舗やイベント、観光地などに招いて現地レポート
- 商品監修・コラボ:製品・企画の監修やコラボアイテムの共同制作を行う
|
このようにマーケティングの目的やビジネスの形態に合わせて、柔軟に施策を実施できるため、さまざまな業種に合った施策を展開できるでしょう。
2. ターゲティングがしやすい
起用するインフルエンサーによっては、年代別・男女別・ジャンル別でターゲティングが行えるため、マーケティングを行う上で大きなメリットとなります。
ファッションや美容、旅行、グルメなど、ジャンルに特化したインフルエンサーを起用することで、そのジャンルへの興味関心が高いフォロワーにアプローチすることが可能です。
以下の資料ではUGCマーケティングで必須となるSNSの活用術を紹介しています。
もし、自社の施策に「自社のターゲットに効果的にアプローチするには?」「他のSNSとの相性は?」とお悩みの方は、以下の資料をご参照ください。

3. 情報を信用してもらいやすい
インフルエンサーは企業が発信する広告と異なり、実際に消費者目線で製品やサービスをレビューしてくれます。そのため、押しつけ感を低減して広告臭のない情報を発信できるようになります。
消費者としての発信は、信頼感や説得力が高く、ユーザーに対して興味関心や共感を獲得できるのが大きなメリットです。
またインフルエンサーによっては製品のフィードバックをしてくれる場合もあり、消費者目線での品質改善や新製品開発につなげられます。
4. オンライン販売と相性が良い
SNSに直接販売ページを貼ったり、SNSのショッピング機能を活用したりして、自社のオンラインショップに直接遷移できる点も魅力です。
インフルエンサーのPR投稿からユーザーをキャンペーンに遷移させることで、熱量や興味関心を下げないまま購入につなげやすくなります。
このように、インフルエンサーマーケティングはオンライン販売と相性が良く、大きく貢献してくれるでしょう。
5. データ取得や効果分析がしやすい
インフルエンサーマーケティングは、TwitterやInstagram、YouTubeなどのSNSや動画プラットフォームなど、インターネット上で実施されるのが一般的です。
そのため、リーチ数やエンゲージメント数、サイト遷移数、CV数などのデータを取得して、分析、効果検証を効率的に行えるメリットがあります。
分析した結果をもとに次の施策に活かせるため、PDCAサイクルを効率的に回せるマーケティング施策と言えるでしょう。
6. UGC創出のきっかけになる
昨今のマーケティング施策において、UGCを重視する企業が増加しています。UGCとは、ユーザー自身が発信するコンテンツのことで、商品の口コミや感想の投稿も該当します。
消費者は口コミ情報を多く求めており、口コミや感想の件数が多いほど信用度が高くなり、インフルエンサーマーケティングはUGC創出の大きなきっかけとなるのです。
インフルエンサーマーケティングは、「インフルエンサーに商品やサービスをPRしてもらって認知獲得すること」がゴールではありません。
「PR投稿の反響によってUGC創出が期待でき、そのUGCを今後のマーケティング施策に活かせる」ことがポイントとなります。
▼合わせて読みたい
7. SEO強化につながる
昨今は、Googleの検索結果にTwitterやInstagram、YouTuberなどのSNS投稿が表示されるケースが増えてきました。
インフルエンサーによるPR投稿に、商品販売ページや企業サイトのURLを記載することで、Google検索エンジンでの評価が高くなります。
とくにYouTubeのプロモーション動画は、Googleの検索結果に表示されやすく、結果的にSEO強化につなげられることがメリットです。
インフルエンサー・マーケティングのデメリット3つ

インフルエンサーマーケティングには、いくつかのデメリットがあります。実施する際は、以下の点に注意しましょう。
- インフルエンサーの選定が難しい
- ステルスマーケティングによる炎上リスクがある
- 高いリテラシーを維持する必要がある
ここでは、それぞれのデメリットや注意点について解説します。
1. インフルエンサーの選定が難しい
デメリットとして、インフルエンサーの選定が難しい点が挙げられます。フォロワー数が多ければよいわけではなく、企業やブランドとの親和性を重視する必要があります。
他にも、インフルエンサーの投稿の質、インフルエンサーとフォロワーの関係性、過去のPR投稿、フォロワー属性、インサイトデータなどもチェックすべき点は多くあります。
マーケティングの目的に沿ったインフルエンサーを起用しないと、成果が思うように得られない可能性があるため、依頼すべきインフルエンサーは慎重に見極めましょう。
さらに、見落としがちな点ですが、まだ他社に起用されていないインフルエンサーを探すことも大切なポイントです。
2. ステルスマーケティングによる炎上リスクがある
企業のPRであることを隠してPR投稿をすることはステルスマーケティングと呼ばれます。
消費者にステマだと認識されると、炎上や商品のイメージダウンにつながってしまいます。
企業が社会的信頼を失う重大な事態にもなりかねないので、インフルエンサーマーケティングの実施には、細心の注意が必要です。
3. 高いリテラシーを維持する必要がある
ステマをしていないとしても、モラルに欠けた投稿やPRをするとSNSで炎上する可能性があります。
SNSは一つの投稿によって炎上することもあり、ネガティブなニュースとして大きく取り上げられるリスクがあるのです。
PR投稿の際は、インフルエンサーの選定を慎重に行ったうえで、事前に投稿内容をチェックする体制を整えておきましょう。
インフルエンサーマーケティングでよく使われるSNS
インフルエンサーマーケティングでよく使われるSNSは、以下が挙げられます。
- Instagram
- X(Twitter)
- YouTube
- TikTok
ここでは、それぞれのSNSで発信するインフルエンサーの特徴について解説します。
Instagram
Instagramをメインに活躍するインフルエンサーは、インスタグラマーとも呼ばれます。
Instagramは写真や動画などビジュアルをメインにしたSNSなので、質の高い写真や動画、俗に言う「インスタ映え」する投稿をしている人が多い傾向です。
ファッションや美容、旅行、グルメなど、見た目の印象を重視するマーケティングに合っていると言えるでしょう。
X(Twitter)
X(Twitter)は、140文字のテキストや画像、動画などを投稿できるSNSです。Xには昔からインフルエンサーが多く、旧名称の「ツイッタラー」と呼ばれています。
Xの特徴は、投稿をリポストして拡散できる点です。
拡散力やリアルタイム性が高いので、SNS上で不特定多数のユーザーから注目を浴びる(バズる)という現象が起こりやすいSNSでもあります。
YouTube
動画投稿プラットフォームのYouTubeで動画コンテンツを発信しているインフルエンサーを「YouTuber」と呼びます。
動画は、短時間で多くの情報をユーザーに伝えられるので、商品やサービスの魅力を短時間で届けられるのがメリットです。
また、YouTuberの中には、Vtuberと呼ばれる種類もあり、さまざまなカテゴリーにおいて起用するケースも増えています。
TikTok
TikTokは、ショート動画を投稿・閲覧・シェアできるSNSです。TikTokで活躍するインフルエンサーは、「TikToker」とも呼ばれます。
TikTokは10~20代と若い世代を中心に人気があり、TikTokerが持つ影響力も若い世代が中心となっています。
また、X(Twitter)のように拡散力が高く、広告がタイムラインで自然に流れるので、バズりやすいSNSでもあります。
以下の資料では、日本国内で利用されているSNSの利用状況と具体的な活用シーンを効果別に解説しています。
「自社のサービスはどのSNSが合うの?」「今から参入すべきSNSは?」とお悩みの方は是非ご参考ください。
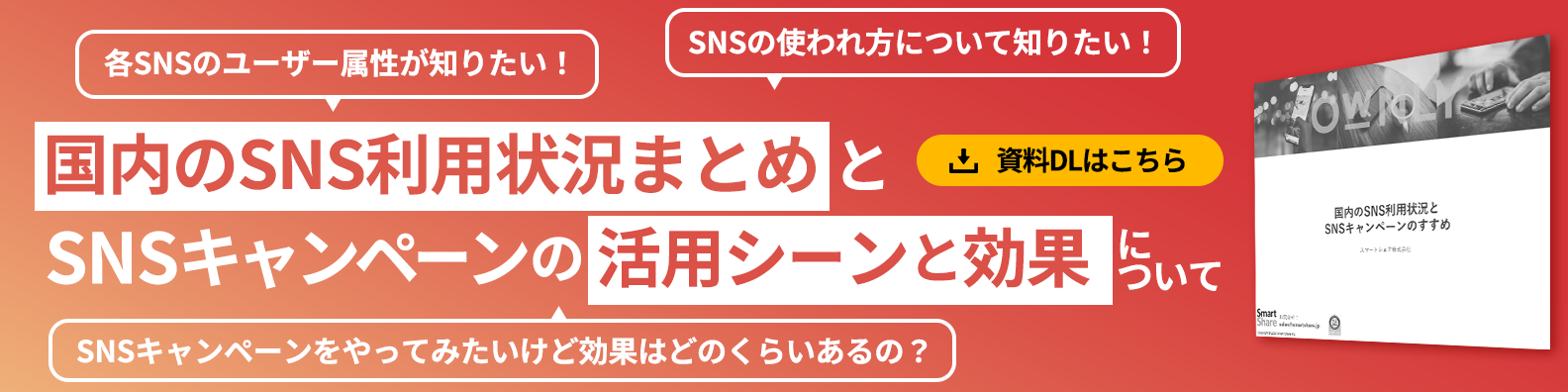
インフルエンサーマーケティングにかかる費用相場
インフルエンサーマーケティングにかかる費用は、インフルエンサーの知名度やフォロワー数、業界などによって大きく変動します。
一般的に、費用はフォロワー単価で決定するケースが多いです。フォロワー単価の相場は、1人あたり2円〜4円程度と言われています。
つまり、フォロワーが10万人いる場合は20〜80万円程度が相場となります。
なお、インフルエンサーのフォロワー数や、投稿の種類、内容、キャスティング方法などによっては、費用が大幅に増減するケースもあります。
事前に予算や費用対効果を確認しつつ、自社に合ったインフルエンサーを選定できるよう務めましょう。
インフルエンサーマーケティングのよくある失敗例
インフルエンサーマーケティングのよくある失敗例として、以下のようなものが挙げられます。
- 思うような成果が出なかった
- 同じような投稿が大量に出た
- 既存のファンから反感を買った
- 一時的な反応で終わってしまった
それぞれの失敗例について詳しく見ていきましょう。
思うような成果が出なかった
一般的な失敗例として、期待していたような成果が得られないことが挙げられます。
適切なインフルエンサーの選定やキャンペーンの設計だけでなく、ターゲット設定の失敗や競合他社など、外部要因によっても成果が出ないことも。
また、インフルエンサーの選定は悪くなかったものの、投稿内容を指定しすぎてインフルエンサーの魅力を低減してしまったというケースもあるでしょう。
SNSプラットフォームによってどのようなコンテンツが適切かは変わります。フォロワー数だけを見るのではなく、共創して伸びるコンテンツを作っていけるインフルエンサーを選びましょう。
同じような投稿が大量に出た
インフルエンサーマーケティングでは、インフルエンサーが自身の投稿スタイルや個性を活かしたコンテンツを提供することが重要です。
しかし、1つのキャンペーンや商品・サービスに対して、似たような投稿が大量に出てしまうことも珍しくありません。
これは、インフルエンサーが自身のフォロワーの反応を見て成功した投稿を模倣しすぎたり、投稿内容に関する制限を与えすぎることが原因です。
同じような投稿が増えると、広告の効果が薄れてしまったり、信頼性が低下したりする恐れがあるので注意しましょう。
既存のファンから反感を買った
インフルエンサーマーケティングでの失敗例として、インフルエンサーが広告を過剰に行ったり、信頼性を損なうような投稿を行ったりすることが挙げられます。
こうした投稿は、インフルエンサーの既存のファンから反感を買う可能性もあり、企業側にとってもインフルエンサー側にとっても痛手です。
■関連記事
SNSのステマとは?ステマ規制や炎上の具体例、対策法も解説
一時的な反応で終わってしまった
インフルエンサーマーケティングを実施して、投稿後すぐに良い反応が見られたものの、一時的な盛り上がりで終わってしまう失敗例もあります。
たとえば、プロモーション期間中に一時的な反応の伸びが得られたものの、その後フォロワーの関心が急速に低下し、持続的な成果が得られなかったというケースです。
長期的な戦略や関係性の構築が不十分であったり、プロモーションの企画設計やメッセージが一過性のものであったりすることが原因です。
企業によるインフルエンサーマーケティングの成功事例3選
ここからは、インフルエンサーマーケティングの成功事例を手法別に見ていきましょう。
1. 商品やサービスのギフティング
ギフティングは、インフルエンサーに無償で商品やサービスを提供し、実際に使用感や評価をPRしてもらう方法です。
インフルエンサーが実際に体験した感想を通じて、信憑性の高いリアルな情報をフォロワーに提供することが可能となります。
ギフティングには、報酬を支払う有償ギフティングと、報酬のない無償ギフティングの二つのタイプがあります。
無償ギフティングはコストを抑えられるメリットがありますが、有償ギフティングの方がPR依頼を受けてもらいやすいでしょう。
2. 企画・コンサルティング
商品やサービスをインフルエンサーと協力して制作し、共同企画やコラボレーションによって展開する戦略の一つです。
たとえば、美容やコスメ業界では、美容系のYouTuberなどに依頼して、共同でプロデュースアイテムを発売する事例も増加しています。
インフルエンサーのファン層を取り込むことで、ブランドの価値を向上させたり、新たな商品やサービスを展開したい企業にとって効果的です。
3. 現地訪問・レポート
店舗やイベント、観光地などを訪れ、その場で観光やサービスなどを実際に体験・レポートしてもらうマーケティング手法です。
インフルエンサーが自身の視点で体験した情報を発信することで、消費者に対して会場の雰囲気やサービスの内容をリアルに伝えることができます。
とくに飲食店など、インフルエンサーを店舗に招待して実際に食事を楽しんでもらい、レビューやPR投稿として投稿するケースも多く見られます。
インフルエンサーマーケティングのキャスティング方法

インフルエンサーマーケティングを行う際は、キャスティングを慎重に行う必要があります。
キャスティングする方法は主に以下の3つがあります。
- 自社で直接インフルエンサーをキャスティングする
- インフルエンサープラットフォーム・ツールを活用する
- インフルエンサーマーケティング会社に依頼する
ここでは、それぞれのキャスティング方法について解説します。
自社で直接インフルエンサーをキャスティングする
キャスティングしたいインフルエンサーが確定している場合は、SNSのDMなどで直接オファーの連絡をする方法もあります。
企業とインフルエンサーが直接やり取りすることで、中間マージンが発生せずコストを抑えられることがメリットです。また、スピード感のあるPRを行うことができます。
デメリットとして、PRのディレクションや商品の発送、炎上対策などを自社ですべて行わなければなりません。また個別の支払いや源泉徴収などの手続きを行う必要もあります。
インフルエンサープラットフォーム・ツールを活用する
インフルエンサープラットフォームを利用することで、インフルエンサーの選定やPRの依頼を行うことができます。
ツールによっては、SNS投稿をもとに自社にマッチした人物を選定したり、カテゴリー別にインフルエンサーを探せるメリットがあります。
ただし、インフルエンサーのマネジメントや商品発送を自社で行う必要があり、ツールの月額費用とキャスティング費用が別途かかる点に注意が必要です。
インフルエンサーマーケティング企業に依頼する
インフルエンサーのキャスティングを実施する企業に依頼することで、インフルエンサーの施策から最終的なレポートまでを一括でサポートしてもらえます。
キャスティングの利用料はかかるデメリットはありますが、専門的なノウハウや実績に見合った業務委託が可能です。
単にキャスティングやPRのみを行うのではなく、報酬の交渉や支払い、ディレクション、炎上対策、定量的な分析を一括代行してもらえます。
インフルエンサーマーケティングの知識や人的リソースがない場合は、企業に依頼するのがおすすめです。
▼合わせて読みたい
インフルエンサーマーケティングを起用するコツ
インフルエンサーマーケティングでキャスティングを行う際は、下記のコツを意識しましょう。
人気の高いインフルエンサーを起用する
インフルエンサーマーケティングのやり方には、人気の高いインスタグラマーやユーチューバーを利用する方法があります。
人気のインスタグラマーが写真を撮影しアップしたり、人気のユーチューバーが動画を撮影しアップしたりする際に、写真や動画の中で商品を使ってもらいます。
そうすると、動画や写真が拡散されるたびに、商品を使っているシーンが拡散され、周知につながるのです。
無作為に抽出したインフルエンサーを起用する
特定のインフルエンサーを利用するだけでなく、無作為に抽出したインフルエンサーを利用する方法もあります。
消費財のプロモーションで試供品を配るサンプリングを行い、実際に体験した人が商品を気に入って投稿し、拡散させる方法です。この場合は、大勢のインフルエンサーを使うことで効果が期待できます。
専門知識のあるインフルエンサーを起用する
このほかに、専門知識を持ったインフルエンサーを利用する方法もあります。業界で著名な人に体験してもらい、レポートなどで大多数の消費者に商品やサービスの感想を伝えてもらうことができます。
テレビタレントやモデル、スポーツ選手といった消費者の尊敬・憧れの対象をインフルエンサーとして利用することも有効な手段です。
消費者の憧れの人が商品を利用することで、消費者の商品への興味が高まり、自分も使用してみようと思うのです。
まとめ
SNSのインフルエンサーを上手く活用したSNSマーケティングは、非常に効果が高く、潜在顧客の獲得に繋げることができます。
インフルエンサー・マーケティングのやり方やリスクを理解し、どのようなインフルエンサーを利用すると効果的なのかしっかり検討していきましょう。
スマートシェアではインフルエンサー・マーケティングのサポートを行っています。インフルエンサーマーケティングにご興味を持たれましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
弊社が提供している「ハッシュタグSEO」はInstagramの検索結果の上位表示を実現させるサービスです。
Instagramのシステムにとって評価の高いインフルエンサーを把握し、PR投稿を依頼することによって、投稿の外部露出が増え、潜在顧客の獲得が期待できます。
もし興味のある方は、無料でダウンロードいただけるので、ぜひ以下のURLからご覧ください。

