- SS Lab
- X(旧Twitter)キャンペーンとは?メリットや事例、成功に導くポイントまとめ

X(旧Twitter)キャンペーンとは?メリットや事例、成功に導くポイントまとめ
X(旧Twitter)を利用する上で、タイムラインで企業のキャンペーン告知を目にしたことがある人は多いのではないでしょうか。近年、X(旧Twitter)キャンペーンを活用して、認知拡大・新規フォロワー獲得に取り組む企業が増えています。
当記事では、X(旧Twitter)キャンペーンを始めたい、興味があるという人に向けて、キャンペーンの種類やメリット、実施手順やポイントなどについて解説します。
実際に話題となった各企業のキャンペーン事例も紹介するので、X(旧Twitter)キャンペーンの実施を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
X(旧Twitter)キャンペーンとは
X(旧Twitter)キャンペーンとは、企業アカウントがX(旧Twitter)上で実施するキャンペーンです。
ユーザーを対象にフォローやリポストなどのユーザーアクションを促し、参加者は抽選などで景品を受け取れます。
Xキャンペーンを行う目的はさまざまです。
|
X(旧Twitter)キャンペーンは、アカウントさえあれば開催できるため、導入ハードルが低く予算を抑えて開催できるキャンペーン手法といえるでしょう。
■関連記事
【2024年】X(Twitter)キャンペーンの成功事例20選|種類・やり方・ツールも紹介
X(旧Twitter)キャンペーンで得られる効果
X(旧Twitter)を活用したキャンペーンは、投稿の拡散力を活かして認知度を高められるのが特長です。
X(旧Twitter)は国内アクティブユーザーが4,500万人を超えるとされており、若年層から中高年層まで幅広い年代に利用されています。
参考:X公式
参考:令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書|総務省情報通信政策研究所
とくに、フォロー&リポストを条件にした形式であれば、新たなフォロワーとの接点を生み出しやすく、継続的な情報発信にもつなげやすくなります。
また、キャンペーンをきっかけに商品やサービスに興味を持ったユーザーが、そのまま購入や来店に至るケースも少なくありません。
Xのリアルタイム性や話題性の高さをうまく活用できれば、広告に頼らず自然な形でユーザーの行動を促進できる点も大きなメリットです。
X(旧Twitter)キャンペーンの種類
X(旧Twitter)キャンペーンでよく活用される参加方法には、以下が挙げられます。
- フォロー&リポストキャンペーン
- 引用リポストキャンペーン
- リプライキャンペーン
- ハッシュタグキャンペーン
- いいねorリポストキャンペーン
- カンバセーショナルキャンペーン
- 診断コンテンツキャンペーン
- インスタントウィンキャンペーン(リプライ型)
- インスタントウィンキャンペーン(特設ページ型)
それぞれの参加方法について特徴やメリットを解説します。
フォロー&リポストキャンペーン
フォロー&リポストキャンペーンは、アカウントの「フォロー」と対象の投稿を「リポスト」して参加するキャンペーンです。
| メリット |
|
| デメリット |
|
ユーザー側は手軽に参加でき、開催側はキャンペーンを広く認知させられるメリットがあります。X(旧Twitter)の特性である「拡散性の高さ」を活かせるキャンペーンのひとつです。
引用リポストキャンペーン
対象ポストをリポストする際に、自分のコメントを添えて投稿してもらう形式のキャンペーンです。ユーザーのリアクションに個性が出やすく、投稿への関与度やブランド理解の深さが高まりやすいのが特長です。
| メリット |
|
| デメリット |
|
拡散と同時に、ファンや支持層のリアルな声を集めたいときや、話題化したいときに適しています。
リプライキャンペーン
対象ポストに対して、指定のハッシュタグやコメントをつけてリプライしてもらう形式のキャンペーンです。
ユーザーと企業アカウントとの双方向のやりとりが生まれやすく、エンゲージメントを高めたい場面で効果を発揮します。
| メリット |
|
| デメリット |
|
ファンとの距離を縮めたい場面や、リアルな声をヒントに商品改善・企画展開をしたいときに適しています。
ハッシュタグキャンペーン
ハッシュタグキャンペーンは、指定のハッシュタグをつけた投稿をすることで参加できるキャンペーンです。
ユーザーによる投稿を自然に増やせるため、UGCを創出しやすいメリットがあります。
| メリット |
|
| デメリット |
|
ただし、リポストキャンペーンに比べて参加のハードルが高いため、魅力的な景品を用意する必要があるでしょう。
いいねorリポストキャンペーン
アカウントをフォローしたうえで、対象ポストに「いいね」または「リポスト」のいずれかを選んでアクションしてもらう参加型のキャンペーンです。
どちらのアクションを選ぶかで、回答や投票の意思表示をしてもらうなど、参加型の企画に活用できます。
| メリット |
|
| デメリット |
|
選択肢の切り口が曖昧だと、参加率が伸びない可能性もあるため、ユーザーが思わず反応したくなる設計が重要です。
カンバセーショナルキャンペーン
カンバセーショナルキャンペーンは、画像や動画に最大4つの選択肢ボタンをつけて、選択肢を選んでポストすると参加できる形式のキャンペーンです。
| メリット |
|
| デメリット |
|
選択肢をタップするだけでユーザーは手間なくポストでき、ハッシュタグ付きの投稿(UGC)が増えるというメリットもあります。
■関連記事
カンバセーションボタンとは?メリットや使い方・キャンペーン事例も
インスタントウィンキャンペーン(リプライ型)
フォローやリポストなどの参加アクションを行ったユーザーに対して、企業アカウントから自動でリプライが届き、その場で当落結果がわかるキャンペーン形式です。
抽選結果が即時に通知されるため、ゲーム感覚で参加でき、盛り上がりやすいのが特長です。
| メリット |
|
| デメリット |
|
エンタメ性を重視したキャンペーンや、話題化・短期間の盛り上がりを狙いたいときに適しています。
インスタントウィンキャンペーン(特設ページ型)
対象ポストに記載されたURLやボタンから特設ページに遷移し、応募すると即時に当落結果が表示されるキャンペーン形式です。SNS上の投稿はあくまで誘導手段となり、ページ内でのブランド訴求や情報取得にも活用できます。
| メリット |
|
| デメリット |
|
Webとの連動施策や、ユーザー情報の取得・育成を重視するキャンペーンに適しています。
診断コンテンツ型キャンペーン
診断キャンペーンとは、SNSや特設サイト上で実施する診断コンテンツ形式のキャンペーンのことです。
診断コンテンツを通じて自社商品を訴求したり、診断結果のシェアによって多くの人にリーチを広げたりするというメリットがあります。
| メリット |
|
| デメリット |
|
■関連記事
Twitter診断キャンペーンとは?メリットや成功事例、実施の流れまで徹底解説
X(旧Twitter)キャンペーンのメリット3つ
X(旧Twitter)キャンペーンを実施するメリットは、主に以下の3つです。
|
それぞれのメリットについて解説します。
拡散性が高く話題になりやすい
Xキャンペーンの大きな特徴は、拡散性の高さです。
フォロー&リポストキャンペーンを実施することで、商品やサービスが話題になりやすいメリットがあります。
参加者のリポストを別のユーザーがリポストするといった二次拡散が期待でき、キャンペーン自体の認知度を高めることができるのです。
幅広い世代にリーチできる
日本国内におけるX(旧Twitter)の月間アクティブユーザー数は、4,500万人を超えています。(※2017年10月時点・公式発表)
10代から60代まで幅広い世代に利用されており、男女の偏りも見られません。
とくに20代と40代は利用率が高く、キャンペーン企画によっては今までリーチできなかった新しい層にもアプローチできるといえるでしょう。
短期間で成果を得られる
キャンペーンを実施することで、認知拡大や新規フォロワー獲得などの成果を短期間で得ることができます。
地道に投稿を続けるオーガニック投稿だけでは、ビジネスでの効果を感じにくいため、景品の用意や広告による発信などのペイド広告が重要です。
X(旧Twitter)キャンペーンの成功事例11選
ここでは、各企業が実施しているX(旧Twitter)キャンペーンの事例を紹介します。
1. キリンビール株式会社|「#クラフトビールの日」 SNS投稿キャンペーン

参照:「#クラフトビールの日」 SNS投稿キャンペーン by Tap Marché
キリンビール株式会社では、毎年4月23日の「クラフトビールの日」を盛り上げるため、SNS投稿キャンペーン「#クラフトビールの日 by Tap Marché」 を開催しています。
本キャンペーンでは、X(旧Twitter)またはInstagramにて、公式アカウントをフォローし、飲食店でクラフトビールを楽しんでいる写真をハッシュタグとメンションを添えて投稿することで応募が完了します。
この取り組みは、クラフトビールの記念日を活用し、SNS上での認知拡大とユーザー参加によるUGC(ユーザー生成コンテンツ)の獲得を狙ったものです。
特に、飲食店での写真投稿を条件とすることで、クラフトビールを実際に楽しむ場面をSNS上に広げ、飲用シーンの拡散と新規顧客の獲得を図っています。
SNSならではの拡散力を活かしつつ、クラフトビール文化の普及と飲食店との相互送客を目指す施策となっています。
2. #もっと知ってタイミー フォロー&RTキャンペーン
スキマバイトアプリ「タイミー」の公式Xアカウントでは、「もっと知ってタイミー」と称して、フォロー&リポストキャンペーンを実施しました。
キャンペーンは期間中1日1回参加可能で、その場で当選結果が分かるインスタントウィン形式で行われました。
/#もっと知ってタイミー
— タイミー (@Timee_official) June 9, 2023
Amazonギフト券
1万円分が当たる🎁
\
毎日参加可能✨
応募締切は6/23(金)
▼参加方法
1⃣@Timee_official をフォロー
2⃣この投稿をRT
3⃣👇URLより抽選に参加https://t.co/qZPwdBzcHH
▼タイミーのDLはこちらhttps://t.co/lPO0kjp6ZB#キャンペーン #プレゼント pic.twitter.com/bsSPGdruXY
参照:#もっと知ってタイミー フォロー&RTキャンペーン|OWNLY導入事例
キャンペーン投稿にはアプリのリンクも含まれており、ユーザーがアプリをスムーズにインストールできるように促進しているのもポイントです。
X(旧:Twitter)を通じてプレゼントキャンペーンを実施することで、サービスの認知拡大につながっている事例です。
3. 拡張4次職実装記念!オススメ職業 押せ推せキャンペーン
人気オンラインゲーム・ラグナロクオンラインでは、新職業「拡張4次職」が実装されたことを記念して、「オススメ職業押せ推せキャンペーン」を実施しました。
新職業ごとに2つの選択肢が用意されており、ユーザーは好きな職業を選択し、イラストまたはコスプレ/ぬいぐるみの画像を添付したポストで投票できます。
/#ラグナロクオンライン#拡張4次職実装 記念キャンペーン 🎉
— ポ三郎@ラグナロクオンライン公式ポリン (@RJC_Po) January 22, 2024
\
激レア✨ドラムのぬいぐるみや
究極精錬で使えるアイテムが当たる!
📢応募方法
①ボク( @RJC_Po )をフォロー
②キャンペーンページから「推しの拡張4次職」を選んで投稿!
▼キャンペーンページ▼https://t.co/Nuvrf8LHEC pic.twitter.com/VaPOiA0Par
参照:【ラグナロクオンライン】拡張4次職実装記念!オススメ職業 押せ推せキャンペーン|OWNLY導入事例
拡散力が高いX(Twitter)の投票キャンペーンを実施することで、現役ユーザーと休眠ユーザーに認知してもらいやすくなります。
また、ゲームキャラクターのぬいぐるみやゲーム内アイテムを賞品にすることで、ユーザーの顧客体験を向上させ、良質なファンを育成する効果が期待できるでしょう。
3. あなたはどのタイプ?#ピュアポテト診断キャンペーン
株式会社湖池屋の公式Xでは、「ピュアポテト ブランド芋くらべ」シリーズの新発売を記念して、X(旧Twitter)上で完結する診断キャンペーンを実施しました。
対象ツイートから診断に参加し、質問に答えて表示された結果をシェアすると、抽選で20名にピュアポテトの詰め合わせが当たるという内容です。
/
— 湖池屋 コイケヤ【公式】 (@koikeya_cp) November 13, 2023
あなたはどのタイプ?#ピュアポテト診断 キャンペーン
\
20名様にピュアポテト詰め合わせ🎁
質問に答えるとあなたにオススメのピュアポテトをご紹介🥔
【応募方法】11/19〆
1️⃣@koikeya_cpをフォロー
2️⃣下の画像をタップし診断に参加
3️⃣結果をシェア
🔽診断はこちらから🔽
参照:あなたはどのタイプ?#ピュアポテト診断キャンペーン|OWNLY導入事例
質問に答えると自分のおすすめのピュアポテトが表示されるため、商品の認知度向上や理解促進、販売促進などにつながっています。
数種類のピュアポテトの魅力を発信しつつ、ユーザー投稿を促すことで、ブランドに関する投稿(UGC)を効果的に増加させた事例です。
■関連記事
診断キャンペーンとは?メリット・デメリットや成功事例、実施する流れも解説
4. The 素材のご馳走 新発売記念キャンペーン
株式会社湖池屋の新商品「The素材のご馳走」の発売日に合わせて、X(Twitter)とInstagramの両SNSで投稿キャンペーンを実施しました。
公式アカウントをフォローのうえ、指定のハッシュタグと@メンションをつけて「あなたのプチ贅沢」を投稿すると参加できる投稿キャンペーンです。
\5万円分の旅行券も当たる/
— 湖池屋 コイケヤ【公式】 (@koikeya_cp) July 10, 2023
The素材のご馳走でリッチに
羽をのばそうキャンペーン🧳🌟
1️⃣@koikeya_cp をフォロー
2️⃣ #The素材のご馳走 と #プチ贅沢 +@koikeya_cp をつけてあなたの『プチ贅沢』を投稿✨→8/15〆
規約→https://t.co/35W8KRb0Qc
応募する🔽
参照:The 素材のご馳走 新発売記念キャンペーン|OWNLY導入事例
また、「湖池屋プレミアム”フライ”デー」として、応募期間中の金曜日18:00~24:00の間に投稿することで当選確率が1.5倍になる仕掛けも用意されました。
限定した時間帯に投稿してもらうことによって、X(Twitter)上でのトレンド入りを狙っていることも本事例のポイントです。
5. キットカット50周年記念コラボキャンペーン
ネスレ「キットカット」公式Xアカウントでは、キットカット×サーティーワン50周年コラボ記念キャンペーンを実施しました。
キットカットとサーティーワンの両アカウントをフォローのうえ、投稿をRTするとその場で100名にオリジナルグッズが当たるインスタントウィン形式です。
🍨🍫 Campaign NEWS 🍫🍨#キットカット × #サーティワン
— キットカット (@KITKATJapan) June 5, 2023
50周年コラボ記念キャンペーン🍫
"キットカット"×サーティワン50周年オリジナルスマホケースが100名様に当たる✨
①@KITKATJapanと@BR31_Icecreamをフォロー
②この投稿をRT
③その場で結果がわかる!
応募期限:6月30日 pic.twitter.com/bdJUDhzgVw
参照:キットカット50周年記念コラボキャンペーン|OWNLY導入事例
複数の企業同士でのSNSキャンペーンは、相互誘客が見込めるため、自社のターゲット層以外にもリーチできるというメリットがあります。
本キャンペーンの期間では、サーティーワンとキットカットのコラボ商品が発売されており、店舗で使えるクーポン付きの限定商品や、SNS上でキャンペーンを実施するなど多方面で盛り上がりを見せています。
6. 釜寅20周年記念「#推し釜飯 を選んで当たる!プレゼントキャンペーン」
宅配御膳「釜寅」では、創業20周年記念企画として、Xの投票キャンペーン「#推し釜飯 を選んで当たる!プレゼントキャンペーン」を開催しました。
人気の組み合わせ6品から好きな釜飯に投票すると、参加者の中から抽選で30名に釜寅オリジナルタオルがプレゼントされるというものです。
/
— 宅配御膳 釜寅 (@kamatora_jp) June 10, 2024
釜寅20周年記念!#推し釜飯 を選んで当たる!プレゼントキャンペーン🎉
\
具材がハーフ&ハーフで楽しめる「選べる釜飯」の人気の組み合わせ6品から好きな釜飯に投票!
抽選で30名様にトラかまさんタオルが当たる🎁
🍚応募方法
①@kamatora_jp をフォロー
②好きな釜飯の画像をタップしてポスト
参照:釜寅20周年記念「#推し釜飯 を選んで当たる!プレゼントキャンペーン」
ユーザー自ら選んでポストする参加型のキャンペーンにすることで、拡散効果だけでなく、商品の認知度や理解度の向上が期待できます。
OWNLYの投票機能を転用することで、好きな画像をタップするだけでポストできるというストレスの無い挙動を実現でき、ユーザーの体験価値の引き上げにつながっています。
7. ビアードパパ25周年企画「シュークリーム復活ファン投票」

参照:ビアードパパ25周年企画第三弾「シュークリーム復活ファン投票」
シュークリーム専門店「ビアードパパ」では、25周年を記念してお客様参加型キャンペーン「シュークリーム復活ファン投票」を開催しました。
2022年までに販売された期間限定シュークリームの中から、社内選抜された8商品を対象に、お客様が「もう一度食べたい」商品に投票してもらうというものです。

投票結果で1位になった商品は、2025年1月に復活販売を予定しており、参加者の中から抽選で25名にオリジナルグッズなどの賞品がプレゼントされます。
本投票を盛り上げるために、3日限定で全員が当たるスピードくじも同時開催され、店舗で利用できるクーポン券が配布されました。
キャンペーンを通して、既存ファンに改めて商品について考えてもらうきっかけを与えることで、想起性が高まりファンのロイヤリティ向上につながっています。
8. 僕ヤバ愛を語ろう!バレンタイン感想投稿キャンペーン
TVアニメ「僕の心のヤバいやつ」公式Xアカウントでは、「#僕ヤバ愛を語ろう」バレンタイン感想投稿キャンペーンを実施しました。
アニメの好きな場面写真を選び、アニメの感想をハッシュタグ付きで投稿すると、抽選で3名にグッズの詰め合わせがプレゼントされるという内容です。
✶˚‧ ⊹ 💟#僕ヤバ愛を語ろう💟⊹ ‧˚✶
— 「僕の心のヤバイやつ」TVアニメ公式@劇場版制作決定!! (@bokuyaba_anime) February 11, 2024
バレンタイン感想投稿キャンペーン#僕ヤバ の好きな場面写真を選び、
あなたの僕ヤバ愛を聞かせてください♪
参加者には抽選でプレゼントも🎁
ぜひご参加ください!!!!✨
参加▶https://t.co/wroA2Qitrp
📅2/17㈯まで pic.twitter.com/BU99813PGX
参照:僕ヤバ愛を語ろう!バレンタイン感想投稿キャンペーン|ONWLY導入事例
バレンタインの時期に合わせて、ファンに「作品の愛」について呟いてもらうことで、良質なUGCを生み出し、作品の認知度向上・拡散を促進しています。
また、キャンペーンを通じてファンとコミュニケーションを取ることで関係性構築につながり、ファンのロイヤリティが向上するのもメリットです。
9. ホテル椿山荘東京「#記念日なんだし椿山荘」
ホテル椿山荘東京の公式X(旧Twitter)では、「記念日を過ごすならあなたはどっち?キャンペーン」と称した投票キャンペーンを実施しました。
アカウントをフォローの上、記念日にしたい過ごし方の画像をタップしてリポストすると投票が完了するというもの。投票数が多かった方に投票した人の中から、5組10名にディナー券がプレゼントされます。
憧れの場所でお泊まり or 贅沢にお食事
— ホテル椿山荘東京 (@Hotel_Chinzanso) November 17, 2023
記念日を過ごすならあなたはどっち?キャンペーン✨
投票数が多かった方に投票した方の中から5組10名様へディナー券をプレゼント🎁
応募☁
1 @Hotel_Chinzanso をフォロー
2 記念日にしたい過ごし方の画像をタップ
3 RTして投票完了#記念日なんだし椿山荘
事前に用意した「憧れの場所でお泊まり」「贅沢にお食事」のいずれかに投票してもらうことで、ユーザーに実際に体験したシーンをイメージしてもらいやすくなります。
ホテル椿山荘東京の認知度向上や集客、SNSのファン獲得・育成につながっていると言えるでしょう。
10. Jackeryブラックフライデー開催記念キャンペーン
Jackery Japanの公式X(旧Twitter)アカウントでは、「#Jackeryブラックフライデー」として、毎日その場で当たるインスタントウィンキャンペーンを実施しました。
フォロー&リポストで参加でき、抽選で同社の新製品を2名、QuoカードPayを計52名にプレゼントするという内容です。
#Jackeryブラックフライデー がやってくる〜👀⭐
— Jackery Japan【公式】 (@jackeryjapan) November 17, 2023
🛍12/1まで開催!アマゾンお買い得情報はこちらから
▷https://t.co/HDgh5aVfp3
フォロー&RTで毎日その場で当たる!
新製品 #Jackery100Plus やQuoカードPayなど計52名にプレゼント🎁
①@jackeryjapan をフォロー
②本投稿をRT
③結果がすぐわかる
参照:Jackeryブラックフライデー開催記念キャンペーン|OWNLY導入事例
自社商品をプレゼントにすることで、商品やブランドの認知拡大、販売促進が見込めます。
同時に、幅広いターゲット層に喜ばれるギフトカードを景品にすれば、より多くのユーザーからの参加が期待できるという点もメリットです。
X(旧Twitter)キャンペーンを実施する手順

ここからは、X(旧Twitter)キャンペーンの具体的な実施手順について解説します。
1. キャンペーンの目的・ターゲットを決める
X(旧Twitter)キャンペーンの内容を検討する前に、実施する目的やターゲットを定めましょう。ここであらかじめKPIを設定しておく必要があります。
目的に応じて、目標にすべき指標(KPI)は異なります。
| 目的 | 目標にする指標 |
| 新商品・サービスの認知拡大
|
リポスト数などのインプレッション数
|
| 商品の販売促進・来店促進
|
キャンペーンをきっかけとする来店数
|
| 話題作り・UGC獲得
|
ユーザー投稿数
|
目的が決まったら、「誰に届けたいか」というターゲットを決定します。
できる限り細かなペルソナを設定して、キャンペーンの種類やクリエイティブの方向性を定めましょう。
2. キャンペーンの詳細を検討する
ターゲットや目的に合わせて、キャンペーンの詳細を検討します。
検討すべき主な内容は以下のとおりです。
|
上記以外にも、キャンペーン用に専用のWebページを作る場合は、その手配も必要になるでしょう。
当選者の集計・抽選方法を抜け漏れなく行い、開催側の負担を軽減するためには、キャンペーン用のツールを活用するのがおすすめです。
■関連記事
【2024年最新】Twitterキャンペーンツール10選|メリットや選ぶポイントとは?
3. キャンペーンを実施する
キャンペーンの詳細が決まったら、キャンペーンを実施しましょう。
キャンペーン期間中も、応募状況や指標の数値を定期的に確認し、必要に応じて配信頻度やクリエイティブを調整します。
自社アカウントから発信するだけではフォロワー外にリーチしにくいため、X(旧Twitter)広告を併用するのもよいでしょう。
問い合わせに対応できるよう、ダイレクトメッセージの受信設定もしくはキャンペーン用のWebページにフォームを作成しておくのがおすすめです。
4. キャンペーンの効果検証を実施する
キャンペーン終了後、初めに定めた目的・数値を達成できたか効果検証を行いましょう。
キャンペーン専用ツールを活用することで、インプレッションやユーザー投稿数などKPIとなる指標を簡単に計測できます。
新たに獲得した新規フォロワーが自社のターゲットであるかをチェックしましょう。単なる懸賞目的でターゲットとかけ離れている場合、フォロワーの離脱率が高くなる傾向にあります。
フォロワーの離脱率が高い=ターゲットと乖離していたと考えられるため、次回以降のキャンペーン施策にも活かせるでしょう。
キャンペーン単体を振り返って終わりではなく、今後のアカウント運用に活かせるよう分析することが重要です。
5. 自社の発信内容を振り替える
X(旧Twitter)キャンペーンを効果的に行うには、投稿内容だけでなく、自社全体の発信方針を振り返ることが重要です。
Xの投稿は即時性が高く拡散されやすい一方で、アカウント単体で成果を上げるには限界があります。
そこで、オウンドメディアや公式サイト、ブログなど他チャネルとの連携を見直しましょう。
たとえば、キャンペーン投稿から自社サイトの記事へ誘導し、SEOでの流入につなげることで、中長期的な集客効果が期待できます。
また、Xで反応が良かったテーマをもとに記事コンテンツを拡充すれば、検索エンジンでも評価されやすくなります。
Xの反応データを分析し、発信のトーンやテーマを統一することで、ブランドの一貫性が生まれ、信頼性や認知度の向上にもつながるでしょう。
■関連記事
中小企業がSEO対策するメリットは?意識すべきポイントや注意点も解説
以下の資料では、Twitter上でキャンペーン施策を行う際の設計手順・注意事項を中心に、キャンペーンから自社サービスへの遷移率を高める方法を解説しています。
SNS運用担当者様や広告代理店様は、ぜひ資料をご参考ください。
X(旧Twitter)キャンペーンを実施するポイント5つ
X(旧Twitter)キャンペーンを実施する際のポイントは以下のとおりです。
- 参加までの負担を下げる
- クリエイティブにこだわる
- 目的やターゲットに合った景品を用意する
- キャンペーン用ツールを活用する
- 送料や在庫管理のコストも考慮する
- 普段からXアカウントを運用する
それぞれのポイントについて解説します。
1. 参加までの負担を下げる
キャンペーンを成功させるには、参加までの負担を下げることが大切です。
条件が複雑すぎると離脱されやすくなるデメリットもありますが、目的に応じて条件をあえて絞ることで、参加者の質を高められる場合もあります。
たとえば、複数ブランドのコラボで複数アカウントフォローを求める場合や、投稿内容にテーマを設けてUGCを狙う場合などです。
大切なのは、ターゲット層にとって負担がないかどうかを基準に設計することです。
基本はフォロー&リポストのようなシンプルな参加方法が参加率を高めますが、狙いたい成果に応じて調整することも検討しましょう。
2. クリエイティブにこだわる
X(旧Twitter)キャンペーンでは、投稿の内容だけでなく、目を引くクリエイティブも成果を左右します。
タイムライン上では多くの情報が流れており、ユーザーの関心を引くには、数秒で印象に残るデザインやコピーが欠かせません。
ブランドカラーやフォントを統一し、世界観を明確にすることで信頼感が生まれます。
また、静止画よりも動画やアニメーションのほうが反応率が高い傾向にあるため、目的に応じて形式を使い分けることも効果的です。
3. 目的やターゲットに合った景品を用意する
景品選びはキャンペーンの参加率を大きく左右するため、ターゲット層や目的に合った景品を用意することが重要です。
たとえば、購買促進や見込み客獲得が目的であれば、自社商品や体験クーポンなどが適しています。
このように、ターゲット層とキャンペーン目的の両面から景品を選ぶことで、期待する成果に近づけます。
発送や管理の手間を抑えたい場合は、デジタルギフトの活用もおすすめです。特にインスタントウィン型のキャンペーンとは相性が良く、運用における負担の軽減にもつながるでしょう。
4. キャンペーン用ツールを活用する
自力でキャンペーンの参加ユーザーを収集・抽選するのは非常に手間がかかります。
効率的にキャンペーンを実施し、効果測定を行う場合は、X(旧Twitter)キャンペーン用ツールの活用がおすすめです。
一般的には応募データの収集・管理・抽選・レポート機能などの機能が備わっています。ツールによって、細かな機能はさまざまです。
自社で実施したいキャンペーンの目的に応じて、最適なツールを選定しましょう。
5. 送料や在庫管理のコストも考慮する
X(旧Twitter)キャンペーンで実物の景品を用意する際は、送料や在庫管理にかかるコストも考慮しておきましょう。
実物の景品、かつキャンペーンの当選人数が多い場合は、送料がかかりすぎてしまう可能性が考えられます。
また、発送作業や在庫管理などの工数も必要になることを踏まえて、費用対効果を検討することが重要です。
6. 普段からXアカウントを運用する
X(旧Twitter)キャンペーンの効果を最大化するには、キャンペーン期間だけでなく、日常的なアカウント運用が重要です。
普段から投稿が少ないアカウントは信頼性が低く見られ、キャンペーンの盛り上がりも一時的で終わりがちです。
日頃から商品・サービスの魅力を伝える投稿や、ユーザーに役立つ情報を発信しておくことで、キャンペーン経由で訪れた人がフォローしやすくなります。
また、ユーザーとの返信やリポストなどを通じて、コミュニケーションを積み重ねることも大切です。こうした継続的な運用が、ブランドの信頼や親近感を育て、キャンペーン後のフォロワー維持にもつながります。
X(旧Twitter)キャンペーンを実施する際の注意点
X(旧Twitter)キャンペーンを実施するうえで、いくつか注意する点があります。
- X(旧Twitter)のガイドラインを遵守する
- 複数アカウントでの応募は禁止する
- 複数回同じ内容をポストさせない
- 法令・景品表示法への配慮を忘れない
- 炎上リスクを回避する工夫をおこなう
ここでは、それぞれ順に解説します。
X(旧Twitter)のガイドラインを遵守する
X(旧Twitter)キャンペーンを実施する際は、プラットフォームのガイドラインを遵守することが必須です。
ガイドラインには以下のような内容が記されています。
|
参照:キャンペーンの実施についてのガイドライン|Xヘルプセンター
これらに違反すると、アカウントの凍結や投稿制限などのリスクがあります。
事前にXヘルプセンターのガイドラインやルール、適用法令をしっかり確認し、安心して実施できるキャンペーン設計を行いましょう。
プラットフォームごとの最新ルールは随時更新されるため、実施前に再確認することも忘れないことが大切です。
複数アカウントでの応募は禁止する
X(旧Twitter)キャンペーンでは、複数アカウントでの応募は禁止されています。
これは、Xが定める「プラットフォーム操作およびスパム行為に関するポリシー」に基づくルールです。
同一人物が複数のアカウントを使って応募・投稿・リポストを行う行為は、不正操作とみなされる可能性があります。
こうした行為はキャンペーンの公平性を損なうだけでなく、該当アカウントの凍結や応募無効の対象になるリスクもあります。
運営側としては、応募規約に「おひとりにつき1アカウントまで」などの文言を明記し、重複応募が発覚した場合は対象外とする旨を示すことが重要です。
また、同一IPや端末からの応募を自動検知できるツールを導入することで、不正防止の精度を高められます。
複数回同じ内容をポストさせない
X(旧Twitter)キャンペーンでは、ユーザーに同じ内容を何度もポストさせる行為も禁止されています。
違反すると、アカウントが一時的に制限されたり、最悪の場合は凍結されるリスクがあります。
キャンペーン設計の際は、「この投稿を何度もリポストして応募」などの条件を設定しないよう注意が必要です。
代わりに、ハッシュタグ付きの投稿や引用リポスト、コメント付き投稿など、ユーザーごとに異なる内容を促す形式が安全です。
投稿内容の重複を避けることで、ガイドラインに準拠しつつ、自然な拡散やブランド認知の向上にもつながります。
法令・景品表示法への配慮を忘れない
キャンペーンを実施する際は、景品表示法や個人情報保護法などの関連法令も遵守しなければなりません。
たとえば、景品表示法では景品の上限金額が定められています。一般懸賞では取引額に関係なく10万円まで、購入や契約を伴う懸賞では取引額の20倍まで(上限10万円)といったルールがあります。
これらを超えると違法となるため、景品金額や配布条件を事前にチェックすることが重要です。
また、ユーザーから個人情報を取得する場合は、利用目的の明示や適切な管理体制も必要になります。これらを怠ると、炎上や法的リスクにつながるため、社内の法務部門や専門家と連携し、安心して運用できる体制を整えておきましょう。
炎上リスクを回避する工夫をおこなう
SNSキャンペーンは拡散力が高い一方で、ユーザーが不信感を抱くポイントには注意が必要です。たとえば、抽選が不透明だったり当選発表が遅れたりすると、不満が広がりやすくなります。
そのため、キャンペーン実施時には応募条件・抽選方法・当選発表スケジュールを明確に伝えることが大切です。
また、ユーザー投稿を促す場合は、不適切な内容や過度な競争心をあおる企画にならないよう配慮しましょう。万が一トラブルが発生した際には、迅速かつ誠実な対応が求められます。
事前にリスクを想定し、対応フローや問い合わせ窓口を準備しておくことで、信頼を失わずに対応できるでしょう。
X(Twitter)で実施されているキャンペーンを調べる方法3つ
X(旧Twitter)では、企業やブランドが多様なキャンペーンを実施しているため、企画の際は他社の取り組みを調べて傾向をつかむことが重要です。
ここでは、X上で実際に行われているキャンペーンを調べる3つの方法を紹介します。
- Xの検索欄からリサーチする
- キャンペーン情報のサイトをチェックする
- 他社のキャンペーン事例を確認する
Xの検索欄からリサーチする
最も手軽にX(旧Twitter)キャンペーンを調べる方法は、Xの検索欄を活用することです。
検索バーに「#キャンペーン」「#プレゼント企画」「フォロー&リポスト」などのキーワードを入力すると、現在実施中の投稿を一覧で確認できます。
さらに「最新」タブに切り替えれば、リアルタイムで投稿された最新のキャンペーン情報を把握できます。
企業名や商品名を掛け合わせて検索すれば、業界や競合の動向も追いやすくなるでしょう。
キャンペーン情報のサイトをチェックする
キャンペーン情報をまとめて紹介している専門サイトを活用するのも効果的です。
企業公式のX(旧Twitter)キャンペーンや懸賞企画を一覧で確認でき、開催期間・応募条件・景品内容なども整理されています。
特に、どのジャンルのキャンペーンが反響を集めているか、どの投稿形式が多いかを把握することで、自社企画のヒントが得られます。
気になるキャンペーンはブックマークしておき、傾向分析や次回施策の参考に活用しましょう。
他社のキャンペーン事例を確認する
同業種や似たターゲット層を持つ企業のX(旧Twitter)キャンペーンを分析すると、効果的な投稿内容や参加条件、景品設定の傾向が見えてきます。
フォロー&リポスト型・引用ポスト型など形式別に成果を比較すれば、自社に最適な手法も見つけやすくなります。
また、キャンペーンを継続的に行っている企業の運用方針を追うことで、フォロワー獲得からエンゲージメント強化までの流れを体系的に学ぶことが可能です。
より具体的な成功要因を知りたい方は、「フォロー&リツイートキャンペーン成功事例から見る運用のポイント」をチェックしてみてください。
実際の事例をもとに、成果を上げるための戦略や設計のコツを詳しく解説しています。資料を無料でダウンロードして、自社のマーケティング施策に役立てましょう。
X(旧Twitter)キャンペーンに関するよくある質問
ここからは、X(旧Twitter)キャンペーンを実施する際によくある疑問について回答します。
フォローされているかを確認するには?
X(旧Twitter)キャンペーンで「フォロー&リポスト」を条件にする場合、応募者が実際にフォローしているかの確認が必要です。
しかし、大規模なキャンペーンや応募数が多い場合は手動では対応しきれないでしょう。そのため、多くの企業では抽選ツールやキャンペーン管理ツールを利用しています。
これらのツールでは、フォロー状態を自動でチェックできるほか、リポスト履歴や応募日時の記録も一括で管理できます。
■関連記事
【2025年最新】X(Twitter)キャンペーンツール15選|メリットや選ぶポイントも解説
キャンペーンの応募者リストの作成方法は?
応募者リストは、抽選や当選連絡をスムーズに行うための重要なデータです。
もっとも一般的な方法は、専用のキャンペーンツールを使って自動で応募者情報を収集する方法です。
ツールを利用すれば、フォロー・リポストの有無、ユーザーID、応募日時などを自動で一覧化できます。
小規模なキャンペーンの場合は、Xの検索機能で指定のハッシュタグやリポストを抽出し、スプレッドシートに手動で整理することも可能です。
ただし、手動管理では抜け漏れやミスが起こりやすいため、効率性と正確性を重視するならツール活用が望ましいでしょう。
リポストキャンペーンで鍵垢にどう対応する?
X(旧Twitter)のリポストキャンペーンでは、鍵付きアカウント(非公開アカウント)は注意が必要です。
鍵垢の投稿は外部から確認できないため、リポストを条件にしていても企業側で応募を確認できません。そのため、多くのキャンペーンでは「公開アカウントでの参加のみ有効」と明記するのが一般的です。
応募条件にこの注意書きを入れておくことで、応募者とのトラブルを防ぎ、公平な抽選を行えます。
キャンペーンの規約で記載すべきことは?
X(旧Twitter)キャンペーンでは、応募規約を明確に記載しておくことで、トラブルやクレームを防げます。主な記載項目は以下の通りです。
- キャンペーンの概要
- 応募期間・応募方法
- 当選者の選定方法・発表時期
- 景品内容および発送方法
- 応募資格(日本国内限定など)
- 個人情報の取り扱いについて
- 注意事項(鍵垢・なりすまし・不正応募への対応など)
- 免責事項および問い合わせ先
これらを明記しておくことで、ユーザーが安心して参加でき、企業側も法的リスクを回避できます。
X(旧Twitter)キャンペーンのまとめ
X(旧Twitter)キャンペーンを活用することで、新規フォロワー獲得・認知拡大・売上増加・ブランディングなどさまざまな効果を得られます。
キャンペーンの種類や手法によっても期待できる効果は変わるため、最適な手法を選び効果的なキャンペーンを実施しましょう。
X(旧Twitter)キャンペーン用ツールを活用するなら、「OWNLY」をご利用ください。OWNLYでは、Xキャンペーンを含め、15種類以上のキャンペーンを無制限で利用いただけます。
また自社のノウハウを活かし、施策の企画から、予算と目標に応じた広告運用の最適化を支援します。当選者の連絡や商品送付などの事務局業務も代行可能です。
サービスや料金プランなど、ぜひお気軽にお問い合わせください。
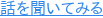
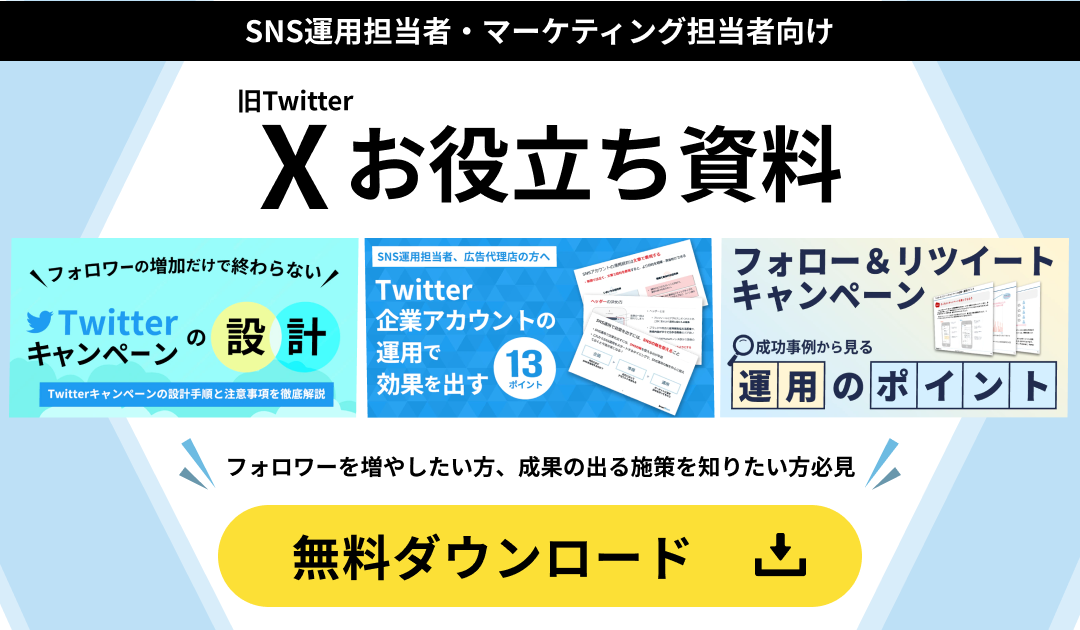

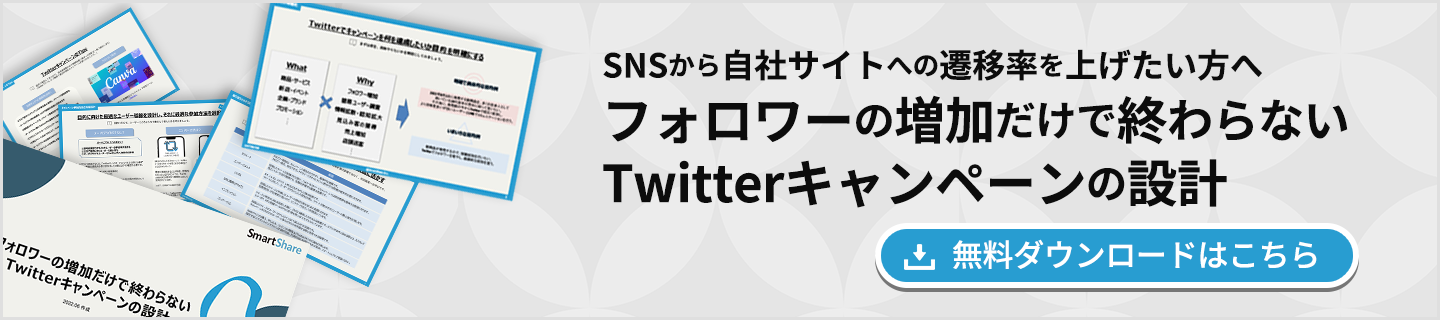

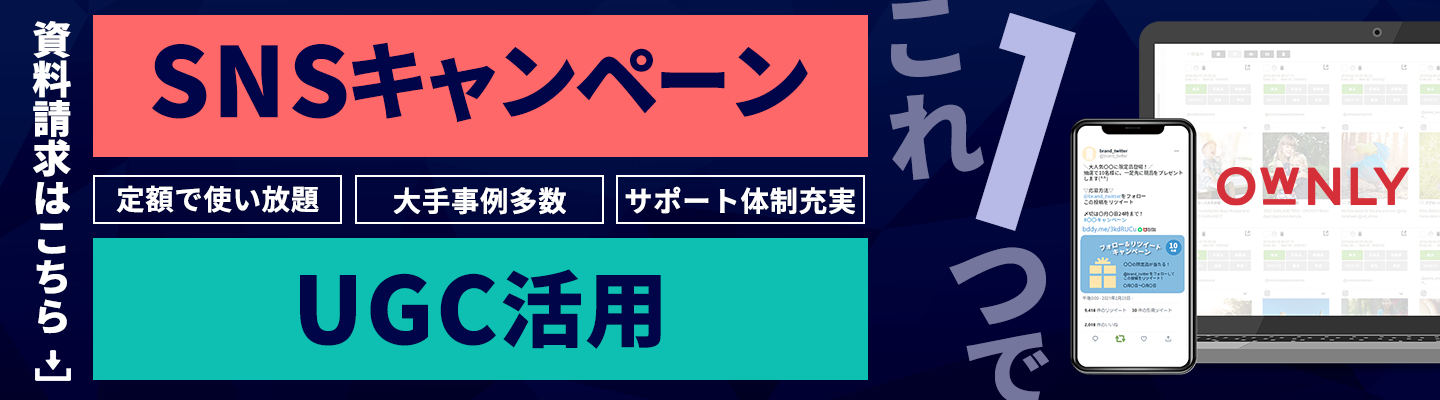












.png?width=260&height=139&name=large%20(8).png)


.png?width=260&height=139&name=large%20(11).png)
.png?width=260&height=139&name=large%20(16).png)


