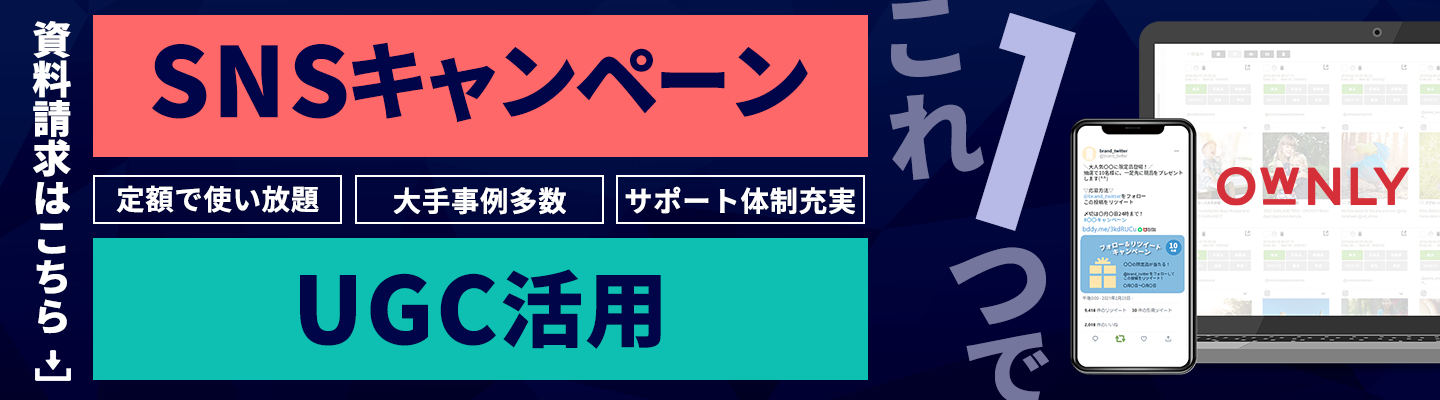SNSやサイトで診断コンテンツを見かけた際に、つい参加したくなったという経験は誰もがあるのではないでしょうか。
診断キャンペーンは、SNS上で診断コンテンツを提供したうえで、診断結果をシェアして応募することでプレゼントが当たるというものです。
この記事では、診断キャンペーンの種類やメリット・デメリット、実際のやり方についても解説します。成功事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
診断キャンペーンとは
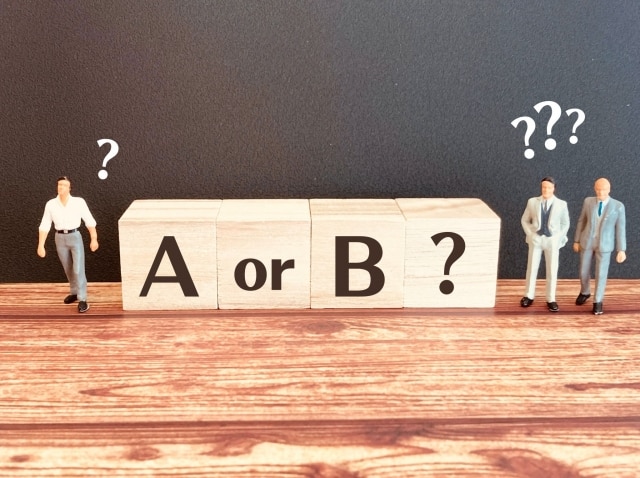
診断キャンペーンとは、SNSや特設サイト上で実施する診断コンテンツ形式のキャンペーンのことです。
Twitterの場合は、ユーザーが企業の公式アカウントをフォローの上、診断結果をTwitter上でシェアすることを応募条件としているものが多くあります。
またTwitter上でのシェアを条件としていなくても、面白いコンテンツであればユーザーが自ら結果をシェアしようとするでしょう。
診断結果として商品やサービスを訴求したり、診断結果がシェアされたりすることで、サービスの認知拡大やブランディングを図れます。
診断キャンペーンの種類
診断キャンペーンの種類はおもに下記があります。
- Twitter bot 診断キャンペーン
- 特設ページの診断キャンペーン
ここでは、それぞれの種類について順に解説します。
Twitter bot 診断キャンペーン
Twitterのダイレクトメッセージを使用して、botによる自動返信で診断コンテンツを提供する方法です。
募集から当選通知まで、すべてのステップをTwitter内で完結できる特徴があります。Webサイトや他ページに遷移する必要がなく、ユーザーの手間が省けるため手軽に参加しやすい点もメリットです。
Twitter内で完結することによって、キャンペーンへの参加や、診断結果のシェアをしてもらいやすくなると言えるでしょう。
特設ページの診断キャンペーン
キャンペーン特設ページにTwitterやLINE、FacebookなどのSNSアカウントでログインして、診断コンテンツを行う方法です。
開始前にアンケートやエントリーフォームを設けることもできるため、企画に合わせたユーザー情報を取得したい場合に適しています。
特設ページを作ることで、商品やブランドをダイレクトに訴求できるメリットがあります。そのまま自社のECサイトやサービスサイトに遷移させやすいことも特徴です。
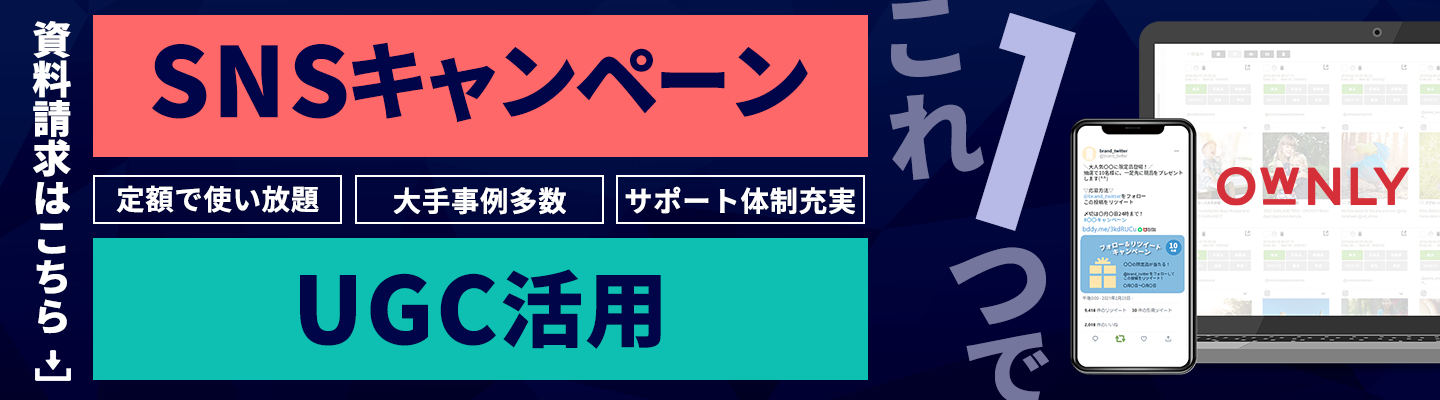
診断キャンペーンのメリット6つ
診断キャンペーンを実施するメリットは下記の通りです。
- 広告感のない自然なプロモーションを行える
- 商品やブランドの理解が深まる
- 診断結果のシェアによる話題化を図れる
- リード獲得や会員登録の導線として活用できる
- コンテンツ資産として長期運用できる
- ユーザーの傾向を把握できる
ここでは、それぞれのメリットを順に解説します。
広告感のない自然なプロモーションを行える
診断キャンペーンは、ユーザーが自ら参加する体験型の仕組みを通じて、商品やブランドの情報を自然に届ける施策です。
質問に答える過程で企業の世界観やサービス内容に触れることができ、ブランドと無理なく接点を持たせられます。
たとえば、性格診断の結果ページに「あなたにおすすめの商品はこちら」と表示された場合も、ユーザーは売り込みと感じにくく、自分ごととして受け入れやすくなります。
こうした流れによって、広告に対して敏感な若年層や情報収集に慎重な層に対しても、抵抗感なくブランドの魅力を伝えることができます。
さらに、診断を通じて得た気づきや共感がシェアされることで、自然な拡散も期待できます。診断コンテンツは、体験そのものが宣伝になる仕組みとして、信頼を損なわずにファンを増やせるプロモーション手法です。
商品やブランドの理解が深まる
診断キャンペーンを実施することで、商品やブランドへの理解を深められる点がメリットです。
たとえば、診断コンテンツを提供しつつ、診断結果の画面で商品やブランドについて訴求することで、より深く興味を持ってもらえる可能性が高まります。
ユーザーを楽しませながら商品を知ってもらえるきっかけとなるでしょう。
診断結果のシェアによる話題化を図れる
診断で面白い結果が出たら、「友人に知らせたい」「家族や友達にも試してほしい」といった心理が働きます。
通常のキャンペーンより自発的なシェアが期待できるため、これまでキャンペーンに参加しなかったユーザーにも訴求しやすい点が特徴です。
ユーザーによるシェアが広がることで、SNS上での大きな話題化が期待できるでしょう。
リード獲得や会員登録の導線として活用できる
診断キャンペーンは、ユーザーの関心を引きつけながら、スムーズに会員登録や情報取得へとつなげることができる施策です。
診断を進める中で「結果を見るにはメールアドレスを入力」といった仕掛けを取り入れることで、自然な流れでユーザー情報の取得が可能になります。
すでに診断に参加している時点で興味が高まっているため、一般的な入力フォームよりも離脱が少なく、登録率の向上が期待できます。
また、取得した情報はその後のメルマガ配信やLINEでの通知、広告配信などにも活用できるため、単発の施策にとどまらず中長期的な顧客育成にもつながるでしょう。
さらに、診断コンテンツ自体が楽しい体験となることで、登録のハードルを下げ、ユーザーに前向きな印象を与える点も強みです。
コンテンツ資産として長期運用できる
診断キャンペーンは、一度作成すれば長期的に活用できる資産型コンテンツとして機能します。
キャンペーンとして期間を区切らず、Webサイトや特設ページに常設することで、継続的にユーザーの流入が期待できます。
たとえば、「○○診断」や「あなたにぴったりの○○チェック」などは、特定の季節やトレンドに左右されにくく、幅広い層が楽しめる内容に仕上げやすいのが特長です。
さらに、定期的に設問を見直したり、結果の表現を変更したりすることで、新鮮さを保ちながら繰り返し活用することも可能です。
景品や特典の入れ替えにより再告知を行うことで、再度話題化も狙えます。こうした柔軟な運用によって、診断コンテンツは単発の施策ではなく、継続的な集客やブランディングを担うマーケティング資産として活躍します。
ユーザーの傾向を把握できる
診断キャンペーンに参加してくれたユーザーの結果から、ユーザーがどんな行動をするのか、どんなものを求めているかなどの傾向を把握できます。
また今後のマーケティング施策に活かせるユーザー属性も入手しやすい点がメリットです。
診断をスタートする前に、性別や年代、都道府県など簡単なアンケートやエントリーフォームを記載することで、スムーズに情報収集が行えるでしょう。
診断キャンペーンのデメリット
診断キャンペーンには大きなメリットがありますが、いくつかデメリットも存在します。実施を検討する前に、デメリットについても把握しておきましょう。
- フォロワーが少ないと話題になりづらい
- 費用が高額になるケースがある
- 企画設計に時間がかかる
- ターゲットによっては参加率が伸びにくい
それぞれ順に見ていきましょう。
フォロワーが少ないと話題になりづらい
いくら面白い診断コンテンツを制作しても、Twitterのフォロワーが少なければ参加人数が少なくなります。診断結果のシェアも発生しづらいため、ユーザー間で話題になりづらいためです。
そのため、フォロワーが少ないのであれば、まずはリツイートキャンペーンなどで認知度を高める必要があるでしょう。
ある程度フォロワーが増えたタイミングで、診断コンテンツを活用したSNSキャンペーンを実施するなどといった戦略的なキャンペーンを考えるのがおすすめです。
費用が高額になるケースがある
診断キャンペーンは、比較的費用がかかりやすい施策のひとつです。
とくに診断コンテンツをゼロから制作する場合、設問設計やロジック構築、デザイン、開発など多くの工程が発生します。制作会社に依頼すると数十万円〜数百万円規模になるケースもあります。
また、SNS広告やインフルエンサー起用などのプロモーション費用も併せて発生することが多いため、自社予算と照らし合わせて検討しましょう。
加えて、システムの保守やキャンペーンページの運用費用も別途かかる可能性があるため、事前に見積もりとスケジュールをしっかり立てておく必要があります。
コストを抑えるには、診断キャンペーンツールやSNSを活用したキャンペーンがおすすめです。
企画設計に時間がかかる
診断キャンペーンは、他のSNS施策に比べて準備に時間がかかる傾向があります。
設問の内容や診断ロジック、トンマナ、ユーザー導線などを細かく設計する必要があり、単純な投稿型キャンペーンのように即日で展開することは難しい場合が多いです。
さらに、設計に時間をかけすぎると公開時期がずれ込み、季節性や話題性を逃してしまうリスクもあります。
魅力的な診断体験を作るには、企画段階から細部まで検討を重ねる必要があります。
短期間で成果を求めたい場合や、スピード重視の施策には不向きとなる可能性もあるため、実施のタイミングや体制を見極めることが重要です。
ターゲットによっては参加率が伸びにくい
診断キャンペーンは、設計やテーマによって成果に差が出やすい施策です。
とくに「診断」に興味を持ちにくいユーザー層を対象とした場合、参加率が想定よりも低くなることがあります。
たとえば、実用性や特典重視の層に向けて、性格診断のような体験型コンテンツを展開しても、動機やモチベーションが噛み合わず参加につながりにくくなります。
また、質問数が多すぎたり結果が曖昧だったりすると、途中で離脱されるリスクも高まるでしょう。
ターゲットに合ったテーマ選定や設問数の調整、参加するメリットの提示などを丁寧に設計することが不可欠です。
診断は万人受けするものではないため、参加率を高めるには、ユーザー理解と企画の方向性が合致しているかを見極める必要があります。
なお、SNSキャンペーンツール「OWNLY」であれば、15種類以上のSNSキャンペーンを定額で行えるため、診断コンテンツを制作するために莫大なコストがかかりません。
診断キャンペーンやSNSキャンペーンを検討している方は、ぜひOWNLYまでご相談ください。
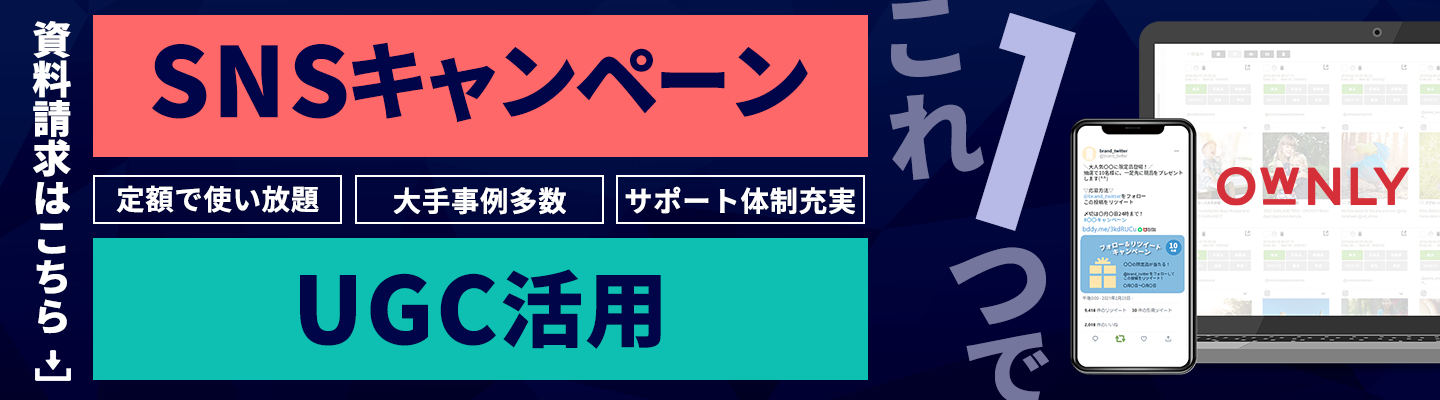
診断キャンペーンを実施する流れ
診断キャンペーンを実施する流れは以下の通りです。
- キャンペーンの目的を明確にする
- ターゲット・目標を決める
- 診断コンテンツを企画する
- キャンペーンの実施・効果検証を行う
ここでは、診断キャンペーンを実施する流れを解説します。
1. キャンペーンの目的を明確にする
まずは、診断キャンペーンを実施する目的を明確にしましょう。
目的を「認知拡大」にするのか「ブランディング」にするのかなど目的によって、キャンペーンの打ち出し方や戦略が大きく異なるためです。
キャンペーンの目的を固めないと、方向性にブレが生じてしまい、キャンペーンが失敗に終わる可能性があります。
2. ターゲット・目標を決める
目的が決まったら、ターゲット層や目標を定めましょう。
どんな層に向けてキャンペーンを実施したいのかを明確にしたうえで、目標にすべき指標(KGI・KPI)の数値を定めます。
|
KGI:プロジェクトなどの長期的な最終目標のこと
KPI:プロセスごとの短期的な達成度を測る中間目標のこと
|
またターゲットを決めるときは、より深堀りして顧客増をイメージしやすい「ペルソナ」を設定しましょう。
3. 診断コンテンツを企画する
目的やターゲット、目標が定まったら、診断コンテンツを企画しましょう。
キャンペーン内容で企画すべき内容は、主に以下があります。
- 診断コンテンツの内容
- 実施期間
- 参加条件
- 抽選方法
- 景品・クーポンの選定
- 特設ページの有無
|
診断キャンペーンは、いかに参加したくなる魅力的なコンテンツを作成できるかが重要です。またユーザーにメリットを感じさせるために、景品やクーポンを用意します。
キャンペーンの企画を行う前に、キャンペーンツールに問い合わせるといいでしょう。
4. キャンペーンの実施・効果検証を行う
企画した内容をもとにキャンペーンを実施します。期間中はこまめにツールで数値をチェックして、必要に応じて告知回数を増やしたり、改善を行いましょう。
期間中は問い合わせ対応が必要になるケースもあります。あらかじめキャンペーン規約を定めたうえで、問い合わせ先を記載しておくと安心です。
キャンペーンが終了したら、あらかじめ定めた指標をもとに効果検証を行いましょう。目標を達成できたか数値を分析することで、今後のマーケティング施策に活用できます。
診断キャンペーンの活用事例3選
ここからは、診断コンテンツを活用したキャンペーンの成功事例を紹介します。
株式会社湖池屋|#ピュアポテト診断キャンペーン

参照:あなたはどのタイプ?#ピュアポテト診断キャンペーン|OWNLY導入事例
株式会社湖池屋は、「ピュアポテト ブランド芋くらべ」シリーズの発売を記念して、X(旧Twitter)上で完結する診断キャンペーンを実施しました。
参加者は公式アカウントをフォローし、診断後に結果をシェアすることで応募できます。
特設ページへのログインが不要な点が特徴で、ユーザーの手間を減らしながら参加ハードルを下げています。
本キャンペーンでは、ピュアポテトの品種ごとの特徴を診断結果として提示し、自然なかたちで商品の魅力を伝える仕組みを採用。
投稿を通じた拡散やUGCの増加を促すことで、SNS上での話題化とブランド認知の向上を狙った施策です。
ミツカン|#Suppin診断キャンペーン
ミツカン公式Twitterアカウントでは、簡単な診断でSuppin(素顔)がわかる診断キャンペーンが実施されました。
公式アカウントをフォローの上、診断結果をツイートすると抽選で100名にプレゼントが当たるという内容です。
診断結果に応じて、「そんなあなたには○○がおすすめ」と同社の商品を訴求することで、商品の魅力が伝わりやすくなっています。
シャイロックの子供たち|シャイロックキャラ診断
映画「シャイロックの子供たち」公式Twitterでは、キャラクター診断キャンペーンが実施されました。
公式Twitterの投稿から診断を進めて、結果をシェアすることで抽選で50名に映画関連グッズが当たるという内容です。
映画に登場するキャラクターからどのタイプかを診断できるというもので、映画への興味関心を促し、理解を深めることで話題化に成功しました。
診断キャンペーンを成功させるコツ5つ
診断キャンペーンを成功させるには、以下のコツを意識しましょう。
- ペルソナやトンマナに合わせたUI・導線設計を行う
- 拡散・参加を促す導線を設計する
- 事前のリスク管理と問い合わせ対応を想定する
- 事後アンケートでユーザーの声を回収する
- 他施策と組み合わせて相乗効果を狙う
ここでは、それぞれのコツについて解説します。
ペルソナやトンマナに合わせたUI・導線設計を行う
診断キャンペーンの成果を左右する要素の一つが、ペルソナとトンマナに合わせたUI・導線設計です。
診断の内容だけでなく、配色やフォント、イラスト、文体なども含めて、想定するユーザー像に寄り添ったトーンで統一しましょう。
たとえば、Z世代向けであればポップで明るい色合いやカジュアルな言葉づかい、ビジュアル重視のUIが効果的です。
一方、30代以上のビジネス層には落ち着いたデザインや丁寧な言い回しが好まれる傾向があります。
また、スマホ利用を前提とした場合は、タップしやすいボタン設計や縦スクロール前提の構成も求められます。ペルソナに合わせたUIとトンマナを丁寧に設計することで、診断中の離脱を減らし、最後まで楽しんでもらえる体験が実現できます。
拡散・参加を促す導線を設計する
診断キャンペーンの効果を最大化するには、参加後の行動を促す導線設計が欠かせません。とくにSNS上での拡散効果を狙う場合は、診断結果のページにシェアボタンを設置するだけでは不十分です。
シェア文言の自動生成やハッシュタグの設計、結果画像のビジュアル化など、ユーザーが「思わず投稿したくなる仕掛け」を用意することが重要です。
さらに、友達招待で景品がもらえる仕組みを加えれば、参加の広がりを自発的に生み出すこともできます。
また、参加後に再診断や別コンテンツへ誘導することで、継続的な接点を作ることも可能です。単に楽しんで終わる診断ではなく、ブランドの情報拡散や再訪問につながる動線を設計することで、キャンペーンの効果をより高めることができます。
事前のリスク管理と問い合わせ対応を想定する
診断キャンペーンを実施する際には、事前に起こり得るリスクを想定しておくことが不可欠です。
たとえば、サーバーエラーや表示不具合が起きた場合、対応の遅れがユーザーの不満や炎上につながることもあります。
また、診断内容や結果に対して「不快に感じた」「偏っている」といった声が上がるリスクもゼロではありません。
こうしたトラブルに備えて、キャンペーン前に表示内容のチェック体制を整え、必要であればテスト公開を行うと安心です。
また、参加者からの問い合わせに対応できる体制も重要です。あらかじめ問い合わせ先を明記し、よくある質問をまとめたページを用意しておくことで、トラブル時の対応スピードが向上します。
事後アンケートでユーザーの声を回収する
キャンペーン終了後の振り返りにおいて、ユーザーのリアルな声を回収することは非常に重要です。
アクセス数やシェア数といった数値データだけでは見えない改善点や成功要因を、参加者の主観的なフィードバックから把握できます。
たとえば「診断が長かった」「結果に納得感がなかった」などの声は、次回の改善に直結します。アンケートは診断後のページやメール・LINE経由で簡単に実施できるため、負担の少ない設問数で設計するのがポイントです。
自由記述欄を設ければ、意外なヒントが得られることもあるでしょう。データとあわせてユーザーの声を蓄積していけば、診断施策そのものの質を高めていくことができます。
他施策と組み合わせて相乗効果を狙う
診断キャンペーンは、他のマーケティング施策と組み合わせることで、より大きな成果を生むことができます。
たとえば、以下のようにユーザーの関心に応じて導線を設計することで、エンゲージメントが高まるでしょう。
- 診断結果をもとにメールマガジンで個別おすすめ商品を案内する
- SNS広告で再アプローチする
また、ECサイトと連携し、診断結果に応じた商品ページへ遷移させれば、購入率の向上も期待できます。
さらに、キャンペーン期間中にインフルエンサー投稿やコラボ企画を同時展開することで、認知獲得と拡散の両立が図れます。
診断単体で完結させず、接点を起点に次のアクションへとつなげていく設計が重要です。複数の施策を連動させることで、施策全体の効果を最大化できます。
診断キャンペーンを実施するなら「OWNLY」
診断キャンペーンは、SNS上での話題化を図りやすいマーケティング手法です。商品やサービスの認知拡大、売上アップに貢献できるでしょう。
通常のリツイートキャンペーンなどに比べて、商品やサービスへの訴求力が高く、自発的なシェアによる拡散が期待できます。
OWNLYでは、診断コンテンツを含む15種類以上のSNSキャンペーンを定額で無制限にご利用いただけます。キャンペーンに必要な機能の提供はもちろん、事務局代行やノウハウをもとにしたサポート体制も充実しています。
「診断キャンペーン以外にも施策を実施したい」「SNS運用に力を入れたい」とお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。