共感マーケティングは、ユーザーに共感してもらえる仕組みを作り、売上アップやブランディング、ファン化を狙う戦略です。
「共感を得るビジネスとは?」「共感マーケティングの企業事例やSNSの活用例を知りたい」とお考えの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、共感マーケティングが注目されている理由や、戦略を検討するステップ、企業によるSNS活用事例、注意点などを徹底解説します。
共感マーケティングとは?
共感マーケティングとは、ユーザーの共感を生む仕組みを作り、売上アップやブランド価値の向上を狙うマーケティング手法のことです。
たとえば、昨今注目されているSDGsの取り組みも共感マーケティングに該当します。企業が抱える目標に目を向けることで、ユーザーとの間で共通認識が生まれ、共感が発生して売上アップやファン増加につながります。
また、参加型キャンペーンでファンを増やしたり、クラウドファンディングによって支援者を増やしたりする施策も、共感を発生させる取り組みが重要です。
共感マーケティングが注目されている理由
近年、インターネットやSNSが発達する中で、消費者側が情報収集してモノを選ぶことが主流になりました。
単純に「流行っているから」「商品の品質が良いから」という理由だけでなく、商品に対して共感や価値を感じられるかが購買の決め手となっています。
また、アフィリエイトなどの普及によって、インターネット上の評判に対する信頼性は下がっており、SNSで投稿される消費者の生の声が重要視されています。
SNSは拡散性が高いため、「共感がさらに共感を呼ぶ」という連鎖が可能となり、ユーザーの共感を生むことでさらなる認知度向上が見込めます。
顧客の評判や口コミ、ユーザーが生成するコンテンツ(UGC)を生み出すための戦略を整えるのが、共感マーケティングが注目される理由のひとつです。
共感マーケティングを実施する4ステップ
共感マーケティングを実施する際は、以下のステップに沿って進めましょう。
- ペルソナやニーズを分析する
- 共感ポイントを洗い出す
- ストーリーを発信する
- UGCを生み出す仕組みを作る
ここでは、それぞれの進め方について解説します。
1. ペルソナやニーズを分析する
まずは、共感マーケティングを展開するターゲットを絞りましょう。
ターゲットが抱える悩みやニーズを分析することで、共感を得られる情報発信が行えるようになります。
このとき、単純に「20代女性」のように大まかなユーザー像を決めるのではなく、家族構成や休日の過ごし方、趣味など実在する人物のように細かくペルソナを設定します。
ペルソナを設定したら、ニーズや課題などを分析し、共感してもらえるコンセプトやストーリーを考えていくことが大切です。
ペルソナやニーズの分析を怠ると、ターゲットから共感を得られない情報を発信してしまうことになり、かえって逆効果になる可能性もあります。
■関連記事
SNSマーケティングで重要なペルソナ設定とは|具体例や作成のコツを紹介
2. 共感ポイントを洗い出す
次に、ペルソナに共感してもらえるポイントを洗い出します。
共感マーケティングでは、どれだけ濃く質の高いファンを作れるかが重要となるため、ファンの熱量を重視することが大切です。
必要に応じて、ユーザーへのアンケートやインタビューを行い、ペルソナが共感してくれそうなコンセプトを見つけましょう。
自社のマーケティングをどのプラットフォーム上で行うべきかお悩みの方や、ターゲット層に届くSNS活用術を知りたい方は、以下の資料をぜひチェックしてください。
資料では、下記のような内容を解説しています。
- Twitter/Instagram/TikTok/LINEなどの様々なSNSの強みや特徴
- 各SNSの利用層の詳細
- 各SNSに最適なキャンペーン施策の詳細

3. ストーリーを発信する
商品やサービスが完成したら、商品に込めたストーリーを発信しましょう。
たとえば、以下のようなものが挙げられます。
- なぜこのコンセプトにしようと思ったか
- 商品を利用したお客さまにどんな変化があったか
- どのような価値を提供する想いがあるのか
- 開発の苦労や課題はあったか
|
このようなストーリーを自社コンテンツやSNS、広告などで発信することで、共感を集めやすくなります。熱量が高いほど、質の高いファン獲得を目指せるでしょう。
4. UGCを生み出す仕組みを作る
共感してくれる自社のファンを集めると同時に重要なのが、UGCを生む出す仕組みを作ることです。
UGC(User generated Content)とは、SNS投稿などユーザー自身が生み出したコンテンツのことを指します。
熱量の高いファンを集めれば、一部のファンは自発的にSNSで投稿してくれることもありますが、UGCを増やすには企業側から仕組みを作ることが必須です。
たとえば、ユーザー参加型のキャンペーンを実施したり、ユーザーとコミュニケーションを深めて自分ゴト化を促進することをおすすめします。
■関連記事
UGCマーケティングとは?重要性やメリット・実施手順・活用事例などを解説
企業による共感マーケティングの事例4選
ここからは、企業による共感マーケティングの事例について紹介します。
1. ホテル椿山荘東京
ホテル椿山荘東京の公式Xアカウントでは、「記念日を過ごすならあなたはどっち?キャンペーン」と称して、投票キャンペーンを実施しました。
用意された複数の選択肢のうち、投票数が多かった方に投票した人の中から、抽選で5組10名に豪華ディナー券をプレゼントするという内容です。
参照:#記念日なんだし椿山荘|OWNLY導入事例
投票キャンペーンを実施することで、ユーザーが2つの選択肢を検討する際に共感を生み出したり、自社ブランドの魅力を感じてもらうことができます。
また、自社のハッシュタグを付けてツイートしてもらうことで、認知拡大や話題化につながります。
■関連記事
Twitterの投票キャンペーンとは?成功事例5選やメリット、注意点を解説
2. 株式会社湖池屋
株式会社湖池屋では、同社が販売する「ピュアポテト ブランド芋くらべ」シリーズの発売を記念して、X上で完結する診断キャンペーンを実施しました。
キャンペーンツイートから診断に参加し結果をシェアすると、抽選で20名にピュアポテトの詰め合わせが当たるという内容です。
参照:あなたはどのタイプ?#ピュアポテト診断キャンペーン|OWNLY導入事例
質問に答えるとおすすめのピュアポテトが紹介されるという診断内容を通じて、商品の認知度向上や想起性の向上などにつながっています。
数種類のピュアポテトの特徴を発信しつつ、ユーザーの投稿を促進することで、UGCを増やしたり、共感を生み出している事例です。
■関連記事
Twitter診断キャンペーンとは?メリットや成功事例、実施の流れまで徹底解説
3. エイベックス・ピクチャーズ株式会社
エイベックス・ピクチャーズ株式会社では、TVアニメ「僕の心のヤバいやつ」公式Xアカウントにて、バレンタイン感想投稿キャンペーンを実施しました。
ファンが「好きな場面写真」を選び、感想をハッシュタグ付きで投稿することで、抽選で3名にアニメグッズの詰め合わせがプレゼントされるという内容です。
参照:僕ヤバ愛を語ろう!バレンタイン感想投稿キャンペーン|ONWLY導入事例
バレンタインにあわせてファンに作品について呟いてもらうことで、ファン同士の共感を生み出し、UGC生成や顧客ロイヤリティ向上につながっています。
4. カルビー株式会社
カルビー株式会社が販売するじゃがりこ公式Xアカウントでは、「#じゃがりこ1個分のごめんね」と称して、ユーザー投稿型キャンペーンを実施しました。
公式アカウントをフォローの上、指定のハッシュタグを付けて謝りたい相手やエピソードを投稿すると参加すると、その場で抽選に参加できるというものです。
参照:「♯じゃがりこ1個分のごめんね」を伝えるTwitterインスタントウィンキャンペーン|OWNLY導入事例
さらに、謝りたい人にメンションを付けて投稿した方から、抽選で100名に同社商品が当たるWチャンスも用意されました。
ユーザー同士で共感の連鎖を生み、認知拡大やブランドの想起性を高めることにつながっています。
共感マーケティングにおける注意点
共感マーケティングを実施する際は、以下の点に注意しましょう。
- コンセプトに一貫性がない
- 売りたいという気持ちが露呈している
- BtoB商材には向かないケースがある
ここでは、それぞれの注意点について解説します。
コンセプトに一貫性がない
商品やサービスのコンセプトに一貫性がないことは、ユーザーが共感を得にくい要因のひとつです。
コンセプトが異なる商品を展開すると、発信するストーリーに矛盾が生じたり、ユーザーが離れてしまう可能性もあります。
一貫性のあるコンセプトを意識して、ファンとの濃く長い関係性を構築することが大切です。
売りたいという気持ちが露呈している
共感マーケティングは、企業側の「売りたい」という気持ちが露呈すると失敗してしまいます。共感マーケティングは、あくまでファンの熱量を高めたり、ブランドの価値を向上させるための施策です。
結果として売上アップにつながるものであり、初めから宣伝であるとユーザーに感じさせてしまっては、ファンの熱量も高まらないでしょう。
商品を売ることはもちろん大切ですが、「売りたい」という気持ちを抑えて、ファンとの交流を優先することが大切です。
BtoB商材には向かないケースがある
共感マーケティングは、ユーザーからの「共感」や「愛着」が主軸です。
一方で、BtoB商材は金額が大きく、成果を第一に考えるため、共感マーケティングとの相性が悪いと言えます。
BtoB商材でSNSマーケティング戦略を取り入れたい場合は、ターゲティングが行いやすいSNS広告がおすすめです。
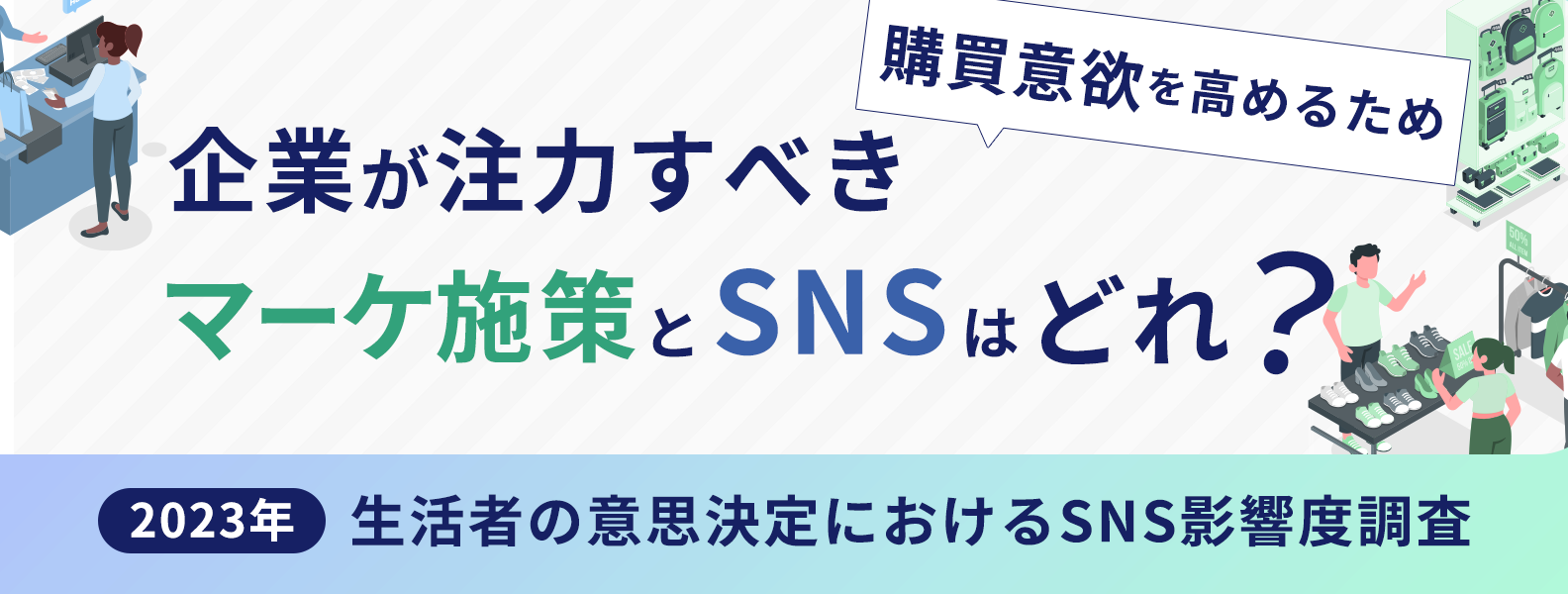
まとめ
共感マーケティングは、消費者との長期的かつ良質な関係性構築につながるマーケティング施策です。
共感マーケティング戦略はSNSと相性が良いため、SNSキャンペーンやUGCマーケティング、インフルエンサーの活用を通じてより効果的な施策を検討しましょう。
SNSを活用して共感マーケティングを展開したいとお考えの方は、SNSマーケティングツール「OWNLY」の活用がおすすめです。
OWNLYでは、SNSキャンペーンをやUGCマーケティング、インフルエンサー施策などを通じて広告運用の効果を最大化するためのサポートを行っています
商品広告やプロモーション戦略を検討している方は、まずはお気軽に下記の資料をダウンロードしてください。

