2023年10月より景品表示法において「ステマ(ステルスマーケティング)規制」の施行が開始され、ステマに関する規制が強化されました。
ステマ規制について「なんとなく知っているけど詳しく説明できない」「広告やSNS運用で気を付けるべきことは?」と疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
本記事では、事業者やSNS運用担当者が知っておくべきステマ規制について、対象となるケースや注意点についてわかりやすく解説します。
正しい知識を身に着けたうえで、ステマ規制を回避して正しくインフルエンサーマーケティングやSNS広告を活用したいと検討している方は、ぜひ本記事と併せて以下のセミナー動画をご視聴ください。
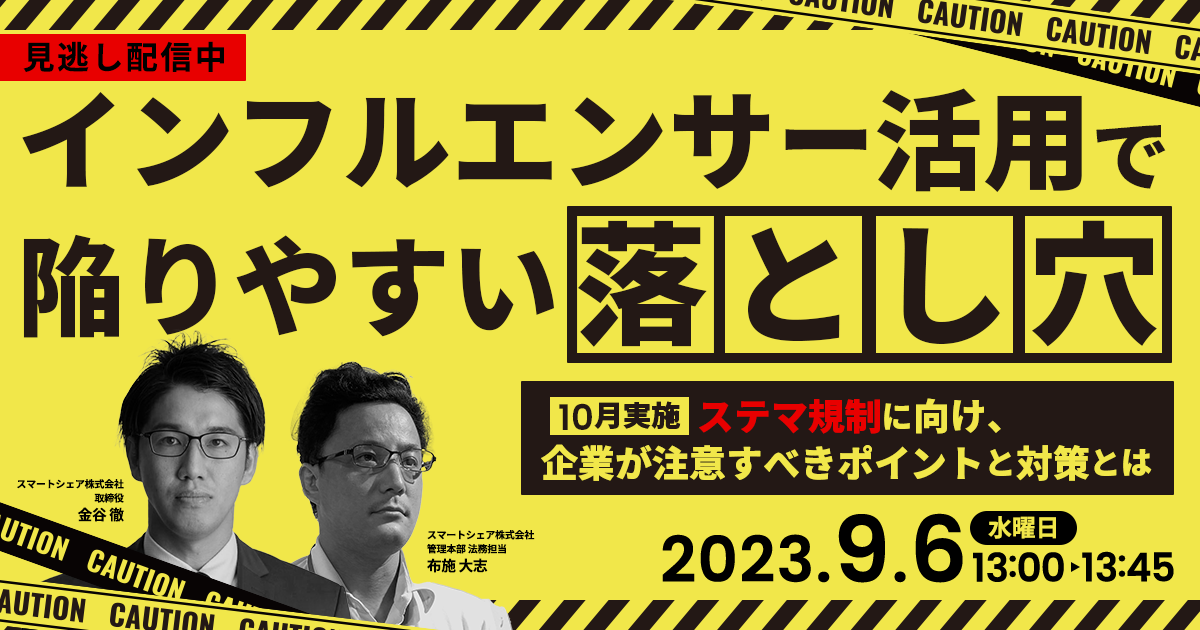
ステルスマーケティング規制とは【2023年10月から施行】
2023年10月1日にステマ(ステルスマーケティング)規制が施行され、ステマが景品表示法で禁止される「不当表示」に指定されました。
景品表示法は消費者庁が所管しており、大袈裟な表示や虚偽の表示、課題な景品類の提供を防ぎ、消費者を守るための法律です。
そのため、商品・サービスを提供する事業者や広告主等は、従来と同じように広告やSNSを運用していると、景品表示法違反になる可能性があります。
ステマ行為自体は規制対象となるので、金銭授受が発生していない場合も法規制の対象となることもあるでしょう。
規制の対象は事業者のみ
規制・懲罰の対象は事業者のみとなっており、宣伝の依頼を受けたインフルエンサーなどの第三者は、規制の対象外となります。
ステマ規制は事業者に向けた規制なので、違反した場合の措置命令や懲罰は事業者に課せられます。
施行日以前の表示も対象となる
ステマ規制が施行されるのは2023年10月1日です。しかし、規制対象となるのは2023年9月30日以前の表示も含まれます。
事業者は、過去に出した広告やSNS投稿の内容についても対策しなければなりません。
そもそもステルスマーケティング規制とは?
ステマ(ステルスマーケティング)とは、広告であることを隠して商品やサービスの宣伝・広告のことです。
景品表示法においては、以下の2つの要件を満たす表示がステマにあたるとされています。
- 一般消費者が事業者の表示であることを判別するのが困難である表示
- 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの
|
引用:内閣府告示第十九号
ステマは、大きく分けて「利益提供秘匿型」と「なりすまし型」の2つがあります。それぞれの種類について見ていきましょう。
利益提供秘匿型
利益提供秘匿型は、企業から依頼を受けた第三者が、利益を受けていることや依頼されたことを隠して広告・宣伝することです。
たとえば、芸能人やインフルエンサーが企業から依頼を受けたことを隠して、個人的な感想であるかのように商品を紹介することなどが該当します。
近年は、こうした利益提供秘匿型のステマがSNS上で大きく問題視されており、世間の目も厳しくなっている傾向にあります。
なりすまし型
なりすまし型は、商品やサービスを提供している会社の人や関係者が、一般消費者になりすまして広告・宣伝を行うことです。
たとえば、自社商品をAmazonで販売し、商品のレビューにおいて一般消費者のフリをして「良い商品」「効果があった」と書くことはステマにあたります。
企業の従業員が身元を隠し、個人のSNSで自社の商品の良い口コミを発信する行為はなりすまし型に該当するので注意が必要です。
■関連記事
SNSのステマとは?ステマ規制や炎上の具体例、対策法も解説
ステルスマーケティング規制が施行された背景
近年SNSの普及とともに有名人を利用したステマが横行し、消費者が合理的に商品を選べず、不利益を被ることが問題視されはじめたことがきっかけです。
ステルスマーケティングに関する検討会によると、ステマによる宣伝手法は、通常の広告よりも効果が高いという実態もあるようです。
- ステマによって、売上が少なくとも20%程度は増加する傾向にある
- インフルエンサーによるステマによって売上が数倍程度になるなど、大きな広告効果がある
|
このように、事業者にとってはステマを行うメリットが大きいことが分かります。ステマ行為が後を絶たないことで、消費者がより広告に嫌悪感を持ち、さらにステマが横行するという悪循環に陥りかねませんでした。
従来まではステマを取り締まる法律がありませんでしたが、令和4年9月にステルスマーケティングに関する検討会が設置され、ステマ規制の施行が決定しました。
ステルスマーケティング規制の対象となる基準
ステマ規制の対象になるかどうかは、以下の2つが基準となります。
- 事業者の表示であるかどうか
- 広告宣伝であることが判別できるか
それぞれの基準について詳しく見ていきましょう。
事業者の表示であるかどうか
事業者自らが行う表示や、事業者が第三者になりすまして行う表示はステマ規制の対象となります。自社サイトやSNSで商品やサービスについて言及する際は、ステマ規制が適用される場合があるため注意が必要です。
また、事業者や子会社の従業員が、第三者になりすまして商品やサービスを宣伝した場合もステマ規制の対象となります。
事業者の社員や子会社の社員は、事業者と一体と認められる場合があり、社員や子会社においてもステマ規制が適用される場合があるため注意しましょう。
広告宣伝であることが判別できるか
芸能人やインフルエンサーなどの第三者に対して、事業者が依頼や指示をして表示を行った場合も、ステマ規制の対象になります。
たとえば、インフルエンサーに報酬を渡して依頼したのにもかかわらず、「PR」「広告」といった表示をせずに宣伝した場合などです。
また、事業者が第三者に対して明らかに依頼や指示をしていない場合でも、第三者に表示させたとして判断されることもあります。
事業者とどのようなやり取りをしたか、金銭授受(対価)は発生したか、事業者と第三者の関係性などから総合的に判断されます。
対価のやり取りは金銭や物品に限らない点も把握しておきましょう。
ステルスマーケティング規制の対象外となるケース
ステマ規制の対象外となるのは、以下のようなケースです。
- 広告や事業者の表示であることが明らかな場合
- 第三者が自主的に表示した場合
それぞれ詳しく見ていきましょう。
広告や事業者の表示であることが明らかな場合
広告であることや事業者による表示であることが分かりやすい形で明記されている場合は、ステマ規制の対象となりません。
たとえば、以下のようなケースが該当します。
- 「広告」「プロモーション」「宣伝」と一般的に使われる文言を分かりやすく明記している
- 事業者が協力している番組等で、エンドロールにスポンサー名を明記している
- 事業者自身のSNSアカウントやWebサイトを通じた表示
- 商品やサービスの紹介を目的とした表示
- テレビCMMのように広告と番組が切り離されている表示
|
引用:景品表示法とステルスマーケティング ~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~
第三者が自主的に表示した場合
第三者の表示に関与した場合でも、客観的な状況にもとづいて、「第三者の自主的な意思による表示」と認められた場合は、ステマには該当しません。
たとえば、事業者に依頼を受けたが低評価を付けた投稿、サンプルとして受け取ったが自由に感想を書いた投稿、キャンペーンに応募するためのコメントなどです。
事業者の指示ではなく、自主的な意思にもとづいた感想を投稿しているため、ステマ規制の対象外となります。
ステルスマーケティング規制の対象になりうる事例
ステルスマーケティング規制では、消費者を誤認させるおそれのある表示が対象となります。特に、次のようなケースは規制に該当する可能性があるため注意が必要です。
- 依頼であることを隠して発信する
- レビューサイトでサクラを雇い評価を上げる
それぞれの事例について解説します。
依頼であることを隠して発信する
企業から依頼や報酬、商品提供を受けているにもかかわらず、事実を明示せずに情報発信を行う行為は、ステルスマーケティング規制の対象となる可能性があります。
例えば、企業がインフルエンサーに商品を無償提供し、SNSでの紹介を依頼したケースが挙げられます。
この際、「提供」「PR」「広告」といった表示をせず、あたかも個人的に購入して使った感想のように投稿しないよう注意が必要です。
レビューサイトでサクラを雇い評価を上げる
実際の利用者ではない人物に高評価の口コミを投稿させる行為も、ステルスマーケティング規制の対象となり得ます。
例えば、企業が外部業者に依頼し、商品やサービスを利用していないにもかかわらず「、た好意的なレビューを大量に投稿させるケースが挙げられます。
レビューの公平性を損なう行為は、規制リスクだけでなく企業の信用低下にも直結するため、避けるべき運用と言えるでしょう。
ステルスマーケティング規制に違反した場合はどうなる?
ステマ規制に違反した事業者は、消費者庁から措置命令が下されます。
措置命令に従わない場合は刑事罰の対象となり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、または両方が科せられます。
近年はステマに対する世間の風当たりも強く、企業全体としてのイメージが悪くなり、業績悪化などにつながる可能性もあるでしょう。
ステルスマーケティング規制に違反しないための対策
ステマ規制に違反しないためには、どのような対策をすべきでしょうか。
- 広告であることを分かりやすく明記する
- SNSに関する社内ルールを策定する
ここでは、それぞれの対策について解説します。
広告であることを分かりやすく明記する
ステマ規制に違反しないためには、広告宣伝であることを分かりやすく明記しましょう。
一目見て消費者に伝わるように、読みやすい大きさと色に設定すると、事業者の表示であることが伝わります。
具体的には、「PR」「広告」「宣伝」といった表示を行います。インフルエンサーに依頼する場合は、必ず明記して投稿してもらうよう徹底しましょう。
X(旧Twitter)ならハッシュタグ、Instagramならブランドコンテンツ機能、YouTubeならテロップなど各媒体に合わせてPRの記載をしてもらうと安心です。
■関連記事
Instagramのブランドコンテンツツールとは?メリットや実施手順も解説
SNSに関する社内ルールを策定する
自社の広報担当者や営業担当者が、第三者であるとなりすまして個人アカウントで自社商品の良い口コミを投稿した場合はステマとなります。
匿名のアカウントであっても規制対象となるので、自社商品をSNSで紹介する際は、企業名や本人の立場を明らかにし、自社商品の紹介であることを明記しましょう。
意図せずステマをしてしまわないよう、社員向けにSNS投稿に関するルールを策定したり、教育・研修を行って周知を徹底する必要があります。
■関連記事
SNSの企業アカウント運用の成功事例!運用のコツや各SNSの特徴も解説
ステルスマーケティング規制についてのよくある質問
ここからは、ステルスマーケティング規制に関するよくある質問について回答します。
ステルスマーケティング規制の具体例は?
ステルスマーケティング規制の対象となるのは、広告であるにもかかわらず、事実を消費者に分かりにくくする表示や発信です。
具体的には、次のようなケースが該当する可能性があります。
- 企業から報酬や商品提供を受けたにもかかわらず、「PR」「広告」「提供」などの表記をせずにSNSへ投稿する
- インフルエンサーに依頼し、個人の感想を装って商品やサービスを紹介させる
- 社員や関係者が一般ユーザーを装い、口コミサイトやSNSで自社商品を高く評価する
- レビューサイトで実際の利用者ではない人物に高評価の投稿を行わせる
企業が発信を依頼する場合は、広告であることを明確にし、誤解を招かない表示を行う必要があります。
参照:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。|消費者庁
ステルスマーケティングは何が悪い?
ステルスマーケティングが問題視される理由は、消費者の正しい判断を妨げてしまう点にあります。
広告であることが明示されていない情報は、消費者にとって第三者の客観的な意見に見えやすく、意図せず誤った認識を持たせるおそれがあります。
本来、消費者は「広告かどうか」を踏まえたうえで、商品やサービスを比較・検討しています。ステマによって、購入後に「広告だと知らなかった」と不信感を抱くケースも少なくありません。
また、ステルスマーケティングは一時的に売上につながったとしても、発覚した際の影響は大きくなります。消費者との信頼関係を守るためにも、広告である場合は正しく伝えることを心がけましょう。
ステルスマーケティング規制に違反するとどうなる?
ステルスマーケティング規制に違反したと判断された場合、消費者庁から行政処分を受ける可能性があります。
具体的には、消費者に誤解を与えた表示や発信をやめること、同様の行為を繰り返さないための再発防止策を講じることなどを命じられます。これは「措置命令」と呼ばれ、企業としての対応が公的に求められるものです。
なお、ステルスマーケティングそのものは、原則として課徴金の対象にはなりません。
ただし、違反行為の内容に「優良誤認表示」または「有利誤認表示」が含まれる場合、課徴金の納付を命じられる可能性もあるため注意しましょう。
参照:ステルスマーケティングに関するQ&A|消費者庁
口コミ投稿の要求は罰則の対象になる?
口コミ投稿を依頼すること自体が、直ちにステルスマーケティング規制に違反するわけではありません。重要なのは、企業が口コミの内容にどこまで関与しているかという点です。
例えば、
以下のような場合は、企業が表示内容を決定しているとは言えず、通常は規制の対象になりません。
- サービス利用後に口コミ投稿を促し、対価として割引や特典を提供する
- 投稿内容や評価について具体的な指示をせず、率直な感想の投稿を求める
一方で、「星5評価を付けること」「高評価や好意的なコメントの投稿を求める」場合、企業が評価内容に関与していると判断されます。
広告であることを明確に表示しなければ、規制に違反する可能性があります。口コミ施策を行う際は、投稿内容を誘導しない運用が重要です。
SNSへの投稿を呼びかけるのはOK?
SNSへの投稿を呼びかける行為自体は、必ずしもステルスマーケティング規制に違反するものではありません。
内容に踏み込まず、あくまで任意での投稿を促す形であれば、問題にならないケースが多く見られます。
たとえば、街頭で試供品を無償配布し、「よろしければ使用後の感想をSNSに投稿してください」と声掛けする程度であれば、通常は規制の対象になりません。
投稿の有無にかかわらず商品を配布しており、評価内容や表現について指示していないためです。
SNS施策を行う際は、あくまで自由意思による投稿であることが伝わる運用を心がけることが重要です。
まとめ
2023年10月より、広告であることを隠して宣伝する「ステルスマーケティング」が景品表示法で規制されました。規制対象には、施行日以前の表示も含まれるため、法律違反にならないよう、自社の広告であることを明記しなければなりません。
なお、規制の対象となるのは事業者のみで、インフルエンサーは規制の対象外です。インフルエンサーに対しては、投稿がPRである旨を記載してもらうようにしましょう。
ONWLYでは、SNSキャンペーンやUGCマーケティング、インフルエンサーマーケティングをはじめ、SNSマーケティングをサポートいたします。
■合わせて読みたい
SNSにおける薬機法とは?NG表現例や施策時の対策について解説

