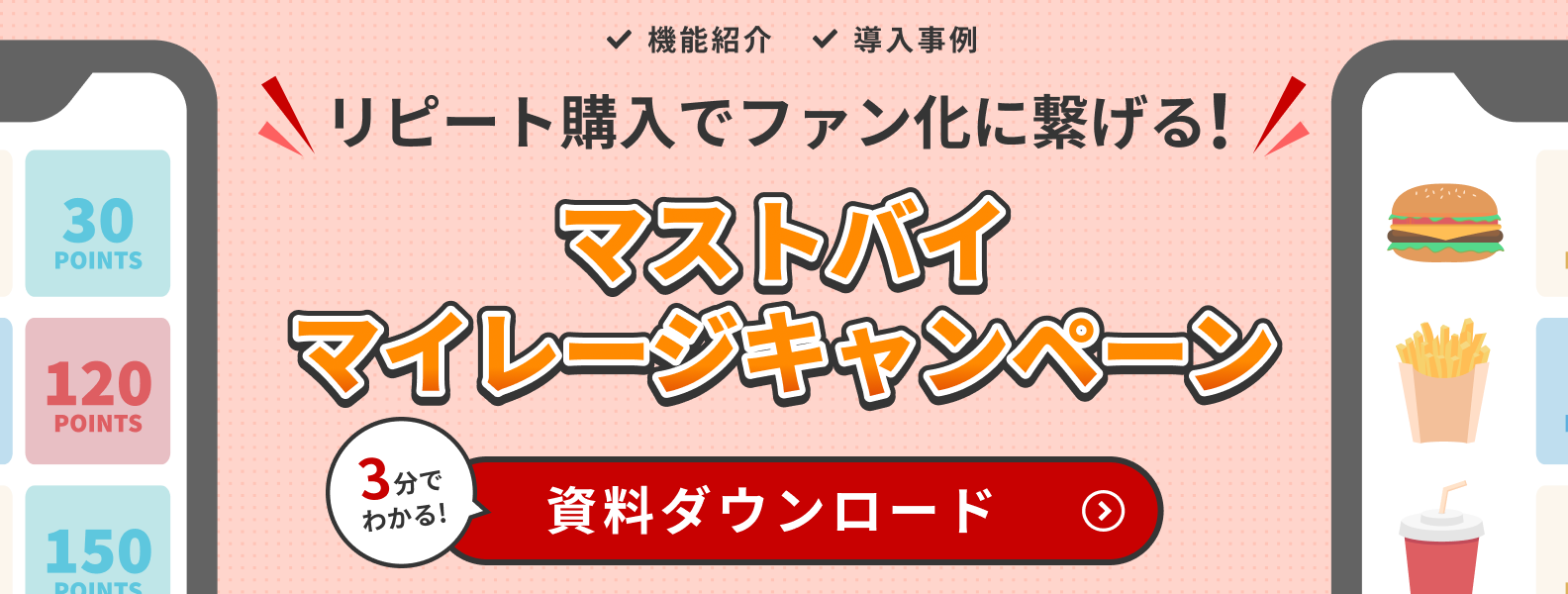マストバイキャンペーンは、数あるキャンペーンの中でも「商品の購入促進」につながるマーケティング施策のひとつです。
キャンペーン施策を実施するにあたって、マストバイキャンペーンを検討している方もいるのではないでしょうか。
当記事では、マストバイキャンペーンの目的や購入証明の種類、事例について紹介します。応募率を高める方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
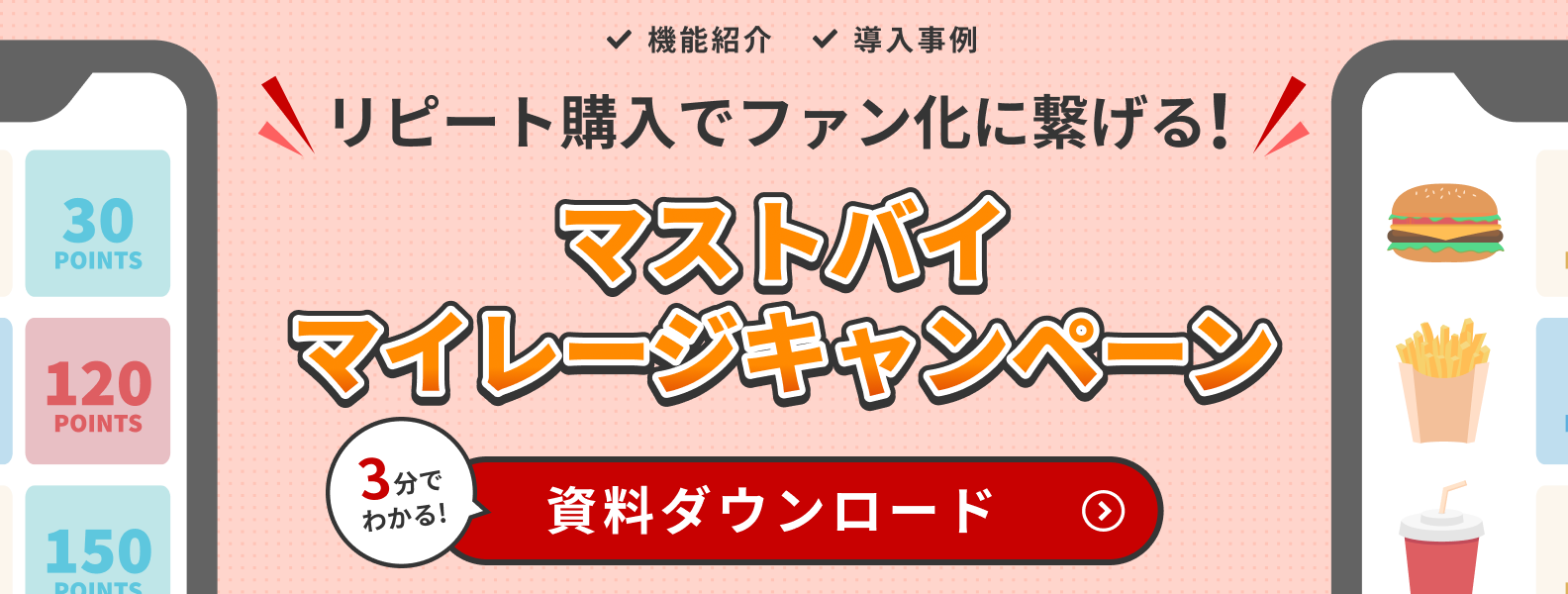
マストバイキャンペーンとは
マストバイキャンペーンは、商品やサービスの購入・利用を促すキャンペーン施策のことです。消費者が商品やサービスを購入することを応募条件となっています。
たとえば、「指定商品を購入する」「〇〇円以上購入する」などといった、購入を前提条件とするタイプがマストバイキャンペーンです。
▼マストバイキャンペーンの例
- 購入後のレシートをアップロードして応募するキャンペーン
- 購入した商品のパッケージに記載されているシリアルナンバーを入力して応募するキャンペーン
- 購入した商品に付属するシールを集めてはがきで応募するキャンペーン
|
いずれの場合も、商品を購入した証明を応募に用いる必要があります。
マストバイキャンペーンとクローズドキャンペーンの関係性
マストバイキャンペーンは、対象商品を購入したユーザーのみが参加できる「クローズドキャンペーン」の一種です。
キャンペーン施策には、大きく分けて「オープンキャンペーン」と「クローズドキャンペーン」があります。
- オープンキャンペーン:誰でも応募できる
- クローズドキャンペーン:特定の条件を満たした人のみが応募対象
|
クローズドキャンペーンの条件には、商品購入のほか、会員登録やメルマガ受信などがあり、購買行動を促進したい場面で活用されやすい手法です。
なかでもマストバイキャンペーンは、確実に購入というアクションが発生するため、販促施策との相性が非常に良好です。
また、クローズドキャンペーンは景品表示法の対象となるため、景品額には上限がある点にも注意が必要です。効果的な運用には、法律面への配慮と目的に沿った設計が欠かせません。
マストバイキャンペーンが注目されている理由
マストバイキャンペーンは、販促施策として再注目されている手法の一つです。
背景には、消費者の節約志向や購買動機の鈍化といった市場環境の変化があります。ただ商品を紹介するだけでは購買につながりにくい今、「買えば当たる」という直接的な動機づけは有効です。
さらに、SNSの活用によって、応募や当選報告の投稿が拡散されやすくなり、話題化を狙った設計も可能です。
実際、SNS連動型のマストバイキャンペーンを導入する企業は年々増えており、レシート応募やLINE連携による参加形式も一般化しています。
購買行動と拡散性を同時に促せる点から、認知拡大と売上向上の両方を狙える施策として注目が高まっています。
マストバイキャンペーンを行う目的・メリット
マストバイキャンペーンは、商品・サービスの購入が必須条件となっており、おもに商品購入の促進が目的です。主に、以下のようなメリットがあります。
- 売上アップや集客につながる
- 自社商品やブランドの認知度が向上する
- 既存顧客のリピート率が高まる
- 小売店・流通の売上に貢献できる
ここでは、それぞれのメリットについて解説します。
売上アップや集客につながる
マストバイキャンペーンを実施することで、消費者のアクションを促せるため、売上アップや新規顧客の獲得につながるのがメリットです。
「限定性」をアピールすることで、一時的な売上アップを実現できるうえに、認知度向上やリピート購買によってLTVが向上する効果も見込めるでしょう。
新商品や期間限定商品の発売や、低迷している商品の打開策として活用するのも有効です。
キャンペーンによって購買意欲を高めることで、キャンペーンをきっかけに初めて店舗に訪れたり、商品を手に取ってもらえる可能性が高まるでしょう。
自社商品やブランドの認知度が向上する
マストバイキャンペーンを行うことで、自社商品やブランドの認知度向上が図れるという点もメリットです。
キャンペーンが拡散されると、より多くのユーザーが自社商品を目にする機会が増えるため、宣伝やプロモーションにも効果的と言えるでしょう。
魅力的なマストバイキャンペーンを実施すれば、競合商品より選ばれやすくなります。キャンペーンをきっかけに自社商品を知り、商品やサービスに価値を感じてもらえれば、ポジティブな印象とともに認知度が向上します。
既存顧客のリピート率が高まる
マストバイキャンペーンは、新規顧客だけでなく既存顧客のリピート率向上にも役立ちます。特典や割引を提供することで、既存顧客のリピート購買を促すことができます。
企業に対するロイヤリティが高まりやすく、長期的な関係性構築につながるという点もメリットです。
マストバイキャンペーンによって、よりお得に商品やサービスを利用できるようになれば、既存顧客の満足度向上につながります。
そして、既存顧客の満足度が向上すれば、口コミや紹介を通じて新規顧客を獲得するきっかけにもなるでしょう。
小売店・流通の売上に貢献できる
マストバイキャンペーンは、ECサイトやネットショップで購入して得た購買証明を用いるタイプもあります。
しかし大半は、コンビニやスーパー、ドラッグストアなど流通・小売店などの実店舗で購入した際のレシートを用いるのが一般的です。
そのため、マストバイキャンペーンの実施によって、メーカーだけでなく商品を販売する流通・小売店の売り上げにもつながるというメリットがあります。
店舗の来店促進や客単価の向上に貢献できるので、流通担当者にとっての評価も高まるでしょう。
マストバイキャンペーンを実施する際に注意すべき法律|景品表示法の基本ルール
マストバイキャンペーンを実施する際は、景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)のルールを守る必要があります。
景品表示法では、懸賞による景品提供を「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」の3種類に分類し、それぞれで提供できる景品の金額上限が定められています。
マストバイキャンペーンは、基本的に「一般懸賞」または「共同懸賞」に該当します。
たとえば、自社単独で実施する場合は一般懸賞となり、商品の販売価格に応じて「景品の上限額」が決まります。
一方で、複数の企業が共同で実施する場合は「共同懸賞」となり、上限は30万円まで引き上げられます。
違反すると行政指導の対象となる可能性があるため、事前にルールを確認し、取引額と景品額のバランスに注意して設計することが大切です。
マストバイキャンペーンの種類【応募方法】
マストバイキャンペーンの応募方法は、下記の3種類に分かれます。
近年は、SNS応募、Web応募、はがき応募を組み合わせたマストバイキャンペーンを実施する企業も多く、幅広いターゲット層にリーチすることができます。
SNSで応募
TwitterやLINEなどのSNSを活用して応募を受け付ける方法です。
SNS上での応募は、特に若年層やデジタルネイティブなユーザーに向けて効果的です。
SNSのフォローや友だち追加を条件とすることで、自社のファン育成・獲得や、新規顧客の開拓などにつなげやすいメリットがあります。
Webで応募
企業のWebサイトや特設ページを活用して、応募を受け付けます。
Web応募はインターネットを利用した一般的な方法であり、スマホとPCの両方に対応できるため、気軽に応募できるメリットがあります。
はがき応募
従来型の応募方法で、はがき(郵便葉書)を使って応募を受け付けます。
WebやSNS応募に馴染みがない50~60代などの層をターゲットにする場合に有効な方法です。
従来の手書きの応募に慣れている方々にとっては、手間を感じることなく参加できる手段であるためです。
マストバイキャンペーンの購入証明の種類

マストバイキャンペーンでは、商品やサービスを購入した証明を必須としているのが一般的です。
ここでは、購入証明の種類について紹介します。
レシート本体
商品を購入した際のレシートをハガキに貼付したり、レシートの写真を撮影して登録したりする購入証明の方法です。
| メリット |
- 応募シールを作成したり集計する手間がかからない
- レシートによって購入店舗を特定できるため、流通タイアップで活用しやすい
- OCR機能を利用すれば集計・確認を自動化できる
|
| デメリット |
- 商品自体に応募シールが付くわけではないので、店頭でのキャンペーン認知につながりにくい
|
レシートに印刷されたQRコードやシリアルナンバーを使って、Web上で登録する方法もあります。
応募シールを作る必要がなく、購入した店舗を特定できるため、店舗限定のキャンペーンで利用しやすいことがメリットです。
■関連記事
レシートキャンペーンとは?成功事例10選やキャンペーンシステムも紹介
商品パッケージの切り抜き
バーコードやマークなど、商品パッケージの一部を切り抜き、ハガキなどに貼って応募する方法です。
| メリット |
- 応募シールを作る手間やコストを抑えられる
- 定番のキャンペーンでは、期間外にも商品を購入してマークを貯めてキャンペーンに備える人もいる(長期のリピート購買につながる)
|
| デメリット |
- POP・シール・パッケージなど店頭での告知が必須
- 現物が必要になるのでWeb応募には不向き
- 切り取るのに適さないパッケージでは使えない
|
キャンペーンのために改めて応募用のシールなどを作る必要がなく、コストが抑えられるメリットがあります。
また実施期間以外に商品を購入し、バーコードやマークを貯めて、次のキャンペーン開始に備えるといった行動も見られ、長期のリピーター獲得にもつながります。
商品貼付シール
商品に貼り付けられたシールを、ハガキなどに貼って購入証明とする方法です。
| メリット |
- 店頭で商品を並べたときにシールがアイキャッチになるため、キャンペーンを認知してもらうきっかけとなる
- 通年同じシールを貼っている場合は、長期のリピート購買につながる
|
| デメリット |
- シールの制作や貼付けにコストがかかる
- シールを貼り付けて応募する場合は、Web応募には不向き
|
キャンペーン専用のシールを作るケースや、期間に関わらず同じデザインのシールを活用するケースがあります。
シール自体がキャンペーン実施のアイキャッチとなり、キャンペーンを知ってもらうきっかけになる点がメリットです。
また商品パッケージの切り抜き同様、長期のリピーター獲得にもつながります。
商品貼付コード(QRコード)
商品にシリアルナンバーやQRコードを印刷したシールを貼付して、Web上で読み取ってもらうことで購入証明とする方法です。
| メリット |
- Web上でポイントを加算する「マイレージ型」キャンペーンを利用できる
- その場で即時抽選が行われる「インスタントウィン」も実施可能
- その場で当たる景品として、デジタルギフトを提供できる
|
| デメリット |
- シリアルナンバーやQRコードを封入する際の制作コストがかかる
|
応募した時点で抽選が実施され、その場で当選結果がわかる「インスタントウィン」キャンペーンが実施できます。
またポイントを加算していく「マイレージ型」のキャンペーンを実施することも可能です。
■関連記事
マイレージキャンペーンとは?メリットや成功事例、ツールも解説
シリアルナンバー
商品パッケージや貼付シール、レシートなどにシリアルナンバーを印字し、専用サイトやSNSからシリアルナンバーを入力して参加してもらう方法もあります。
|
メリット
|
- Web上でポイントを加算する「マイレージ型」キャンペーンを利用できる
- その場で即時抽選が行われる「インスタントウィン」も実施可能
- その場で当たる景品として、デジタルギフトを提供できる
|
|
デメリット
|
- パッケージレイアウトの変更や貼付けにコストがかかる
- シリアルナンバー封入する際の制作コストがかかる
|
QRコードと同様に、基本的にWebからの応募になるので、ユーザーの参加を促しやすいのがメリットです。
ただし、パッケージレイアウトの変更やシール作成、貼付コスト、実施の準備に時間がかかるという懸念点も考えられるでしょう。
応募するとその場で抽選が行われ、すぐに当選結果が分かるインスタントウィンキャンペーンと組み合わせやすいのも特徴です。
また、ポイントを加算して応募する「マイレージ型」キャンペーンも実施しやすいでしょう。
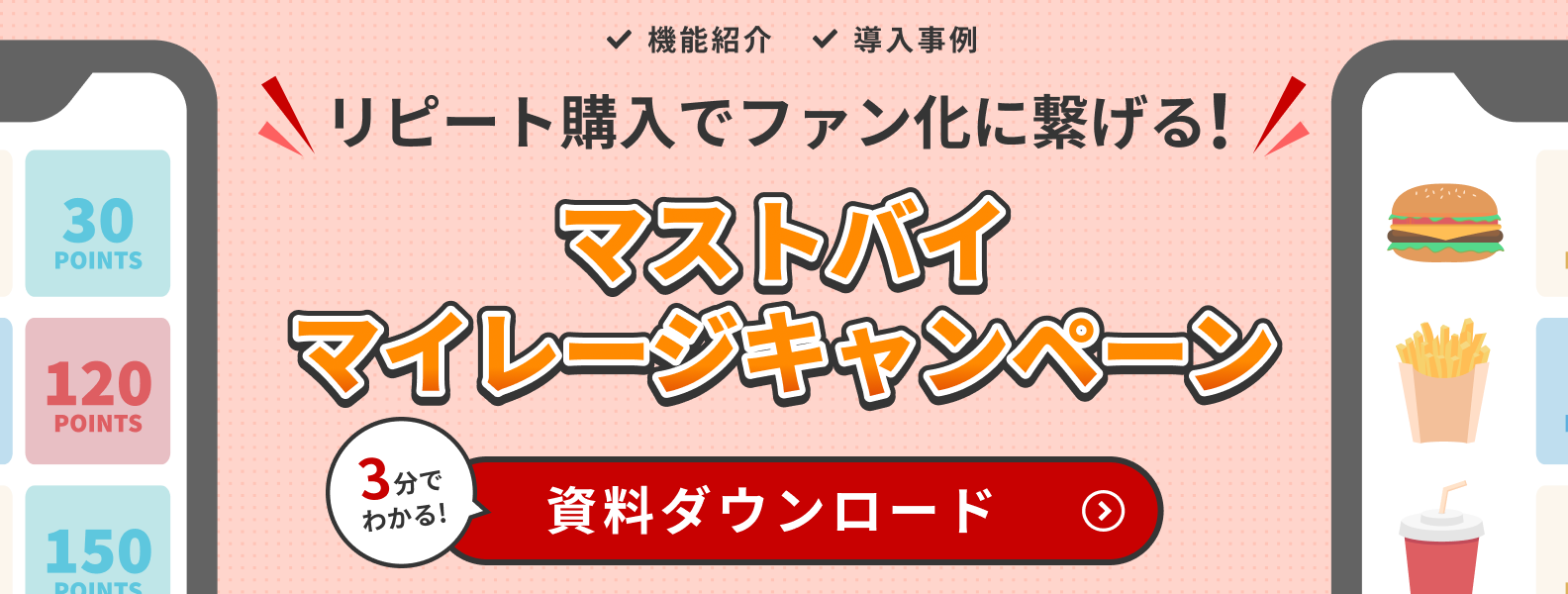
マストバイキャンペーンを実施する上での課題
マストバイキャンペーンにはさまざまなメリットがあるものの、課題やデメリットを把握したうえで実施しないと失敗に終わるリスクも考えられます。
マストバイキャンペーンを実施する上で懸念すべき課題には、以下が挙げられます。
- 応募に手間がかかる
- 参加者が偏るケースがある
- ハガキの場合は効果測定が難しい
ここでは、それぞれの課題について解説します。
応募に手間がかかる
マストバイキャンペーンは、応募者が商品を購入したうえで、レシートやシリアルナンバー、応募シールなどを使って応募する必要があります。
レシートやシールなどを保管して必要情報を入力して応募する工程が生じるため、消費者にとって応募のハードルが高くなってしまいます。
また、応募手順が複雑であると、途中で応募を辞めてしまうケースも感がられるでしょう。
そのため、マストバイキャンペーンを実施するときは、できる限り応募プロセスを簡略化することが大切です。
たとえば、スマートフォンで気軽に応募できるようにしたり、アプリやSNSを活用してスムーズに応募できるようにすることで、応募者の負担を大幅に軽減できるでしょう。
参加者が偏るケースがある
マストバイキャンペーンは、特定の商品を購入することが条件になります。
そのため、商品に興味がある人や日常的に購入している人など、特定の層のみに参加者が偏ってしまう傾向があります。
キャンペーンの参加者層が狭くなると、新規顧客の獲得が難しくなったり、広範囲へ」リーチを広げるのが難しくなるでしょう。
そのため、商品の購入条件を緩和したり、商品のラインナップを幅広くしたりすることで、より多くの人が参加しやすくなるように工夫するのがおすすめです。
また、新規顧客や新たなターゲット層の興味を引くために、商品そのものに加えて、目を引く豪華な景品や特典を用意するのもよいでしょう。
ハガキの場合は効果測定が難しい
ハガキ応募形式のキャンペーンは、デジタルな手段を使った応募方法に比べて、応募者のデータ収集や分析が難しくなってしまいます。
ハガキ応募の場合は手作業での処理が必要になるので、応募者の属性や行動パターン、買い物の傾向などを詳細に把握するのが困難です。
そのため、キャンペーンの効果やROI、マーケティング戦略に役立つ情報を正確に測定しづらいといえるでしょう。
マストバイキャンペーンを実施するときは、WebサイトやSNS、専用アプリを通じて応募できるキャンペーンシステムを活用するのが効果的です。
キャンペーンシステムを使うことでデータの収集・分析がおこないやすく、より正確な効果測定が可能になるでしょう。
マストバイキャンペーンで応募率を高めるコツ10選

マストバイキャンペーンは購入促進に効果的な施策のひとつです。
しかし、昨今では数多くのキャンペーンが実施されているため、ただ実施するだけでは成功に辿り着きにくいでしょう。
- ターゲットを理解する
- SNSを活用して話題化する
- 懸賞品をトレンドに合わせる
- 複数の懸賞品を設定し収集してもらう
- インスタントウィン型(当たり外れ)にする
- ダブルチャンス形式型にする
- 応募しやすい方法を選ぶ
- マイレージ形式にする
ここでは、キャンペーンの応募率を高める方法について解説します。
1. ターゲットを理解する
マストバイキャンペーンを成功させるためには、自社のターゲット層を理解することが重要です。
自社商品・サービスのターゲット層を理解し、ニーズにもとづいた情報発信や訴求を行いましょう。また、ターゲットに効果的にリーチするためのSNSを選定することも大切です。
キャンペーンをより多くの人に参加してもらうことにつながります。
なお、顧客自身が気付いていないような本音や動機である「インサイト」を捉えることで、商品開発やマーケティングに活かすことができます。
インサイトについては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
■関連記事
インサイトとは?ニーズとの違いや分析方法・事例も紹介
2. SNSを活用して話題化する
SNSを活用して、キャンペーン情報を拡散させて話題化させることは、キャンペーン実施において重要なポイントです。
広告に比べて、より多くのユーザーをキャンペーンに誘導できるため、応募数の向上につながりやすくなります。
キャンペーン期間中に拡散してもらいやすいよう、写真や情報を拡散してもらいやすい仕組みを作りましょう。
3. 懸賞品をトレンドに合わせる
マストバイキャンペーンでは、懸賞品選びも重要です。
担当者の好みに偏らず、ターゲットのニーズに寄り添えているか・トレンドを押さえられているかなど、懸賞品の分析も行いながら選定しましょう。
またデジタルインセンティブを懸賞品とすることで、配送や受け取り、再配達の手間を感じることなく、当選の喜びを味わってもらえます。
4. 複数の懸賞品を設定し収集してもらう
複数の商品を懸賞品として設定することで、商品を収集してもらう方法です。
マイレージ型のマストバイキャンペーンで多く用いられており、リピーター獲得につながりやすいメリットがあります。
同時期にキャンペーンを実施する場合は、景品の上限額について十分注意しましょう。
5. インスタントウィン型(当たり外れ)にする
抽選結果がすぐにわかるインスタントウィン型にすることで、ユーザーの参加意欲を向上させるのも効果的です。
インスタントウィン型は、キャンペーンに応募した時点で抽選が実施され、その場ですぐに当選結果がわかるシステムです。
演出を工夫することで、当たり外れに関わらずユーザーにとって再び応募したくなるような楽しみ方ができるでしょう。
6. ダブルチャンス型にする
一度外れても当選する機会を残しておく、「ダブルチャンス型」のキャンペーンも効果的です。
ダブルチャンス型にすることで、一度外れた方でもモチベーションが下がりづらく、何度でも参加してもらいやすいメリットがあります。
7. 応募しやすい方法を選ぶ
マストバイキャンペーンでは、ユーザーが応募しやすい方法にすることも重要です。
ただし、応募しやすい方法と言っても、年齢や性別、趣味嗜好などのターゲット属性によって異なるため、親和性の高い応募方法を選ぶ必要があります。
たとえば、10~20代のZ世代を中心としたターゲット層の場合は、WebサイトやSNSから応募できる形がおすすめです。
反対に、50~60代以降のユーザーをターゲットにする場合は、昔から馴染みのあるハガキ応募にも対応するといいでしょう。
もちろん応募方法は1つに絞る必要はなく、WebやSNS、はがきなど複数の応募方法を組み合わせることで、幅広いユーザー層からの応募が期待できます。
8. マイレージ形式にする
マイレージ形式のキャンペーンは、対象商品・サービスを購入するとポイントが貯まり、貯まったポイントに応じて抽選に応募するキャンペーンです。
購入するごとにポイントが加算されるので、リピーター獲得や複数回の来店・購買促進、エンゲージメント向上などのメリットがあります。
主に既存顧客を対象に実施するため成果が出やすく、費用対効果が高いこともマイレージ型キャンペーンの特徴です。
9. 購入前から気になる仕掛けを用意する
マストバイキャンペーンの応募率を高めるには、購入前からユーザーの関心を引きつけることが重要です。
購入を検討する段階でワクワク感を生み出せれば、参加意欲も高まりやすくなるでしょう。
たとえば、以下のような仕掛けが効果的です。
- SNSでのカウントダウン投稿
- 景品の一部を先行公開
- インフルエンサーによる事前レビュー
- 特設ページの先出し公開
発売前から期待感を高めておくことで、開始直後に一気に購入・応募へとつながりやすくなるでしょう。
キャンペーンが話題になりやすく、レシート投稿数やSNSシェア数の伸びにも直結します。
10. ユーザー生成コンテンツ(UGC)を活用する
ユーザーによるSNS投稿やレビューといったUGC(ユーザー生成コンテンツ)を活用することで、キャンペーンの応募を自然な形で後押しできます。
企業発信では届きにくいリアルな感想が共感や信頼を生み、キャンペーンの魅力を自然に伝える役割を果たします。
たとえば、以下のようなハッシュタグを設けることで、より関心を持ってもらいやすくなるでしょう。
- 「#〇〇を買ってみた」
- 「#〇〇キャンペーンに参加」
さらに、投稿者限定の抽選を別途用意することで、「投稿するともう一度当たるチャンスがある」という動機づけにもなるでしょう。
売上アップやリピーター獲得につながる「マイレージマストバイキャンペーン」については、以下の資料で詳しく解説しています。
無料でダウンロードいただけるので、SNS担当者様や広告代理店様は、ぜひ資料をご活用ください。
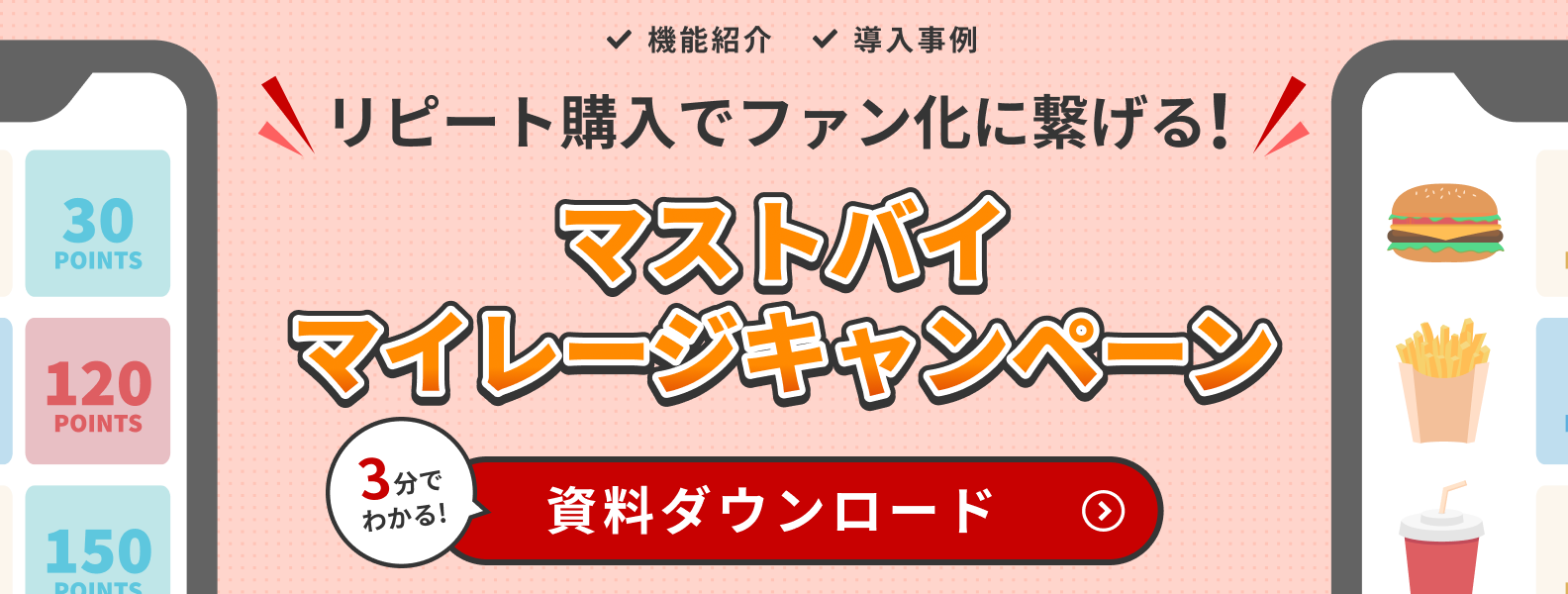
マストバイキャンペーンの成果を測る評価軸
マストバイキャンペーンの成果を測るには、以下の観点で評価しましょう。
- キャンペーン期間中の売上
- キャンペーンの応募者数
- SNSやメディアでの話題性
- 流通側からの反応
- LTV(顧客生涯価値)への影響
ここでは、それぞれの評価軸について解説します。
キャンペーン期間中の売上
マストバイキャンペーンの大きな目的としては、商品の売上増加が挙げられます。キャンペーン期間中の売上は非常に重要な評価軸です。
キャンペーン期間前の売上と比較し、売上がどれくらい伸びたかをチェックしましょう。
商品によっては、時期や季節的な要素も影響するので、こうした外的要因も合わせて見定めることが大切です。
ここでは、売上額ではなく「1店舗あたりの販売個数」を見るようにしましょう。
キャンペーンの応募者数
キャンペーンが成功したかを測る一つの指標として、応募者数の多さも重要です。
目標としていた応募者数に対してどれくらいの応募が集まったか、毎年実施しているのであれば前年比はどうだったかなどを分析しましょう。
また、景品ごとの人気・不人気や、応募数が伸び始める時期など、あらゆる視点で応募数を分析すれば、応募者数の変動の要因を探ることができます。
期待していた応募者数に達しなかった場合は、キャンペーンの企画や設計、広告、告知方法に改善の余地があると言えるでしょう。
SNSやメディアでの話題性
インターネットが普及した現代では、WebメディアやSNSでの話題性を数値化して測ることも重要視されています。
SNSでは、いいねやシェア数、ユーザーの口コミ(UGC)の数など、さまざまな要素を分析しましょう。
また、写真やコメントなど数値化できない定性データもまとめることで、新たな気付きのきっかけになることもあります。
また、ニュースサイトなど主要なメディアで取り上げれらた数も気にしておくのがおすすめです。
流通側からの反応
キャンペーンを実施するとなると、商品を購入する消費者のことばかりを気にしがちですが、流通・小売店からの評判も無視できないポイントです。
流通でキャンペーンを実施してもらうことは、期間中に該当商品を店頭に採用してもらえるうえに、需要を見込んで発注を増やしてもらえる可能性が高いと言えます。
反対に、流通においては、売場を確保したにもかかわらず売上が伸びなければ、対象商品の売場を確保するのがリスクとなってしまうでしょう。
キャンペーンの評判をもとに、次回の商談を円滑に進めたり、キャンペーン施策につなげたりと、キャンペーン後の成功を左右すると言えます。
LTV(顧客生涯価値)への影響
マストバイキャンペーンは、一時的な売上だけでなく、LTV(顧客生涯価値)への影響も評価対象に含めるべきです。初回購入で終わらず、継続的な接点を生む設計ができているかを確認しましょう。
たとえば、以下のような指標がLTV評価の目安になります。
- キャンペーン後3か月以内のリピート率
- LINEやメルマガ登録数の増加
- SNSフォロー後の投稿反応数や閲覧数
マイレージ形式や連動企画で接点を継続させる工夫があれば、ユーザーがブランドに留まりやすくなります。単発で終わらない設計をすることで、LTVの向上と次回施策の成果にもつながるでしょう。
SNSにおけるマストバイキャンペーンの成功事例6選
ここからは、マストバイキャンペーンの事例について解説します。
1. 新潟茶豆|たくさん食べてごちそうを当てようキャンペーン

参照:OWNLY導入事例
JA全農にいがた/にいがた園芸農産物宣伝会では、新潟茶豆のPRを目的に「新潟茶豆 たくさん食べてごちそうをあてよう!キャンペーン」を実施。
対象商品を購入したレシートを撮影し、メールアドレスまたはLINEでエントリーすると応募できるというもの。また、はがき応募にも対応することで、幅広い層からの応募を狙いました。
レシート応募によって購買を促し、豪華賞品をプレゼントにすることで新潟茶豆の認知拡大にもつながっています。
|
応募条件
|
対象商品を購入&LINEでエントリー
|
|
ポイント
|
- 対象商品の購入によって購買促進が期待できる
- はがき応募に対応することで幅広い層からの応募を狙える
|
2. グランツリー武蔵小杉|LINEレシートキャンペーン

引用元:OWNLY導入事例
グランツリー武蔵小杉のLINE友だち登録キャンペーンです。LINE友だち・新規友だち限定で抽選で100名に商品券がプレゼントされるという内容です。
応募期間中に対象店舗で3,000円以上のレシートを撮影し、トーク画面のメニューから「お応募する」ボタンを押して、レシート写真を送信すると応募できます。
LINEの友だちであればレシート1枚につき1回参加できるため、友だち登録数増加にくわえて商品の販売促進につながる点が大きなメリットです。
|
応募条件
|
LINE友だち登録&レシート応募
|
|
ポイント
|
- 施設への来店促進や売上アップにつながる
- レシート1枚につき1回参加できるため、何度でも参加してもらえる
|
3. 株式会社トライフォース|レシート応募キャンペーン
株式会社トライフォースが展開する「ハマボールイアス」では、年末のホリデーシーズンに合わせて、レシート応募キャンペーンを実施しました。
キャンペーン特設サイトからLINE公式アカウントに友だち追加し、対象商品を購入したレシートでキャンペーンに応募できます。

参照:ハマボールイアス HAPPY HOLIDAY レシート応募キャンペーン|OWNLY導入事例
案内メッセージに従ってLINEのトーク画面でレシート応募すると応募が完了し、後日当選者にトーク画面で通知されるというものです。
キャンペーンを通じて友だち数を増やすことで、店舗のお得なキャンペーン情報やクーポンなど、販促につながるコンテンツを継続的に配信しています。
4. 株式会社キリン|マイレージ型マストバイキャンペーン
株式会社キリンでは、購入ごとで発行したポイントで参加できる「OWNLYマイレージ型マストバイキャンペーン」を実施しました。
キャンペーン対象商品を購入すると、ポイントが付与され、貯めたポイントに応じてプレゼントを贈呈するキャンペーンです。
OWNLYでは、LINE・Twitter・Facebookアカウントで参加可能なため、参加ハードルが低く多くのユーザーに参加してもらうことができます。また、様々なインセンティブを用意し、ユーザーに希望コースを選んでもらうことが可能なので、ユーザーの参加意欲を高め、幅広い層の人に参加してもらえるでしょう。
参加方法も簡単で、レシートを撮影してアップロードすることで簡単に応募可能。加えて、期間内に複数回の購入が期待でき、長期リピーターの獲得やエンゲージメント向上を実現できます。
|
応募条件
|
対象商品を購入すると貯まるポイントで応募
|
|
ポイント
|
- 溜めたポイントに応じて応募できるマイレージ型によって複数回の購入やリピーター獲得が狙える
- 複数のコースを用意することで幅広い層に参加してもらえる
|
5. キリンビバレッジ株式会社|Summer Afternoon Teaキャンペーン

参照:Summer Afternoon Teaキャンペーン|OWNLY導入事例
キリンビバレッジ株式会社では、2024年7月9日~8月6日にかけて、ウエルシアグループとの共同企画として「Summer Afternoon Teaキャンペーン」を実施しました。
キャンペーン期間中にウエルシアグループの店舗にて購入した対象商品500円(税込)以上のレシートを1口として、キャンペーンサイトにアップロードすると応募できるというものです。
応募者のうち、抽選で500名にキャンペーン限定のオリジナルペアグラス、100名にデジタルギフト1,000円分が当たります。
キャンペーンを通じて同社商品を多くの人の手に取ってもらうきっかけとなり、新規顧客の獲得や既存顧客のファン化を促すことができます。
|
応募条件
|
対象店舗で購入したレシート500円以上を1口として応募
|
|
ポイント
|
- キャンペーン限定のオリジナルグッズを景品にすることで、既存顧客からの興味も引きやすい
- デジタルギフトの景品を用意すれば、幅広い層から応募してもらいやすくなる
- 小売店の集客や販売促進、売上アップにつながる
|
6. キリンビバレッジ株式会社首都圏統括本部|第2回 1都4県いろんないいねキャンペーンwith北陸

参照:第2回 1都4県いろんないいねキャンペーンwith北陸|OWNLY導入事例
キリンビバレッジ株式会社首都圏統括本部では、「第2回 1都4県いろんないいねキャンペーンwith北陸」としてレシートキャンペーンを実施しました。
キリンビバレッジ全商品が対象商品となっており、対象商品1本を必ず含む500円(税込)以上を購入したレシートで応募できるというものです。
賞品はそれぞれ、首都圏の1都4県ごとにコースが分かれており、各20名に豪華な景品が当たります。
キャンペーンを通じて首都圏の魅力を多くの人に知ってもらうきっかけを作ることができます。
|
応募条件
|
対象商品1本を必ず含む500円以上のお買い上げレシートをURL、もしくは店頭の専用応募はがきから応募する |
|
ポイント
|
- 合計6つのコースを用意することで、幅広い層の興味を引きやすく、多くの人に参加してもらいやすい
- 首都圏ごとのコースで各地の魅力を知ってもらえる
|
OWNLYのマストバイマイレージキャンペーンの事例や応募率を高める方法、販売促進に直結する施策を知りたい方は、以下の資料をぜひご覧ください。
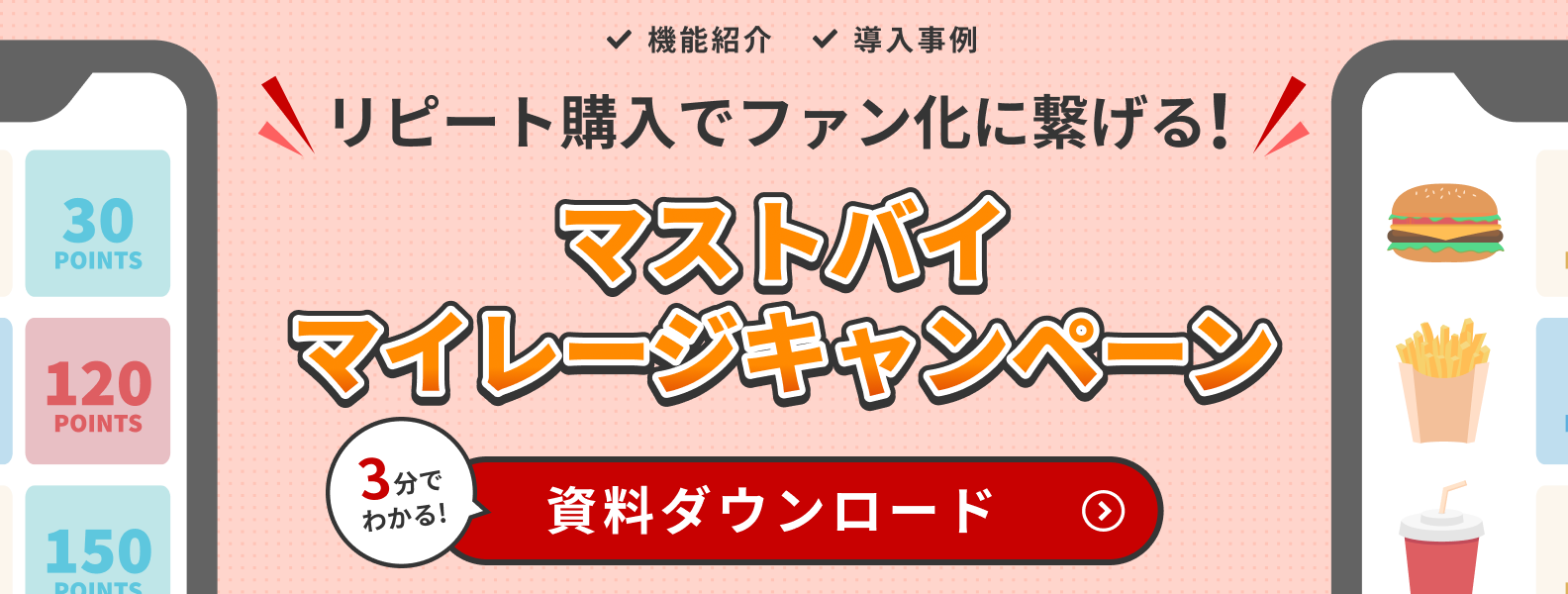
SNSでマストバイキャンペーンを実施する際の注意点
SNSでマストバイキャンペーンを実施する際には、以下の点に注意しましょう。
- ターゲットを理解する
- プライバシーや法規制を遵守する
- 効果検証や分析を徹底する
ここでは、それぞれの注意点について解説します。
1. 応募条件や当選基準を明記する
SNSでマストバイキャンペーンを実施する際は、応募条件や当選基準を明確に伝えることが欠かせません。
曖昧なまま進めると、参加者との認識にズレが生じ、トラブルや不信感につながります。
特に「何をしたら応募が完了するのか」「当選者はどう選ばれるのか」は、事前に丁寧に説明しておく必要があります。
たとえば、以下のような点は必ず明記しましょう。
- 応募に必要なアクション(購入+投稿など)
- ハッシュタグやメンションの指定
- 非公開アカウントは対象外であること
- 当選者の選定方法(抽選・先着など)
「フォロー&リポスト」などの簡単な形式でも、条件を明文化することで安心感が生まれ、結果的に応募数の増加にもつながります。
2. 過剰な演出や煽りによる誤認を避ける
SNSは拡散力が高いぶん、投稿内容の印象が与える影響も大きくなります。
マストバイキャンペーンを紹介する際に、過剰な演出や誤解を招く表現を使うと、景品表示法違反や炎上リスクにつながるおそれがあります。
たとえば、以下のような表現や演出は誤認を招くおそれがあります。
| 表現例 |
注意点 |
対応策 |
|
「全員当たる」
|
実際は抽選なのに断定表現を使っている
|
「抽選で○名様に」などと明記する
|
|
当選人数が書かれていない
|
応募者が当選条件を把握できない
|
人数や選定方法を記載する
|
|
景品写真だけを大きく掲載
|
実物と異なる印象を与える恐れがある
|
「写真はイメージ」と注記する
|
ユーザーに誤解を与えない表現を心がけることで、キャンペーンへの信頼感を高め、安心して参加してもらえる土台が生まれます。
3. プライバシーや法規制を遵守する
SNSでキャンペーンを実施する際は、プライバシー保護や法規制の遵守にも注意しましょう。
具体的には、個人情報の取り扱いに関する法律や、各SNSプラットフォームのガイドラインを厳守する必要があります。
キャンペーンの際は、ユーザーに個人情報を入力してもらうこともあるでしょう。そのため、ユーザーの同意なく個人情報を収集・使用しないように注意が必要です。
また、景品表示法や著作権法などの法律についても配慮し、法的リスクを避けるようにしましょう。ユーザーからの信頼性を維持するには欠かせません。
4. 応募期間や景品内容の変更は避ける
マストバイキャンペーンをSNSで実施する際は、応募期間や景品内容の変更は、できる限り避けるべきです。
SNSでは情報が瞬時に拡散されるため、一度広まった内容を途中で変更すると、参加者の混乱や不信感を招く可能性があります。
やむを得ず変更が必要になる場合は、事前に「内容は予告なく変更する場合があります」と記載しましょう。変更が決まった時点で速やかに各投稿・特設ページ・公式アカウントなどで周知を徹底することが重要です。
キャンペーン内容の安易な変更は、企業への信頼低下やSNS上での批判につながりかねません。設計段階で柔軟性を持たせつつ、変更を最小限にとどめることが大切です。
5. 炎上時の対応フローを事前に準備しておく
SNSキャンペーンには拡散力がある一方で、想定外の批判や誤解が一気に広がるリスクも伴います。
万が一に備えて、炎上時の対応フローを事前に準備しておくことは、企業リスク管理として欠かせません。
たとえば、以下をあらかじめ社内で共有しておくとスムーズに対処できます。
- 対応責任者の明確化
- 初動対応の手順書
- 発信停止や投稿削除の判断基準
また、問い合わせ窓口の整備や、想定Q&Aの用意も有効です。
炎上は情報発信そのもののミスだけでなく、対応の遅れや不誠実さによって深刻化することが多くあります。冷静かつ迅速に動ける体制を整えておくことで、ブランドイメージや信頼性の低下を最小限に抑えることができます。
6. 効果検証や分析を徹底する
キャンペーン実施後の効果検証と分析は、キャンペーンの施策改善に必要不可欠です。
まずは、キャンペーンの目標を明確に設定し、KPIやKGIを定めましょう。その上で、SNSのインサイトツールや外部の分析ツールを使用して、エンゲージメント率、リーチ数、コンバージョン率などのデータを収集します。
収集したデータをもとに、どの要素が成功要因となったのか、または改善が必要かを分析し、具体的な改善策を導き出しましょう。
定期的な効果検証とPDCAサイクルを回すことで、キャンペーンの精度と効果を向上させることができます。
マストバイキャンペーンを実施するならツールの利用が不可欠
マストバイキャンペーンを実施する際は、キャンペーンツールの利用が欠かせません。
キャンペーンツールを利用すれば、以下のような複雑な応募条件での設定も可能です。
- 対象商品を○○個以上のレシートで応募できる
- 対象商品からどれか1つを購入すると応募できる
- 対象商品を○○Payまたはクレジットカードで決済すると応募できる
|
キャンペーンツールを活用してWeb応募に対応すれば、レシートの検閲や当選通知もWeb上で簡単に行えるようになり、作業のコストを削減できます。
景品をデジタルギフトやクーポンに設定すれば、景品の準備や発送のコストも減らせるでしょう。
また、Web上に購入者のデータが蓄積されるので、いつどこで買われているか、何を一緒に買っているかが把握できます。
「どんなレシートキャンペーンツールを選べばよいか分からない」「マストバイキャンペーンに対応しているツールを知りたい」とお考えの方は、以下の記事もぜひチェックしてください。
■関連記事
【2024年最新】レシートキャンペーンツール13選|導入するメリットや選び方を解説
マストバイキャンペーンのツールを導入する際の比較ポイント
マストバイキャンペーンの各ツールは対応SNSや機能、サポート体制などに違いがあるため、目的に合ったサービスを選ぶことが大切です。
ここでは、ツール選定時に確認しておきたい5つのチェックポイントを紹介します。
- 対応できるキャンペーン形式に柔軟性があるか
- 応募データの収集・管理がスムーズに行えるか
- 応募ユーザーの体験がスムーズであるか
- サポート体制や導入スピードが適切か
- 景品表示法への対応機能が整っているか
自社の体制や実施したいキャンペーン形式に合わせて、最適なツールを見極める参考にしてください。
対応できるキャンペーン形式に柔軟性があるか
ツールによって、対応できるキャンペーン形式には大きな差があります。
たとえば、インスタントウィンやレシート応募、QRコード入力、LINE連携など、どの応募方法に対応しているかを事前に確認することが重要です。
マストバイキャンペーンをSNSと組み合わせて実施する企業も増えており、SNSアカウント認証やDM送信などの機能が備わっているかもポイントです。
自社の実施予定の形式に合ったツールであるかを必ずチェックしましょう。
応募データの収集・管理がスムーズに行えるか
キャンペーンの成果を可視化し、効果検証を行うには、応募データの収集・管理機能が不可欠です。
応募者情報の自動収集、抽選結果の管理、重複排除機能、当選通知の自動化などが備わっているかを確認しましょう。
また、CSV出力やダッシュボード表示など、データを扱いやすい形式で提供してくれるかも大きな比較ポイントです。
将来的にCRMや販促施策に活かせるよう、マーケティング活用の視点からもチェックすることが大切です。
応募ユーザーの体験がスムーズであるか
応募者が途中で離脱しないためには、ユーザー体験(UX)の良さも重視すべきポイントです。
応募フォームの入力が簡単か、ステップ数が最小限か、スマートフォンでもスムーズに操作できるかをチェックしましょう。
特にマストバイキャンペーンでは、レシート撮影や購入証明のアップロードが必要な場合もあるため、画像添付やQRコード入力のしやすさなど、実際の応募導線がストレスなく完了できる設計になっているかを見極めることが重要です。
サポート体制や導入スピードが適切であるか
初めてキャンペーンを実施する場合や、短期間で成果を出したい場合には、ツールのサポート体制や導入スピードも重要な判断基準です。
マニュアルの有無、問い合わせ窓口の対応状況、トラブル時の対応速度などを確認しておきましょう。
また、申し込みから利用開始までの期間がどれくらいかかるか、テンプレート活用やセットアップ代行の有無も、導入工数に大きく影響します。
社内リソースに応じて、どの程度のサポートが必要かを考えて選定することが大切です。
景品表示法への対応機能が整っているか
マストバイキャンペーンでは、景品表示法に基づく景品額の制限を守る必要があります。ツールによっては、あらかじめ法令対応済みの設計テンプレートが用意されていたり、条件に合致した景品設計のサポートを提供しているものもあります。
また、当選率の設計や抽選方法において不正が起きにくい仕組みになっているかどうかも重要です。
法的リスクを回避し、安心して運用できる体制が整っているかを判断材料の一つとしておくとよいでしょう。
マストバイキャンペーンを実施するならOWNLYの利用がおすすめ

(詳しくはこちら)
OWNLYは、SNSマーケティングを一元管理できるサブスクリプション型のマーケティングプラットフォームです。
さまざまなSNSマーケティングに対応しており、ツール提供だけでなく、施策の企画から広告運用まで幅広くサポートします。Twitter・LINE・Instagramなど、さまざまなSNSマーケティング手法に対応。
インスタントウィン、レシート応募、フォトコンテストなど15種類以上のキャンペーンタイプを無制限で利用でき、UGC収集から活用まで1つのツールで実現可能です。
通算700ブランド以上の導入実績があり、フォロワー獲得・認知拡大・販売促進・店舗集客・EC売上向上を目指せます。
Ownlyの詳しいサービス概要は以下の資料から確認いただけます。お気軽にダウンロードください。