近年、IT業界で注目を集めているのが「スーパーアプリ」。生活に役立つ多種多様なサービス機能が集約された統合アプリの総称です。
「スーパーアプリとはどんなもの?」「スーパーアプリが注目されている背景とは?」などの疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
本記事では、スーパーアプリとは何かについてや、注目されている理由、世界・日本におけるスーパーアプリの例などを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
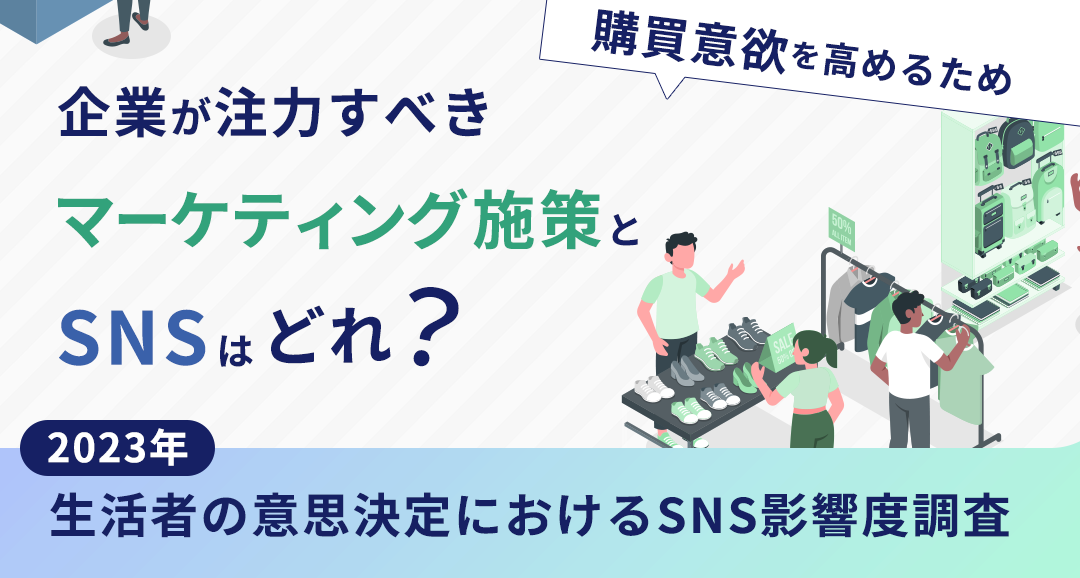
スーパーアプリとは
スーパーアプリとは、複数の機能やサービスを統合したアプリのことです。
メッセージや電子決済、ショッピング、フードデリバリー、タクシー配車、ニュース、音楽、ゲームなど、あらゆるサービスを一つのアプリで完結できます。
従来は、それぞれのサービスごとにアプリをインストールする必要がありましたが、スーパーアプリなら手間が省け、シームレスな操作が可能です。
まるで、一つのアプリで生活を完結できるようなイメージです。
こうした利便性から、中国や東南アジアではすでに広く普及しており、日本でも今後大きな注目を集めていくと予想されています。
ミニアプリとの違い
ミニアプリは、スーパーアプリ内で動作する軽量なアプリです。
スーパーアプリ自体がさまざまなサービスを提供するのではなく、スーパーアプリをプラットフォームとしてミニアプリが動作しています。
たとえば、スーパーアプリはデパート、ミニアプリはデパートの中のテナントのような関係です。デパートではさまざまな商品を購入できますが、テナントでは限られた商品しか購入できません。
ネイティブアプリとの違い
ネイティブアプリは、特定のOS向けに開発された個別のアプリです。
iOSやAndroidで別々に開発されているため、アプリストアからダウンロードしてインストールする必要があります。
スーパーアプリは、ネイティブアプリのようにダウンロードの手間や一度に複数のアプリを立ち上げる必要がないという点も違いです。
スーパーアプリが注目されている理由
スーパーアプリは、複数のアプリをインストールして切り替えたり、会員登録したりする必要がなく、ユーザー体験がよりスムーズになります。
通常のネイティブアプリを利用する際は、新しくダウンロードする度にIDやパスワードを作る必要があり、容量によってダウンロードできないことも。
スーパーアプリはさまざまな機能が備わっているので、ユーザーにとって利便性が高く、一度インストールされるとアンインストールされにくい傾向にあります。
そのため、企業にとっては、ユーザーを長期的に囲い込めるというメリットもあり、企業はさまざまなサービスを提案しやすく収益化の機会が多くなります。
世界各国のスーパーアプリの例
ここからは、世界各国にどのようなスーパーアプリが存在するのかについていくつかの例を紹介します。
WeChat|中国

参照:WeChat
WeChat(ウィーチャット)は、中国で最も普及しているスーパーアプリです。
ミニアプリとしてチャットはもちろん、ショッピングやチケットの予約、フードデリバリー、タクシー配車、ゲームなど、さまざまな機能が統合されています。
感染症の拡大によって、WeChat上で感染状況をリアルタイムで確認できるサービスや、健康状態を確認するサービスとしても活用されています。
中国では、生活インフラの一部として欠かせない存在です。
AliPay|中国

参照:AliPay
AliPay(アリペイ)は、中国の阿里巴巴集団(アリババグループ)が提供する東南アジア最大級のスマホ向けキャッシュレス決済サービスです。
決済機能に特化しており、中国国内では9億人以上のユーザーが利用しています。QRコード決済が盛んな中国において、Alipayはなくてはならない存在です。
WeChat同様にスーパーアプリ化が進んでおり、現在はタクシー配車や資産運用、医療関連、信用スコア診断などさまざまなミニアプリが統合されました。
Gojek|インドネシア

参照:Gojek
Gojekは、インドネシア初のオンラインタクシー・配車を行うアプリです。
当初は配車サービスから始まり、映画のチケット購入、ハウスキーパーの手配、食事のデリバリーなどのミニアプリを統合しています。
大型店舗だけでなく、個人経営の小さな店舗でも決済方法として採用することが増えています。
Grab|マレーシア

参照:Grab
Grabは、2012年にマレーシアで誕生したスーパーアプリです。
東南アジアでは最大級の配車サービスを中心としており、設立後は本社をシンガポールに移し、約330の都市圏に展開するまでに成長しました。
車の手配や運転手のコミュニケーション、料金支払いなどをアプリで完結でき、決済やローン、自動車保険等の各種サービスも提供されています。
日本国内のスーパーアプリ候補
日本国内においても、スーパーアプリ化しつつあるアプリがいくつかあります。
- LINE
- PayPay
- Yahoo!Japan
- X(旧Twitter)
それぞれのアプリについて見ていきましょう。
LINE

参照:LINE
LINE株式会社が運営するLINEは、日本を中心にアジア圏で利用されており、とくに国内ではコミュニケーションツールとして年代問わず利用されているアプリです。
LINEのユーザー数は月間9,700万人(2024年3月末時点)に上ります。
■基本情報
- 提供開始日:2011年6月
- アクティブユーザー数:1,9億人
- 主要国:日本、台湾、インドネシア、タイ
- 提供サービス:メッセージ/決済/ニュース・音楽・マンガ配信・ゲーム配信/ブログ/金融サービス/広告配信/リサーチ
|
LINEはチャットや音声・ビデオ通話などの機能だけでなく、決済や音楽、ニュース、マンガといったエンタメコンテンツなど幅広いサービスを提供しています。
また、LINEは公式アカウントの運営も可能で、友だちになったユーザーに対してチャットボットやメッセージを配信して販促を行うことも可能です。
■関連記事
LINE公式アカウントの面白い事例8選|便利な機能や運用のコツも紹介
PayPay

参照:PayPay
ヤフー株式会社とソフトバンク株式会社が共同設立した「PayPay」株式会社が運営するPayPayは、キャッシュレス(QRコード決済)サービスです。
サービス開始以降は、ユーザー数を急激に増やしており、現在は国内最大級のQRコード決済サービスにまで成長しています。
■基本情報
- 提供開始日:2018年10月
- アクティブユーザー数:6,000万人
- 主要国:日本
- 提供サービス:決済/EC/金融サービス
|
PayPayモールやPayPayフリマ、PayPay証券などのサービスを展開しており、ユーザーを獲得しています。
また、タクシー配車サービス「DiDi」との連携や、PayPay請求書払いに対応した振込票の拡大、飲食店における事前注文サービスの提供なども行われています。
スーパーアプリの課題
スーパーアプリにはさまざまなメリットがありますが、運営側とユーザー側の双方にも課題がいくつか存在します。
運用側の課題
スーパーアプリは、競合との差別化が激しいという課題があります。
市場を独占すると大きな利益が期待できますが、予算さえ確保すれば真似できるビジネスモデルなので、差別化が難しいとも言えます。
とはいえ、自社で提供できるサービスが多くあることが前提となるため、ビジネスが多角化されていない状況では参入が難しいでしょう。
また、決済情報やメッセージ機能などあらゆる情報を扱うので、セキュリティやプライバシーへの配慮も必要です。
現在は、広告のために個人情報を収集・利用されることに対して嫌悪感を持つユーザーも多く、セキュリティやプライバシー対応に必要なリソースも大きいと言えます。
ユーザー側の課題
ユーザー側の課題としては、1つのアプリで囲い込みが起こる「アプリロックイン」が生じる可能性がある点です。
すべてのサービスが使いやすく良質であれば問題ないかもしれませんが、他にサービスの選択肢がない場合にも使い続けなければなりません。
また、スーパーアプリは多数の機能やミニアプリなどを集約しているので、機能性を追求するあまり、操作性が悪くなってしまうことも。
とくにスマホ端末の場合は、機能性や操作性の両立が難しいので、バランスを考慮したうえでUI・UXを設計する必要があります。
X(旧:Twitter)もスーパーアプリ化を狙っている?
2022年10月に、イーロンマスクは総額6兆4,000億円で米Twitterを買収しました。その後は色々な仕様を変更し、名前をTwitterから「X」に変更するなどの改革に取り組んでいます。
現在X(Twitter)は世界で5億5,000万人を超えており、ソースコードの一部公開や広告費を支払う仕組みを構築したりと、利用者を増やす試みが行われました。
イーロンマスクは、世界的な決済サービスPayPalのCEOであったことから、決済サービスの実装はそう遠くない未来かもしれません。
Xには多くのユーザーがおり、DM機能なども備わっているため、決済機能を搭載することでXをスーパーアプリにすることを目論んでいます。
■関連記事
Twitterが「X」に変更!ブランド変更の理由や企業への影響も解説
まとめ
国内外においてスーパーアプリの需要は今後も高まることが予想されており、多くの企業が注目しています。
日本でスーパーアプリは流行らないといわれることもありますが、LINEやPayPay、Yahoo!Japanなどのスーパーアプリ候補が出てきています。
ユーザーの囲い込みを実現しやすく、いかに利用者を集めてサービスを普及させるかが重要です。
スーパーアプリとSNSを連携させてそれぞれの利便性を掛け合わせることで、ユーザーはより便利で快適な体験を味わえるようになります。
