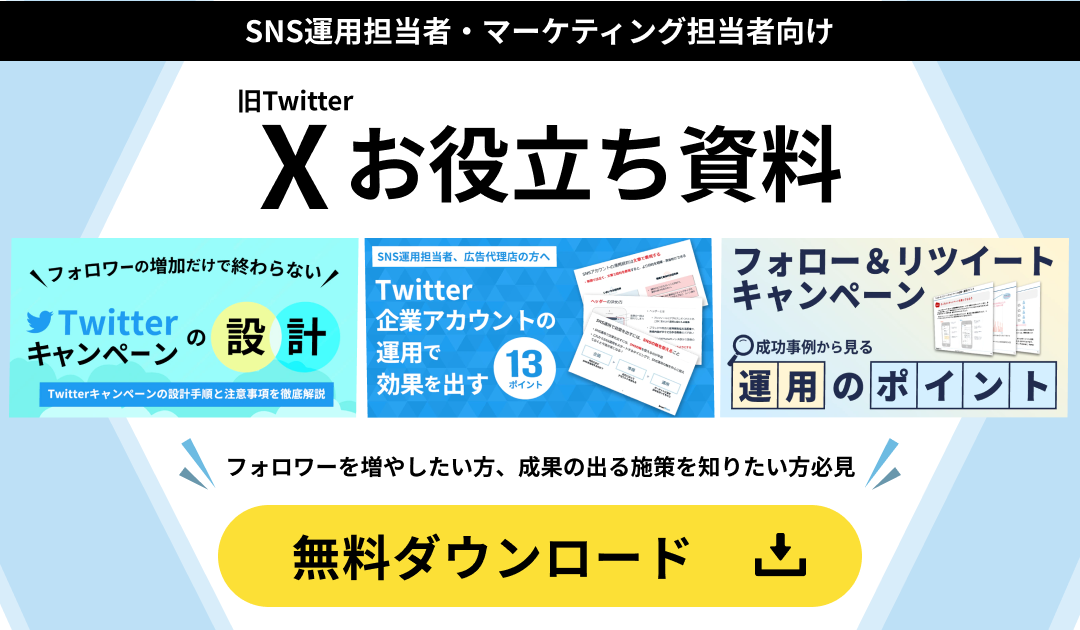X(旧Twitter)の運用で成果を上げるには、アクティブユーザー数が多い時間帯を狙って投稿することが重要視されています。
夜の時間帯がゴールデンタイムと言われていますが、他の時間帯ではユーザーの傾向にどのような違いがあるのでしょうか?
この記事では、Twitter運用における最適な投稿時間や曜日ごとの傾向、ツイートが拡散されやすくなるポイントなどについて解説します。
以下の資料では、X(旧Twitter)をはじめとした日本国内で利用されているSNSの利用状況と具体的な活用シーンを効果別に解説しています。
「X(旧Twitter)の利用状況やユーザー属性が知りたい」「自社のサービスはどのSNSが合うの?」とお悩みの方は是非ご参考ください。
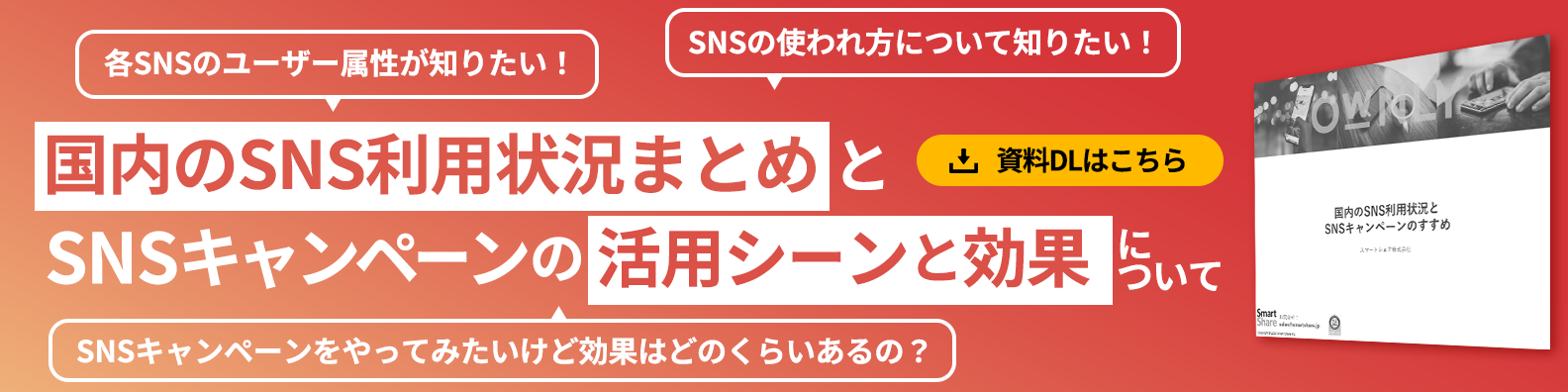
X(旧Twitter)運用で投稿時間を意識するべき理由
Twitter運用で成果を上げるには、投稿する時間帯を意識することが大切です。ツイートの時間帯が重要視されている理由には、下記が挙げられます。
- アクティブ率の変動が大きいため
- フォロワーやエンゲージメントに関係するため
ここでは、それぞれ順に解説していきます。
アクティブ率の変動が大きいため
X(旧Twitter)を利用しているユーザーのアクティブ率は、時間帯によって大きく異なります。アクティブ率が高い時間帯にツイートすれば、それだけ多くの人に投稿を見てもらえる可能性が高まります。
反対に、自社のターゲット層が活発でない時間帯に投稿した場合、魅力的なツイートをしたとしてもユーザーからの反応は薄くなってしまうのです。
投稿は思いつきではなく、タイミングを見極めて戦略的に行う必要があると言えるでしょう。
フォロワーやエンゲージメントに関係するため
投稿した内容が多くの人の目に留まると、いいねやリツイート、リプライなどのアクションをもらえる可能性が高まります。
多くのユーザーに拡散されれば、さらに他のユーザーへと拡散が広がる二次拡散が期待できます。
アクティブユーザーが多い時間帯にツイートすることで、エンゲージメント向上やフォロワー獲得などにつながるでしょう。
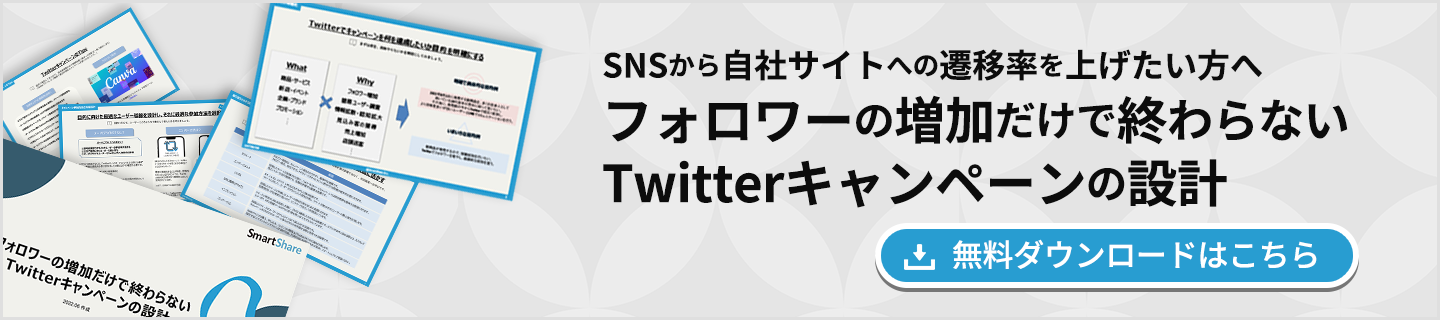
X(旧Twitter)のおすすめ投稿時間
ここからは、一般的にアクティブユーザー数が多いと言われる時間帯を紹介します。
ただし、ユーザー属性によってアクティブな時間帯は異なります。そのため一概にこの時間帯がおすすめとは言えません。
自社のターゲット層をよく見極めたうえで、最適な時間帯に投稿することを心がけましょう。
7~8時・土日8~10時|通勤・通学の時間帯
Twitterのアクティブ率は深夜から早朝にかけて落ち込み、朝の7~8時になるとTwitterを利用するユーザーが増加傾向になります。
通勤・通学の時間帯である朝の7~8時は、社会人や学生が電車やバスで移動しているスキマ時間に、スマホでTwitterをチェックする人が多くいます。
なお、土日は平日に比べて起床時間が遅くなるユーザーも多いので、8~10時頃がおすすめの時間帯です。
朝はSNSをチェックするユーザーは多いものの、投稿するユーザーはそれほど多くありません。そのため、リーチ数を増やしエンゲージされやすい穴場の時間帯とも言えるのです。
この通勤・通学のピークタイムを過ぎると、徐々にアクティブユーザーの数は減っていく傾向です。
平日・土日12~13時|お昼休憩や昼食の時間帯
お昼休憩やランチタイムとなる12~13時の時間帯は、平日・休日どちらもSNSのユーザー数が増える傾向にあります。
学生や社会人が昼食をしながら、ゆったりとTwitterをチェックするユーザーが多いことが考えられます。
ただし、アクティブユーザー数が多いぶん、投稿されるツイートも増加するので、タイムラインの流れが早くなることも予想されるでしょう。
画像や動画を活用したりと、ユーザーの目を惹き注目を集められるような工夫をしましょう。
13時を過ぎると、お昼休憩が終わる人が増えてアクティブ率も下がります。
平日・土日15~17時|休憩や放課後
午後の授業や仕事がひと段落つく15~17時頃も、おすすめの投稿時間帯です。とくに16時以降は放課後の時間帯となるので、学生の利用者数が増える傾向にあります。
中学生・高校生・大学生など若年層をメインターゲットにしている場合は、この放課後時間帯を狙った投稿が効果的と言えるでしょう。
また、夕食の支度を始める前の時間帯でもあるので、家事が落ち着いたスキマ時間で主婦層がTwitterをチェックしているケースも多いです。
平日・土日20~22時|ゴールデンタイム
1日のうち最もアクティブユーザー数が多いのが、20~22時の時間帯です。夕食後から就寝までの間で自由な時間を過ごす人が多く、ゴールデンタイムとも呼ばれています。
平日・休日問わずアクティブ率が高くなるので、さまざまなジャンルでの投稿に向いています。ただし、この時間帯は投稿するユーザーの割合がもっとも多くなるので、投稿が埋もれてしまいがちな点に注意しましょう。
ゴールデンタイムに投稿する場合は、ユーザーの興味関心を惹く投稿を心がける必要があります。
【曜日別】X(旧Twitter)アクティブユーザーの傾向
アクティブユーザーの増減は、時間帯だけでなく曜日も関係しています。
ここでは、平日・休日におけるアクティブユーザーの傾向を解説します。
平日は曜日による違いはほとんどない
月~金曜日の平日は、曜日によって多少の変化はあってもユーザーの行動に大きな違いはないようです。これは月曜日から金曜日までの5日間、多くの人は同じルーティンを繰り返しているためと考えられます。
朝の6時に起床して12時にお昼休憩を取り、17時に退社する、というように、時間軸において1日の過ごし方にほとんど変化はありません。
平日にTwitter投稿をする際は、曜日にこだわるよりは、アクティブ率が高い時間帯を狙ってツイートするほうが効果が高いと言えるでしょう。
休日は平日に比べてアクティブ率が高い
一般的な休日とされる土日祝は、平日に比べると、1日を通してアクティブ率が高いことが分かっています。中でも休日の午後はとくにアクティブユーザー数が多く、拡散効果やエンゲージメント率向上が見込める時間帯です。
休日にじっくりとSNS投稿をさかのぼったり検索したりするユーザーも多く、フォロワー以外のユーザーにも情報を届けやすくなります。
マーケティングやビジネスとしてSNSを運用する場合は、休日に投稿するのは億劫に感じる人もいるかもしれません。
しかし、休日にしっかり情報発信することで他社との差別化にもなるため、予約投稿などを活用して、積極的に投稿するのがおすすめです。
アクティブユーザーが多い=エンゲージメント率が高いとは限らない
ユーザーのアクティブ率が高い時間帯に投稿すれば、多くの人に見てもらえると考えがちですが、必ずしもエンゲージメント率が高まるとは限りません。
多くの投稿が流れる時間帯ほど、競合の情報も多くなり、ユーザーの注意を引くのが難しくなるためです。
また、ユーザーが「見ているだけ」の状態であることも多く、いいねやリポストなどのアクションにはつながらないケースもあります。
大切なのは「どのタイミングなら、自分のフォロワーが反応しやすいか」を見極めることです。
時間帯の傾向に加えて、自社の投稿ジャンルやトーンに合ったタイミングを見つけることで、効率よくエンゲージメントを高めることができます。
Twitterの投稿時間における運用のポイント
Twitterで投稿時間帯を意識するときは、下記のポイントも大切です。
- アクティブ率が高い時間より前に投稿する
- 2. ゴールデンタイムだけにこだわらない
- 投稿頻度を高める
- セルフリツイートを活用する
- 滞在時間を伸ばすコンテンツを企画する
- ハッシュタグを活用してトレンドを取り入れる
- インフルエンサーを起用して拡散する
- 予約投稿を活用する
- 自社のフォロワー属性を分析する
- 時間帯・曜日・投稿内容のテストをおこなう
ここからは、運用のポイントについて解説します。
1. アクティブ率が高い時間より前に投稿する
X(旧Twitter)では、ユーザーが多く利用する時間帯を狙って投稿することが基本ですが、「アクティブ率が高い時間帯の少し前」に投稿しておくのが効果的です。
たとえば、通勤時間帯の7時台や昼休みの12時前後は投稿が集中しやすい傾向にあります。
そのため、投稿直後に一定のリアクションを得られなければ、アルゴリズムによって露出の機会が減ってしまいます。
そのため、7時に注目が集まるなら6時半〜6時45分頃に投稿することで、ユーザーのタイムラインに表示されやすくなるでしょう。
リアルタイム性が高いXでは、短時間で反応を集めることが拡散のコツとなるため、投稿タイミングの微調整が非常に重要です。
2. ゴールデンタイムだけにこだわらない
20~22時はアクティブユーザー数が最も多いものの、ゴールデンタイムだけにこだわる必要はありません。
むしろこの時間帯はすぐに投稿が埋もれてしまう可能性が高く、投稿が逆効果になってしまうこともあるのです。
さまざまな時間帯での投稿を試し、長期的な視点でどの時間帯がよいかを見極め、1日複数回投稿することをおすすめします。
3. 投稿頻度を高める
ユーザーがアクティブな時間帯に投稿したとしても、1日1回の投稿ではすぐに埋もれて見てもらえない可能性があります。
ほぼ毎日複数回のツイートをする企業も数多く存在するので、投稿頻度を高めることを意識するといいでしょう。
Twitter上のトレンドや話題を常にチェックして、話題性の高いトレンドに便乗するなど、あらゆる角度からツイートネタを探すのがおすすめです。
4. セルフリツイートを活用する
投稿のタイミングによっては、投稿が他のツイートに埋もれてしまうことがあります。多くリーチできなかったり、タイミングを誤ってしまったりしたときは、セルフリツイートを活用しましょう。
セルフリツイートによって過去のコンテンツを再度タイムラインに表示させられるので、一度はリーチできなかったユーザーに情報を届けることができます。
しかし同じ投稿に集中しすぎたり、セルフリツイートの頻度が多すぎると、ユーザーにしつこいと思わせてしまう可能性もあるので注意しましょう。
5. 滞在時間を伸ばすコンテンツを企画する
投稿時間を工夫するだけでなく、ユーザーの目に留まったあとに「滞在してもらえる投稿内容」を意識することも大切です。
たとえば、画像や動画つきの投稿や、思わず続きを見たくなるスレッド形式の投稿は、タイムライン上での滞在時間を伸ばしやすくなります。
とくに多くの投稿が流れてくる時間帯には、ただ投稿するだけでなく、ユーザーがその投稿に留まってくれる工夫が必要です。
伝えたい情報を詰め込むのではなく、冒頭に目を引く一文を置いたり、あえて余白や間を持たせたりすることで、読み進めたくなる投稿を目指しましょう。
6. ハッシュタグを活用してトレンドを取り入れる
投稿時間を意識する際は、その時間帯に話題になっているハッシュタグやトレンドワードを活用することで、投稿の露出を高めやすくなります。
たとえば、朝の時間帯にはニュース系や日常の習慣に関するトピック、夜はエンタメや感情的な投稿がトレンドに入りやすい傾向があります。
こうした傾向を踏まえ、その時間帯に話題になっているキーワードを含めて投稿すると、タイムラインに表示される可能性が高まります。
ハッシュタグを活用する際は、過剰に入れすぎず、関連性のあるものに絞ることがポイントです。
また、投稿内容とハッシュタグが噛み合っていないと逆効果になる場合もあるため、話題性と自社アカウントの文脈をすり合わせて活用しましょう。
7. インフルエンサーを起用して拡散する
投稿の反応を高めたい時間帯に合わせて、インフルエンサーとの連携を図るのも有効な手段です。
フォロワー数が多く、投稿の拡散力を持つインフルエンサーが投稿を引用・シェアすることで、自社の投稿もより多くの人の目に触れやすくなります。
とくにユーザーが多く集まる時間帯にあわせてインフルエンサーを起用することで、効果はより高まります。
キャンペーンや新商品告知など、時間を意識したタイミングの投稿は、事前の打ち合わせや調整が肝心です。
フォロワーとの相性や投稿内容のトーンを合わせることで、自然な流れで拡散されやすくなります。
拡散の時間帯を逆算し、投稿時間だけでなく「誰が、いつ」発信するかも含めて設計しましょう。
8. 予約投稿を活用する
狙いたい時間帯に合わせた計画的な運用には、予約投稿の活用が非常に有効です。
狙った時間に毎回手動で投稿するのは手間がかかるうえ、投稿ミスや遅れが生じる可能性もあります。
Xの公式機能や外部ツールを利用すれば、事前に投稿時間を設定しておくことが可能です。曜日や時間帯ごとのパターンを把握しやすくなり、安定した運用にもつながります。
また、投稿時間を固定化することで、フォロワーにとっても「この時間に投稿される」という認識が生まれやすくなり、エンゲージメントの向上が期待できます。
9. 自社のフォロワー属性を分析する
Twitterでアクティブ率が高い時間帯はある程度決まっているものの、ターゲット層によって活発な時間帯に違いがあることを理解しておきましょう。
たとえば、会社や学校でスマートフォンをチェックできない時間帯には、アクティブユーザー数が少なくなります。
しかし主婦や高齢者向けの情報発信をするアカウントなら、朝〜昼頃の時間帯のほうがターゲットに見てもらいやすくなることが予想できます。
このように、自社のターゲット層がどんな時間帯にアクティブなのか、分析しながら運用していくことが大切です。

10. 時間帯・曜日・投稿内容のテストをおこなう
投稿時間を最適化するには、「時間帯」「曜日」「投稿内容」の組み合わせごとに反応を見ていくことが大切です。
X(旧Twitter)は業種やフォロワー層によって反応の出やすいタイミングが異なるため、一般的な傾向だけで判断するのは不十分です。
たとえば、同じ内容の投稿を平日・休日や異なる時間帯に分けて投稿し、それぞれの反応を比較することで、最も効果的な組み合わせを見つけやすくなります。
さらに、投稿のトーンや形式によっても最適な時間が変わる場合があるため、複数の視点で検証することが重要です。
投稿ごとに数値を記録し、「どの曜日・時間帯に、どんな投稿が効果的だったか」を定期的に振り返ることで、精度の高い運用につながります。
■関連記事
Twitterのアルゴリズムを攻略するには?運用担当者必見のコツや施策
SNS別の伸びやすい投稿時間
X(旧Twitter)の投稿時間を最適化する際は、ほかのSNSの傾向も合わせて把握しておくと、時間帯を比較しながら運用方針を決めやすくなります。
媒体ごとにユーザーの行動パターンが異なるため、同じ内容でも伸びやすい時間帯が変わります。
ここでは代表的なSNSの傾向を解説します。
Instagram
Instagramで設定されることが多い投稿時間は、次のとおりです。
Instagramは20〜30代の利用者が多く、生活のリズムに合わせてアプリが開かれる傾向があります。朝の準備前後や昼休憩、夜のリラックス時間にフィードやリールの閲覧が増えやすい傾向です。
画像や動画の形式に応じて、投稿時間を使い分けると効果的です。
たとえば、リールは夜帯、フィード投稿は昼や夕方など、利用シーンに合わせて配分すると安定した反応が得られるでしょう。
Facebook
Facebookで利用されることが多い投稿時間は、次のとおりです。
Facebookは30〜50代の利用が中心で、仕事の合間や帰宅後にタイムラインを確認する人が多い傾向があります。平日の投稿が動きやすく、業務終了後の時間帯に反応がまとまりやすいのが特徴です。
企業ページの投稿は、個人アカウントと比べて露出が限定される場合があります。
投稿時間の調整に加えて広告を併用したり、他のSNSと使い分けたりすると運用しやすくなるでしょう。
TikTok
TikTokで利用されることが多い投稿時間は、次のとおりです。
TikTokは10〜20代の利用比率が高く、通学前後や夕方の時間帯にアプリが開かれやすい特徴があります。
夜間から深夜にかけては、おすすめ欄の回遊が増えるため、夜間を投稿枠として使うアカウントも多く見られます。
朝・夕方・深夜の3つを軸に分けてテストすることで、ターゲットごとに適切な投稿時間帯を把握しやすくなるでしょう。
YouTube
YouTubeで利用されることが多い投稿時間は、次のとおりです。
YouTubeは幅広い年齢層に利用されており、特に20〜40代の視聴者が多くを占めます。
昼休憩や帰宅後など、まとまった時間が取りやすいタイミングに再生が増える傾向があります。
ショート動画は、朝やすき間時間の投稿でも再生が伸びる場合があります。再生リストや通知など複数の入口から視聴が発生するため、動画の長さやテーマに合わせて投稿時間を調整すると効率的です。
YouTubeは他SNSと異なり、公開直後だけでなく、検索や関連動画から長期間再生される仕組みを持っています。短期的な反応だけで判断せず、コンテンツに合った時間帯を軸に運用を続けることが大切です。
X(旧Twitter)の投稿時間についてのよくある質問
投稿時間を意識した運用に関しては、目的や投稿内容によって最適なタイミングが変わります。
ここでは、Xで投稿を伸ばしたい・拡散させたいときに多く寄せられる質問をまとめました。
平日で伸びる・拡散されやすい時間は?
X(旧Twitter)で投稿が伸びやすい時間帯は、ユーザーの活動が集中する朝・昼・夜の3つに分けられます。
|
時間帯
|
特徴
|
|
7〜8時
|
通勤・通学の時間帯で、移動中にアプリを開く人が多い
|
|
12〜13時
|
昼休憩中の利用が増え、ツイートの閲覧・反応が活発になる
|
|
20〜22時
|
1日の中で最もアクティブ率が高い時間帯
|
朝は投稿数が少なく、タイムライン上で目立ちやすいため、リーチを伸ばしやすい時間帯です。昼は社会人や学生が休憩中に利用するケースが多く、画像や動画など視覚的な投稿が反応を得やすくなります。
夜は幅広い層が利用するゴールデンタイムで、エンタメやトレンド系の投稿と相性が良いです。
ターゲットの生活リズムを想定し、これらの時間を基準に投稿をテストすると、安定した反応を得やすくなるでしょう。
投稿時間は関係ないって本当?
X運用において投稿時間は重要ですが、投稿時間だけで表示が決まるわけではありません。X(旧Twitter)はタイムラインの表示が完全な時系列ではなく、エンゲージメントや関心度によって順序が変わる仕組みです。そのため、時間よりも投稿内容や反応率のほうがリーチを左右します。
一方で、利用者が多い時間帯に投稿すれば、目に触れる機会が増える可能性があります。
重要なのは、時間を固定することではなく、狙いたいユーザーがアクティブな時間を意識しながら投稿を重ね、反応が得やすいタイミングを見つけることです。
イラスト投稿が伸びやすい時間は?
イラスト投稿は、閲覧や共有の時間が取りやすい夜の時間帯に反応が集まりやすい傾向があります。
- 平日:20〜23時
- 土日:10〜12時・20〜23時
夜間帯は投稿数も増えますが、ファンアートやトレンド系のイラストが拡散されやすい時間帯でもあります。
自分の作品が見られやすい時間を確認し、定期的に投稿することで安定した反応を得られるでしょう。
自社X(旧Twitter)の最適な投稿時間を見極めて運用しよう
Twitterは数あるソーシャルメディアの中でも、とくに拡散性が強いプラットフォームです。他のSNSと比較して利用者数も多いので、いかにユーザーに見てもらえるかが肝となります。
自社におけるアクティブユーザーの傾向を把握して、どのような戦略や施策を立てていくかを検討することで、効果的なマーケティングが行えるでしょう。
以下の資料では、Twitter運用を成功させる施策やノウハウなど、Twitterマーケティングに関するさまざまなお役立ち情報を発信しています。
Twitterマーケティングを成功させたい方や、Twitter運用を本格的にチャレンジしたいと考えている方は、ぜひ下記からご覧ください。