自社商品やブランドに愛着を持つファンを増やし、安定的な売上基盤を構築する「ファンマーケティング」が注目されています。
ファンを増やすことができれば、口コミの拡散や継続率の向上によって、安定的にビジネスを成長させることが可能です。
そんな中、「ファンマーケティングは具体的にどういうもの?」「実施するメリットや戦略のポイントが知りたい」とお考えの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、ファンマーケティングの基礎知識やメリット・デメリット、具体的なSNS戦略のポイントなどについて解説します。
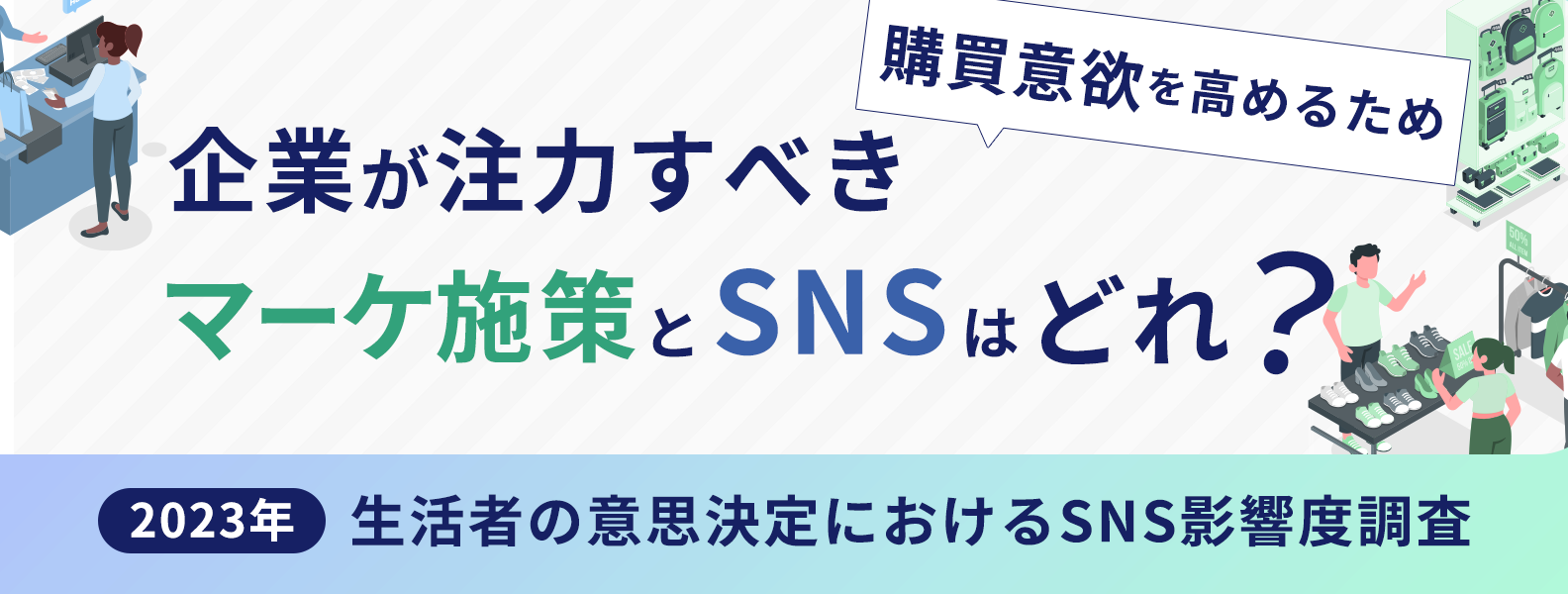
ファンマーケティングとは?
ファンマーケティングは、企業や商品、ブランドへの愛着を持つファンを増やすことで、中長期的に売上を拡大するマーケティング手法です。
従来はマスメディアの広告が主流でしたが、現在はインターネットの普及により、SNSやWEBサイトを通じた情報拡散が可能となりました。
効果的な施策としては、SNSやライブ配信の活用、クラウドファンディングの実施、ファンが集まるコミュニティの構築があります。とくに、ユーザー同士の交流を深める場の提供が重要とされています。
ファンによる口コミや情報発信によって、新規顧客の獲得やリピート率の向上、商品の改善や開発に役立てることが可能です。
ファンマーケティングが注目される背景
顧客は、インターネットやSNSを通じて商品の口コミやレビューを自由に発信し、情報収集も簡単に行えるようになりました。
そのため、企業からの情報発信よりも、実際のリアルな使用感が伝わる口コミが消費者に大きな影響を与える傾向があります。
とくに、ファンからの肯定的な口コミは「バズ」の可能性を秘めています。
しかし、口コミには肯定的な意見だけでなく、否定的な意見も含まれるでしょう。否定的な意見はマイナスの感情を引き起こす可能性があります。
これらは適切に分析して商品やサービスに反映することで、サービスの改善につなげることができるでしょう。
ファンマーケティングを実施するメリット
ファンマーケティングを実施するメリットには、以下が挙げられます。
- 口コミによって新規顧客が増加する
- 売上やLTVの向上につながる
- 消費者目線の開発・改善が行える
- 広告費削減につながる
それぞれのメリットについて見ていきましょう。
口コミによって新規顧客が増加する
ファンはSNSなどを利用して、自分が気に入った商品やサービスについて情報を積極的に発信します。消費者は企業からの情報よりも、他の消費者からの口コミに対して敏感に反応する傾向にあります。
そのため、ファンマーケティングをうまく行うことで、良質な口コミが生まれ、新規顧客の獲得をスムーズに進めることにつながるでしょう。
一般的には、新規顧客を獲得するには、既存の顧客を維持するための5倍程度のコストや時間が必要と言われています。
顧客獲得コストを削減して売上を大きく伸ばすためにも、新規顧客をスムーズに獲得できるファンマーケティングが有効です。
売上やLTVの向上につながる
ファンマーケティングを実施することによって、売上アップやLTV向上につながる点がメリットです。
LTV(ライフタイムバリュー)とは、顧客が生涯にわたってもたらす利益の総額を指します。1回の取引から得られる利益だけでなく、2回目以降の継続的な取引から得られる利益を考慮に入れたものです。
多くの類似商品が存在し、商品が飽和状態にある「成熟市場」では、新たな需要を創出することは難しいと言えます。そのため、既存顧客であるファンが生む需要が重要です。
ファンは商品を1度だけ購入するのではなく、繰り返し購入してくれる存在です。LTVを高めるためには、ファンの存在が不可欠と言えるでしょう。
消費者目線の開発・改善が行える
顧客が製品やサービスのファンになると、顧客から良質なフィードバックを得ることができます。
ファンは企業が気づかない商品やブランドの価値やニーズを見つけてくれるため、商品の開発や改善に活かせるでしょう。
また、以下のような取り組みも効果的です。
- 共創:ファンが企業と協力して新商品やサービスを開発する活動
- モニター:開発段階のプロトタイプなどをファンに評価してもらう活動
|
一般的には、良質なフィードバックを得るためには、製品やサービスの割引や調査など、一定のコストがかかることが多いです。
そのため、ファンからの良質なフィードバックを得られやすいことはコスト削減の視点においても大きな利点と言えます。
広告費削減につながる
ファンマーケティングを実施することで、広告費を削減することが可能になります。
ファンになった顧客は、自分が支持する商品やサービスを他の人に知ってもらいたいと思い、自発的に宣伝活動を行います。
先述のとおり、SNSでの宣伝や商品レビューは大きな影響力を持っています。
商品やサービスを実際に体験した人々からの口コミは、企業自身が商品を宣伝するよりも効果的です。結果的に、広告費を削減することにつながるでしょう。
ファンマーケティングを実施するデメリット
ファンマーケティングを実施する際は、いくつかデメリットも理解しておきましょう。
それぞれのデメリットについて解説します。
中長期的な視点が必要になる
ファンマーケティングは、ファンを獲得して育成するまでに期間がかかるため、初めてすぐに成果が出るようなものではありません。中長期的な視点でマーケティング施策を展開していく必要があります。
時間が経つほど企業としてのストーリーが生まれやすく、それに共感して顧客はファンになっていきます。
この中長期的な施策が参入障壁となるため、ファンマーケティングを上手く構築できれば、企業にとって大きな差別化のポイントとなるでしょう。
炎上リスクがある
ファンマーケティングは、一般的なマーケティング手法に比べて顧客との距離感が近い手法です。そのため、思いがけない形で情報が広がり、炎上するリスクがあることも否めません。
たとえば、企業に勤める人の本音や人柄が分かるような情報を発信している場合に、意図的でなくとも、反感を買ってしまう可能性があります。
ファンマーケティングに限らず、炎上リスクに関する対策やガイドラインを設置しておくと安心です。
ファンマーケティングで効果的な施策6選
ファンマーケティングでは、企業からの一方的な情報発信ではなく、ファンが主体的に関われる施策設計が重要です。
- SNSの参加型キャンペーン
- ファンコミュニティの運営
- サブスクリプションサービス
- 共創型商品開発
- アンバサダー制度導入
- サンプリング体験会
ここでは、ファンとの関係性を深め、継続的な支持につなげやすい代表的な施策を6つ紹介します。
1. SNSの参加型キャンペーン
SNSの参加型キャンペーンは、ファンに投稿や投票などの行動を促し、ブランドとの接点を増やせる施策です。
いいねやコメント、ハッシュタグ投稿など、日常的な操作で参加できるため、負担が少なく実施できます。参加方法はできるだけシンプルにし、条件や流れを明確に伝えることが重要です。
認知拡大だけでなく、ファンとの関係を継続的に深める手段として活用しやすい施策です。
■関連記事
【2025年最新】SNSキャンペーン成功事例34選|効果や成功のポイントも解説
2. ファンコミュニティの運営
ファンコミュニティの運営は、継続的にファンと接点を持ち、関係性を深めやすい施策です。
SNSの非公開グループやコミュニティツールを活用することで、共通の関心を持つユーザー同士が交流できる場を作れます。
運営側は一方的に情報を発信するのではなく、質問や意見募集などを通じて会話を生み出すことが重要です。コミュニティ内で得られた声は、商品改善や施策立案にも活かせます。
3. サブスクリプションサービス
サブスクリプションサービスは、定期的な提供を通じてファンとの接点を継続できる施策です。
毎月の商品配送や会員限定コンテンツなど、一定の頻度で接触機会を作れる点が特徴です。
内容に対して価格が高すぎると継続が難しくなるため、無理なく続けられる設計が求められます。また、会員限定の情報発信や先行販売を行うことで、特別感を演出できます。
解約理由や継続状況を確認しながら、必要に応じて内容を調整することが重要です。
4. 共創型商品開発
共創型商品開発は、ファンの意見やアイデアを商品づくりに反映する施策です。
アンケートや投票で要望を集めたり、試作品への意見を募ったりすることで、実際の声を企画に活かせます
すべての意見を反映する必要はありませんが、どのように活かしたかを丁寧に説明することが重要です。参加した実感が残ることで、商品への愛着や支持につながるでしょう。
■関連記事
共創マーケティングとは?メリットや成功事例、コツについて解説
5. アンバサダー制度導入
アンバサダー制度は、ブランドを継続的に応援してくれるファンに活動を任せる施策です。
商品紹介やイベント参加などを通じて、実際の使用感や感想を発信してもらえます。企業発信よりも自然に情報が伝わりやすく、信頼性も高まりやすい点が特徴です。
選定時は、フォロワー数だけでなく、投稿内容やブランドとの相性を重視しましょう。活動内容やルールを明確にすることで、無理のない運用につながります。
■関連記事
アンバサダーマーケティングとは?メリット・デメリットや費用相場・成功事例も紹介
6. サンプリング体験会
サンプリング体験会は、商品やサービスを実際に試してもらい、率直な感想を得られる施策です。
オンラインイベントや店舗、ポップアップなど、実施方法は目的に応じて選びましょう。事前に参加条件や体験内容を明確に伝えることで、期待とのズレを防げます。
体験後にアンケートやコメントを回収すれば、改善点の把握にも役立つでしょう。感想の一部を紹介すると、参加者の声を活かした発信にもつながります。
ファンマーケティングのSNS戦略を検討するポイント7つ
ファンマーケティングを実施するときは、SNSやWebサイトの活用が必要不可欠です。
ここからは、SNSにおけるファンマーケティング戦略を検討する際のポイントについて見ていきましょう。
- 企業理念やコンセプトを明確にする
- ファンを定義する
- ファンと積極的にコミュニケーションを取る
- ファン同士のコミュニティを提供する
- 売上をKPIに設定しない
- ファンの意見を収集・活用する
- 社内の運用体制を整える
ここでは、それぞれのポイントについて解説します。
1. 企業理念やコンセプトを明確にする
ファンマーケティングを実施するときは、企業理念やコンセプトを明確にすることが大切です。
企業理念やコンセプトに共感してくれる人が増えれば、長期的に企業やブランドに愛着を持ってくれるファンを育成しやすくなるでしょう。
単純に商品の性能やサービスの魅力を訴求するだけでなく、企業の理念やビジョンに共感してもらえるような発信を行うのがおすすめです。
2. ファンを定義する
そもそもファンとは、どのような人を指すかについて定義しましょう。
ファンの定義は企業によってさまざまですが、世界観や価値観に共感し、商品やサービスを多く使用してくれるような人物が当てはまります。
「利用金額が大きい人」がファンと定義されがちですが、そうではありません。
具体的にファンを定義するには、「購買データ」や「感情データ(顧客ロイヤリティ」)の2軸から考えるのがいいでしょう。
3. ファンと積極的にコミュニケーションを取る
ファンマーケティングを成功させるには、ファンとの密なコミュニケーションが非常に重要です。
実際に、ファンマーケティングに実施している企業は多いため、コミュニケーションの密度で差別化を図ることもポイントとなります。
自社商品やサービスを利用して投稿しているユーザーに、いいねやコメント、リポストなどで反応するなどのアクションが挙げられます。
4. ファン同士のコミュニティを提供する
ファン同士がつながり交流できるコミュニティサイトや、ファンミーティングを実施したりするのも効果的です。
ファン同士が交流を深めることで、ファンとの接点を持ちやすくなったり、ファン同士の会話から新たなアイデアを得たりすることができます。
ここで注意すべきなのは、会話や交流を野放しにしないことです。ファンの会話は時にネガティブな方向に進んでしまうことがあるためです。
5. 売上をKPIに設定しない
ファンマーケティングは、ファンを獲得・育成することで中長期的に利益につなげていくマーケティング施策です。
そのため、KPI(重要成果指標)を「売上」に設定すると、適切にファンマーケティングの効果測定を行うのが困難になってしまいます。
たとえば、ファンマーケティングの場合はリピート購買数やLTV、エンゲージメント、顧客満足度などをKPIに設定するのがおすすめです。
6. ファンの意見を収集・活用する
ファンマーケティングにおけるSNS戦略では、ファンの意見を継続的に集め、運用や施策に反映する姿勢が欠かせません。
コメントや引用投稿、アンケート機能などを活用すれば、日常的な反応を自然な形で収集できます。
意見を集める際は、質問内容を具体的にし、ユーザーが回答しやすい形に整えることが重要です。集まった声は、商品改善や企画立案だけでなく、投稿内容の見直しにも役立ちます。
また、意見を受け取ったままにせず、反映した内容や対応結果を発信すると、ファンとの信頼関係が深まります。SNSを一方的な発信の場にするのではなく、顧客の声を活かす運用を意識しましょう。
7. 社内の運用体制を整える
ファンマーケティングのSNS戦略を継続的に進めるには、社内の運用体制を整えることが重要です。
担当者が曖昧なままだと、投稿内容のブレや対応の遅れが生じやすくなります。
SNS運用ではさまざまな業務が生じるため、企画立案、投稿作成、コメント対応、効果測定など、役割を分けて整理しましょう。
また、判断基準や投稿ルールを事前に共有しておくと、対応の質を保ちやすくなります。複数人で運用する場合は、情報共有の方法も決めておく必要があります。
定期的に振り返りの場を設けることで、改善点を見つけやすくなり、安定した運用につながります。
ファンマーケティングを実施するときの注意点
ファンマーケティングを実施するときは、商品やサービスのプロモーションばかりをしすぎないよう注意しましょう。
たとえば、ファンコミュニティを運営する上で、ファンに価値提供ではなく商品のプロモーションばかりを流すと、ファンが抵抗を覚える可能性があります。
セールス感が強すぎるとファンは「売り込まれている」と感じてしまうので、ファン自ら進んで商品を購入してもらうように熱量を高める施策を行いましょう。
また、ファンマーケティングに一貫性がないとがっかりさせてしまうため、ファン視点でマーケティング施策を立案することが大切です。
ファンマーケティングの成功事例3選
ここからは、ファンマーケティングの成功事例について紹介します。
1. よなよなの里

参照:よなよなエール公式サイト
クラフトビールメーカーの「ヤッホーブルーイング」では、オウンドメディアやSNSでの交流、ファン同士が交流するイベントの開催などさまざまな施策を打ち出しています。
定期的にオンラインファンミーティングが開催されており、年内に忘年会のような感覚で参加できるイベント「〆宴」を開催しているのが代表的です。
〆宴では、参加者が楽しめる多数のイベントが実施されており、オフラインではなくWeb会議ツールを使用してオンラインイベントを行っているのも特徴です。
オンラインミーティングでは、大抽選会なども開催されており、参加すると豪華な景品がもらえることで、イベントの集客やファンのロイヤリティ向上につながっています。
また、SNS上ではハッシュタグキャンペーンを実施しており、X(Twitter)やInstagramでの〆宴の盛り上がりを見せています。
2. ワークマン

作業服を販売する株式会社ワークマンでは、自社ブランドのファンを起用する「公式アンバサダー制度」を設けています。
公式アンバサダーを起用し、インフルエンサーマーケティングのように、同社商品に関する情報発信を積極的に行っています。
アンバサダーにはいち早くワークマン製品を見て発信できる新製品発表会に招待したり、新製品のモニターやアンケートを依頼したりするというものです。
SNSを中心に同社商品のUGCが投稿されるため、ユーザーとブランドとの接点が増えることで認知度向上につながっています。
広告費を抑えつつ新規顧客の獲得につながっており、アンバサダー自身の満足度向上にも寄与しているといえるでしょう。
3. チロルチョコ

参照:チロルフェス2023
チロルチョコ株式会社では、日本でロングセラーとなっているチョコレート駄菓子「チロルチョコ」のファンマーケティングを取り入れています。
代表的な施策としてリアルファンイベント「チロルフェス」が開催されており、100名以上のチロルチョコファンが来場しました。
チロルチョコ専用箱のワークショップや新商品プレゼント大会、オリジナルグッズの販売、イベント限定展示品などさまざまなコンテンツを提供しました。
また、会場にはフォトスポットを展示することで記念写真を楽しむ様子がSNSに積極的に投稿され、「#チロルフェス2023」がX(Twitter)でトレンド入りし話題になっています。
■関連記事
共創マーケティングとは?メリットや成功事例、コツについて解説
企業SNSでファンマーケティング戦略を展開しよう
ファンマーケティングは、中長期的な視点でファンを増やして売上を安定化することを前提としたマーケティング戦略です。
中でも、ユーザーによる口コミや発信(UGC)は、ファンとの交流を深めるだけでなく、新規顧客を獲得するために非常に効果的と言えます。
また、UGCはSNSマーケティングを実施する上で必要不可欠な存在です。
ファンマーケティングの実施を検討している方は、まずはUGCの創出や活用から始めてみてはいかがでしょうか。
UGCの活用を効率化にするには、ぜひ下記の資料をチェックしてみてください。

