いまや"炎上"は、企業にとって最も恐れる事態ではないでしょうか。オンライン・オフライン問わず、"炎上対策"は色んなところで語られています。
炎上対策として「炎上したら早めに謝罪することで、事態を鎮静化できる」という意見をしばしば耳にします。しかし、最近の炎上事例を見ていると、状況によっては「早期に謝罪する」が逆効果になってしまう場合もあるかもしれません。
どんな状態であれば、対応が必要になるのかについて解説します。
「炎上」かどうかを判断するのは"主観"
そもそも炎上とは何でしょうか?
「炎上」という言葉の定義としては
- インターネット上で
- 収集がつかないほど多くの
- 批判が集中すること
ということになります。なんだか曖昧だと感じませんか?
「①インターネット上で」は、いいとして。
「②収集がつかないほど多く」が具体的にどのくらいなのかは難しいです。
批判意見が10件で「炎上した」と感じる場合もあるでしょう。いっぽう立場によっては、1,000件の批判意見でも気にしない人もいます。「多い」は主観だし、またその人の立場によっても異なります。
「③批判が集中すること」といっても、そもそもここで言う批判って何でしょうか。例えばなにか新発売の商品があったとして、それが思いのほか不評で「使いにくい」「買うのは無駄」といった意見があふれたとしても、それを炎上とは呼ばないでしょう。ここでいう批判は、もっと、ブランドや個人そのものに対して嫌悪感を催すような性質のもの。それもやはり主観で、立場によって異なります。
よって、ある話題が「炎上」か否かは、主観によって判断するしかないのです。
なぜ「炎上」が問題なのか?
「炎上」という言葉は、何かとても恐ろしいことが起こっているような印象を受けます。
しかしながら、どんな人・商品・ブランドにも、批判の声は必ずあります。批判すべてが問題なのではなく、批判が問題にならない場合と、対応が必要な場合があるのです。
ここでは、どんな場合に批判が問題になるのかについて解説します。
SNSでは「クラスタ」外の情報は入ってこない
ところで、SNSでは「クラスタ」が自然に形成されています。
各SNS独自のアルゴリズムにより、SNSではより興味のある情報を知り、好きな話題に触れて快適に利用できる仕組みになっています。たとえばTwitterでは、気づけばいつの間にか似たような属性の人でフォロー・フォロワー関係が構築されていますよね。YouTubeでも、今までの視聴履歴に基づいて、次に見るべき動画がオススメされています。
なので、「Twitterのタイムラインが同じ話題で埋め尽くされていたけど、家族に聞いたらこの話題について全然知らなかった」ということも、頻繁に起こり得ます。Twitterユーザーは日本国内で4500万人。10万リツイートされても全体の0.002%です。SNSで盛り上がっているように見えても、その話題を全然知らない人がいたとしても全く不思議ではないのです。
このように、SNSではあえて探さない限り、好きなものや興味ある話題にだけに触れて、不愉快なものを見なくて済むように住み分けされています。
よって、批判的な意見が上がっていたとしても「顧客層ではないクラスタ内」にとどまっているなら、それほど深刻な問題ではないといえます。一部だけで盛り上がっていても、クラスタ外の顧客の目には、めったに触れないからです。
批判が企業にとって不利益なのはどんな場合か
では逆に、批判的な意見が企業にとって問題になるのはどんな時でしょうか?
まず、批判しているのが「メインの顧客層」である場合は明らかに問題です。最も支持を得たい人達から、逆に批判されてしまっているということは、マーケティングの失敗を意味します。
もう一つ問題といえる状況は、批判が特定のクラスタだけにとどまらず、クラスタ外を含む多くの人の目に触れてしまっているときです。
購買を決定する時最も力を持つのは「口コミ」の力です。企業広告は「良いところだけを切り取っているのでは?」と思われがちなので、多くの人はより「生の声」を聞きたいと考えます。
そこで、TwitterやInstagramで検索します。結果、ポジティブな意見を目にしたり、商品の負の側面が大した問題ではないと確信できたりすると、購買に至りやすくなるわけです。(本を買う前に、レビューを調べること、ありますよね)
そしてもちろん、「口コミ」の力が負の方向に働くこともあるのです。
どうも何かやらかしたらしいよ、となれば、あえてここから買わなくても良いかな……と購買を避ける意識が働いてしまいます。批判意見が共感できるものだったりするとなおさらです。
炎上から少し時間が経っても、検索サジェストに関連ワードが残り続けることもあります。商品について何も知らずに検索したとき「〇〇 炎上」とあれば、どうしても見てしまいます。
結論として、批判の声が下記の状態になっている場合は、対応が必要でしょう。
|
まとめ
炎上の定義は実はあいまいで、主観によって判断されるものです。「批判的な意見が多く寄せられ……」という言い方をすることがありますが、これは実はかなり主観的な見方です。
たとえばSNSではクラスタが形成され、話題になっているように見えても、実は仲間内で盛り上がっているだけだった、という状況が往々にして発生します。批判殺到と思いきや、実際はたいして話題になってなかった、など。逆に言えば、批判的な意見が上がったとしても、それが一部のクラスタ内だけにとどまっているならあまり問題はありません。
しかし、「メイン顧客層に批判されている場合」と、「批判の声がクラスタ外に広まった場合」には、批判の声が”負の口コミ”として機能してしまうので、早急な対応が必要です。
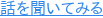













.png?width=260&height=139&name=large%20(8).png)


.png?width=260&height=139&name=large%20(11).png)
.png?width=260&height=139&name=large%20(16).png)


